会社設立までの手順は?必要な手続きと費用の内訳、メリットを網羅的に解説
目次[非表示]
- 1.会社設立までの流れ
- 1.1.Step1. 事業計画の策定
- 1.2.Step2. 会社の基本情報の決定
- 1.3.Step3. 会社用の印鑑(実印)の作成
- 1.4.Step4. 定款の作成
- 1.5.Step5. 定款の認証
- 1.6.Step6. 資本金の払い込み
- 1.7.Step7. 登記申請書類の作成
- 1.8.Step8. 法務局への設立申請
- 1.9.その他 知的財産等の商標登録
- 2.会社設立後の手続き
- 2.1.税務署・都道府県・市町村への届出
- 2.2.社会保険・労働保険の手続き
- 2.3.法定帳簿・備品の準備
- 2.4.法人口座の開設
- 3.会社設立にかかる費用と資本金の調達方法
- 3.1.会社設立費用の内訳
- 3.2.会社設立費用の節約方法
- 3.3.資本金の調達方法
- 4.会社設立のメリットとデメリット
- 4.1.会社設立のメリット
- 4.2.会社設立のデメリット
- 5.会社設立に関するよくある質問
- 5.1.Q. 株式会社と合同会社はどう違う?
- 5.2.Q. 有限会社は設立できる?
- 5.3.Q. 貸借対照表と損益計算書の違いは?
- 5.4.Q. スタートアップ向けの助成金を利用する流れは?
- 5.5.Q. 個人事業主から法人化する際の注意点は?
- 5.6.Q. 起業・会社設立後に顧問弁護士は必要か?
- 6.まとめ
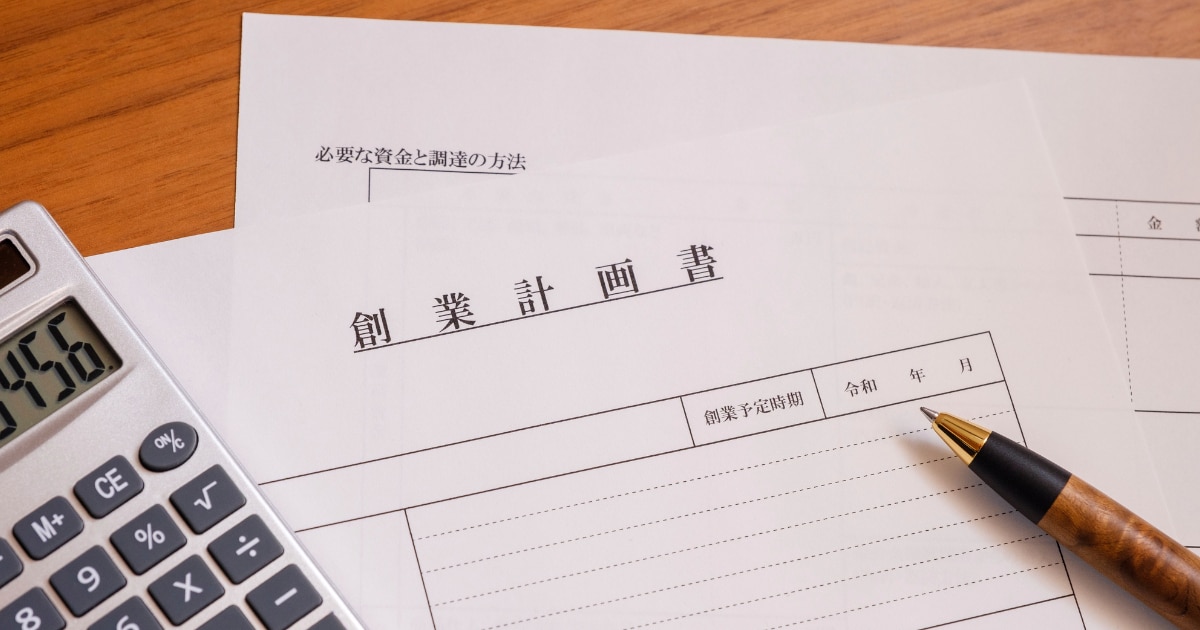
これから会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)を設立する場合、どのような手順で手続きを進めればよいのでしょうか。個人事業主からの法人化(法人成り)や新規事業の立ち上げなど、目的は様々ですが、いずれの場合も法務局へ登記申請を行うまでに多くの手順が必要となります。円滑なスタートを切るためにも、事前に抜け漏れなく準備しておくことが成功の鍵です。
この記事では、会社設立を検討している方に向けて、必要な基礎知識を網羅的に解説します。具体的な手続きの流れから、費用の内訳、設立形態ごとのメリット・デメリットまで、一つひとつ丁寧に説明します。また、法律の専門家から会社設立の支援を受けられる便利な法務サービスALSP(代替法務サービス事業者)もご紹介します。
新規会社設立はもちろん、個人事業主・フリーランスから法人化を検討されている方、関連会社・子会社設立などを検討されている方も、ぜひ本記事を事業計画の参考にしてみてください。
会社設立までの流れ
初めに、一般的な会社設立までの流れを8つのステップに分けて解説します。各ステップで何をすべきかを具体的に把握し、設立手続きへ向けて手順を確認してみましょう。
Step1. 事業計画の策定
会社設立の第一歩は、事業の根幹となる事業計画を具体的に策定することです。まずは市場調査や競合分析を行い、自社の強みやビジネスチャンスを明確にした上で、具体的な事業プランを検討します。
事業内容によっては、行政からの「許認可」が必要な場合があります(例:建設業、不動産業、飲食業、古物商、人材派遣業、食品製造業、医療機関など)。許認可の取得要件(資本金、人員、設備など)は事業によって異なるため、必ず事前に管轄の行政庁に確認し、取得へ向けて詳細を詰めておきましょう。
計画が定まったら、以下の要素を盛り込んだ「事業計画書」を作成します。事業計画書は、融資を受ける際の審査や、協力者を得るためにも重要な書類となります。
- 事業の目的・ビジョン
- 事業内容(提供する商品・サービス)
- 市場・競合分析
- マーケティング・販売戦略
- 人員計画
- 資金計画・収益見通し
Step2. 会社の基本情報の決定
事業計画が固まったら、会社の骨格となる基本情報を決定します。これらは「定款」や「登記申請書」に記載する重要事項です。
会社形態
主な会社形態として「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つが挙げられます。現在、新規設立の多くは株式会社または合同会社です。形態によって法律上の扱いや税金、社会的信用度などに違いがあるため、事業の目的や規模にもっとも適した形態を選択することが大切です。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
種類 | 株式会社 | 持分会社 | 持分会社 | 持分会社 |
出資者 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 規定なし | 規定なし |
設立費用 | 約20万円〜 | 約6万円〜 | 約6万円〜 | 約6万円〜 |
特徴 | 資金調達力・信用度が高い。上場を目指せる。 | 設立費用が安く、経営の自由度が高い。 | 無限責任社員と有限責任社員で構成。 | 全員が無限責任社員。 |
資本金
事業計画に基づいて、事業の運転資金となる資本金の額を算出します。設立当初に必要な経費・人件費・設備投資などを踏まえて、少なくとも3ヶ月から半年程度の運転資金を準備しておくのが一般的です。自己資金と、融資などの外部資金の割合も計画しておきましょう。2006年の会社法改正により資本金1円での設立も可能になりましたが、資本金の額は会社の体力や信用度を示す指標の一つでもあるため、慎重な設定が求められます。
商号(会社名)
会社の「顔」となる商号(会社名)を決めます。他社と混同されないよう、独自性のある名称を検討しましょう。商号はブランドイメージに直結するため、事業内容が伝わりやすく、覚えやすい・読みやすいことが大切です。商号に使える文字(ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字など)や記号にはルールがあります。また、同一の本店所在地で同一の商号は登記できないため、法務局のオンラインシステムなどで事前に商号調査を行うことをお勧めします。
事業目的
定款に記載する事業目的を決定します。現在行う事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も記載しておくことで、将来事業を拡大する際の定款変更手続き(費用と手間がかかる)を省略できます。「適法性」「明確性」「営利性」の3つの要件を満たすように、具体的かつ包括的に設定しましょう。
本店所在地
会社の登記上の住所となる「本店所在地」を定めます。自宅や賃貸オフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペースなども登記可能ですが、契約内容によっては法人登記が認められない場合もあるため事前に確認が必要です。なお、「本店」は法律用語であり、一般的に企業の本拠地を指すビジネス用語の「本社」とは異なります。
設立日
設立日(会社成立の日)は、法務局に会社設立登記を申請した日となります。そのため、法務局が開庁している平日を設立日として設定する必要があります。記念日などに合わせたい場合は、その日に申請を行いましょう。
会計年度(事業年度)
会社の決算月を定め、会計年度を設定します。法人の会計年度は自由に決められます。事業の繁忙期や、消費税の免税期間を最大限活用できる時期などを考慮して、戦略的に決算月を設定するとよいでしょう。
役員・株主の構成
会社運営に必要な役員(取締役など)や、出資者である株主の構成を決定します。取締役会を設置しない株式会社であれば、取締役1名から設立が可能です。誰が、どのくらいの権限を持つのか、会社の意思決定機関をどのように設計するかは、ガバナンスの観点から非常に重要です。
Step3. 会社用の印鑑(実印)の作成
法務局に登録する「会社実印(代表者印)」を作成します。会社実印は、会社の重要な契約や意思決定の際に用いられ、法的な効力を持つ印鑑です。この他に、銀行手続き用の「銀行印」、請求書や領収書に押印する「角印(社印)」も併せて作成しておくと、その後の業務がスムーズです。ただし、オンライン申請をする場合は印鑑不要で設立登記が可能です。
Step4. 定款の作成
会社の憲法ともいえる「定款」を作成します。定款には、Step2で決めた会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地など)を盛り込み、会社法に則って作成しなければなりません。定款には必ず記載が必要な「絶対的記載事項」、記載がなければ効力が生じない「相対的記載事項」、任意で記載できる「任意的記載事項」があります。非常に重要な文書であるため、法律の専門家から支援を受けて作成すると安心です。
Step5. 定款の認証
作成した定款が法的に正当な手続きで作成されたことを証明してもらうため、公証役場で「定款認証」を受けます。公証人に認証を依頼し、認証を受けた定款には認証印が押されます。この手続きは株式会社の設立時にのみ必要で、合同会社の場合は不要です。
Step6. 資本金の払い込み
定款認証後、発起人(会社設立の企画者)個人の銀行口座に、定められた資本金を払い込みます。この際、誰がいくら払い込んだかを明確にするため、個々の発起人が自身の名義で「振込」によって支払うことがポイントです。払い込みが完了したら、通帳のコピーと「払込証明書」を作成し、登記申請の際に提出します。
Step7. 登記申請書類の作成
法務局へ提出する登記申請書類一式を作成します。一般的に以下の書類が必要となりますが、会社形態や機関設計によって異なる場合があるため、法務局のウェブサイトで確認するか、専門家に相談しましょう。
【法人登記の必要書類の例】
|
Step8. 法務局への設立申請
必要な書類を一通り揃え、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。申請方法は、窓口持参、郵送、オンライン申請があります。法務局の担当者が書類を審査し、不備がなければ1週間~2週間程度で登記が完了し、会社が正式に成立します。登記完了後は、会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」が取得できるようになります。
その他 知的財産等の商標登録
会社設立はビジネスのスタートですが、事業内容によっては「商標」の調査・登録も重要になります。商号(会社名)は登記されても、それだけでは他社が同じ名称を商品やサービスのブランド名として使うことを防げません。自社のブランドを守り、他社の商標権を侵害するリスクを避けるためにも、会社設立と並行して商標登録を検討することをお勧めします。会社設立から商標登録までワンストップで代行するALSP(代替法務サービス事業者)「クラウドリーガル」のようなサービスを利用するのも有効な手段です。
関連記事:商標登録の出願プロセス完全ガイド!侵害対策や失敗を避ける方法は?
知的財産権とは?種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説
会社設立後の手続き
会社設立登記が完了しても、まだ終わりではありません。事業を本格的に開始するために、以下の手続きを速やかに行う必要があります。
税務署・都道府県・市町村への届出
会社を設立したら、所轄の税務署へ「法人設立届出書」を提出します。これにより、法人として税務申告を行う体制が整います。節税メリットの大きい青色申告の適用を受ける場合は、「青色申告承認申請書」も併せて提出しましょう。このほか、役員報酬や従業員給与を支払うために「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要です。
また、税務署だけでなく、事業所を管轄する都道府県税事務所および市町村役場にも、それぞれ法人設立の届出が必要です。
社会保険・労働保険の手続き
年金事務所で「健康保険」や「厚生年金保険」といった社会保険の新規適用手続きを行います。法人は、社長1人であっても社会保険への加入が義務付けられています。
また、従業員を1人でも雇用する場合は、労働基準監督署で「労働保険関係成立届」、ハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」を提出し、労働保険・雇用保険の加入手続きを行いましょう。
法定帳簿・備品の準備
日々の取引を記録するための会計帳簿として、「総勘定元帳」や「仕訳帳」などの主要簿を準備します。会計ソフトを導入すると、効率的に帳簿管理や決算申告が行えます。その他、業務に必要な事務機器や書類整理用のキャビネット、文書管理システムなどを揃え、業務環境を整備しましょう。
法人口座の開設
法人名義の銀行口座(法人口座)を開設します。法人口座の開設は任意ですが、個人のお金と会社のお金を明確に分ける(公私混同の防止)ために必須です。また、法人口座があることで対外的な信用度が高まり、金融機関からの融資や取引先との契約がスムーズに進むというメリットがあります。近年、口座開設の審査は厳格化しているため、登記事項証明書や定款、事業計画書など、必要な書類をしっかり準備して臨みましょう。
会社設立にかかる費用と資本金の調達方法
ここでは、会社設立にかかる費用の目安や、資本金の調達方法について解説します。会社設立時には、設立のための法定費用と、事業を始めるための運転資金の両方が必要です。
会社設立費用の内訳
定款認証手数料・謄本代
株式会社の場合、公証役場での定款認証に約3万円〜の手数料が必要です。
収入印紙代
紙の定款を作成する場合、印紙税法に基づき4万円の収入印紙が必要です。ただし、PDFで作成する電子定款であれば収入印紙代は不要となり、大きな節約になります。
登録免許税
法務局での登記申請時に納める税金です。株式会社の場合、資本金の額×0.7%(最低15万円)、合同会社の場合は資本金の額×0.7%(最低6万円)がかかります。
印鑑作成費用
会社実印・銀行印・角印の3本セットで、1万円~5万円程度が目安です。素材やデザインによって価格は変動します。
専門家への依頼にかかる費用
司法書士や行政書士、ALSP(代替法務サービス事業者)などに設立手続き支援を依頼する場合、5万円~20万円程度の報酬が目安となります。どこまでの業務を依頼するかによって費用は異なります。
資本金
前述の通り、事業を運営していくための元手です。国内では300万円~500万円で設立する企業が多い傾向にありますが、事業内容に応じて適切な額を設定します。
ランニングコスト
設立費用とは別に、事業運営のためのランニングコストも準備が必要です。「オフィスの家賃」「人件費」「水道光熱費」「通信費」「各種保険料」などが含まれます。法人設立時は、少なくとも3ヶ月~半年分のランニングコストを用意しておくのが一般的です。
会社設立費用の節約方法
設立費用を抑えるには、まず電子定款を活用して収入印紙代4万円を節約するのが効果的です。また、シェアオフィスやコワーキングスペースを利用すれば、初期費用や月々の賃料を大幅に削減できます。オフィスの什器は中古品やリースを検討するのも良いでしょう。さらに、国や地方自治体が実施している創業補助金や助成金を積極的に活用することで、初期費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
資本金の調達方法
資本金の調達方法は、「自己資金」と「外部資金」に大別されます。
自己資金: 自身の預貯金や、親族・友人からの出資(贈与税に注意)が一般的です。
外部資金: 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、地方自治体の制度融資、信用保証協会の保証付き融資などが代表的です。その他、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの出資、近年ではクラウドファンディングを活用した資金調達も注目されています。
資金調達に不安がある場合は、専門家による資本政策(ファイナンス)のサポートを受けられるALSP(代替法務サービス事業者)「クラウドリーガル」のようなサービスに相談するのも有効な手段です。
会社設立のメリットとデメリット
起業する際に個人事業主ではなく、あえて会社を設立するのには理由があります。メリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の事業にとって最適な形を検討しましょう。
会社設立のメリット
節税効果が期待できる
個人の所得税は累進課税で所得が高いほど税率が上がりますが、法人税は一定の税率です。利益が一定額を超えると、個人事業主よりも法人のほうが税負担を抑えられる可能性があります。また、役員報酬や退職金を費用(損金)として計上できるなど、経費として認められる範囲が広がります。
社会的な信用力が向上する
法人は法的に登記された組織であるため、個人事業主よりも社会的な信用力が高まります。これにより、大手企業との取引や金融機関からの融資、優秀な人材の採用がしやすくなるなど、事業拡大の機会を得やすくなります。
資金調達の選択肢が広がる
銀行融資は個人事業主よりも法人のほうが審査に通りやすい傾向があります。また、株式会社であれば株式発行による増資など、多様な方法で資金を調達できます。
決算月を自由に決められる
個人事業主の決算月は12月と定められていますが、法人は事業の繁忙期などを考慮して自由に決算月を設定できます。
事業の永続性が高まる
個人事業主の場合、事業主の死亡や引退で事業が終了してしまいますが、法人は経営者が変わっても事業を継続できます。事業承継がスムーズに行える点も大きなメリットです。
会社設立のデメリット
設立に費用と時間がかかる
前述の通り、株式会社で約20万円~、合同会社で約6万円~の法定費用がかかります。また、書類作成や手続きに多くの時間と手間を要します。
設立後の事務・会計負担が大きい
法人設立後は、複雑な法人税の申告や、社会保険の手続き、株主総会の開催(株式会社の場合)など、多くの事務作業が発生します。正確な帳簿管理が求められ、法令遵守も厳しくチェックされます。
会社と経営者個人の資産が区別される
会社の資産は経営者個人のものではありません。会社の資金を経営者が私的に流用すると、法的に問題となる可能性があります。
社会保険への加入義務が生じる
法人は従業員の人数にかかわらず、経営者自身も厚生年金保険・健康保険への加入が義務付けられています。これにより、個人事業主時代よりも保険料の負担が増える場合があります。
赤字でも法人住民税の均等割がかかる
法人は、たとえ事業が赤字であっても、資本金や従業員数に応じて算出される「法人住民税の均等割」(最低でも年間約7万円)を納める義務があります。
会社設立に関するよくある質問
最後に、会社の設立に関するよくある質問とその回答をご紹介します。今後の会社設立へ向けて疑問点を解消しておきましょう。
Q. 株式会社と合同会社はどう違う?
A. 株式会社と合同会社は、どちらも有限責任(出資額の範囲で責任を負う)の法人ですが、主に「所有と経営」の考え方と「設立・運営コスト」が異なります。
株式会社: 出資者(株主)と経営者(取締役)が分離できるのが特徴です(一致も可能)。株式を公開して広く資金を集めることができ、社会的信用度が高い反面、設立・運営コストが高く、株主総会の開催など厳格な運営が求められます。
合同会社: 出資者(社員)=経営者であり、迅速で柔軟な意思決定が可能です。設立費用が安く、運営の自由度も高いため、小規模なビジネスやスピーディーな事業展開を目指すベンチャー企業に適しています。
Q. 有限会社は設立できる?
A. 2006年に施行された新会社法により、有限会社法が廃止されたため、現在、有限会社を新規に設立することはできません。 法改正以前に設立された有限会社は「特例有限会社」として存続していますが、これは株式会社の一種とみなされています。
Q. 貸借対照表と損益計算書の違いは?
A. どちらも会社の経営状態を示す重要な財務諸表ですが、示す内容が異なります。
貸借対照表(B/S): 「ある一時点」における会社の財政状態(資産、負債、純資産のバランス)を示す書類です。会社の「健康診断書」に例えられます。
損益計算書(P/L): 「一定期間」における会社の経営成績(どれだけ売上があり、費用を使い、利益が出たか)を示す書類です。会社の「成績表」に例えられます。
Q. スタートアップ向けの助成金を利用する流れは?
A. まずは、中小企業基盤整備機構のポータルサイト「J-Net21」や、各自治体のウェブサイトなどで、自社の業種や地域、事業内容に合った助成金・補助金をリサーチします。公募要領をよく読み、対象となる条件を満たしているか確認しましょう。申請には、事業の目的や具体的な実施内容、予算などを明確に記載した事業計画書の提出が不可欠です。審査を経て採択されると、助成金が交付されます。申請手続きが複雑な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
Q. 個人事業主から法人化する際の注意点は?
A. 個人事業主から法人化(法人成り)すると、税制上のメリットや信用の向上が期待できますが、いくつかの注意点があります。まず、社会保険への加入が義務となり、保険料負担が増える可能性があります。また、個人事業の資産(在庫、設備、売掛金など)を法人に引き継ぐ際の手続きや、税務上の処理を適切に行う必要があります。どのタイミングで法人化するのが最適か(売上や利益の目安)は、税理士などの専門家に相談し、慎重にシミュレーションすることが重要です。
Q. 起業・会社設立後に顧問弁護士は必要か?
A. 企業規模や法人形態を問わず、事業を行う上で契約行為は必ず発生します。取引先との契約書チェック、労務問題の予防、コンプライアンス体制の整備など、ビジネスには法的なリスクが常に伴います。特に法務部を設置できない中小企業やスタートアップにとって、問題が起きてから弁護士を探すのでは手遅れになるケースも少なくありません。日常的に相談でき、事業内容を理解してくれている顧問弁護士の存在は、トラブルを未然に防ぎ、事業を安心して拡大していくための強力な「守り」となります。
関連記事:個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業に顧問弁護士は必要?導入のメリットや顧問料の費用相場
関連記事:企業法務とは?押さえるべき法律と法的リスクの対策、よくある質問は?
まとめ
ここまで、会社設立の手続きの流れ、費用の内訳、設立のメリット・デメリットなどを網羅的に解説しました。会社を設立するまでには多くのステップがあり、さらに設立登記後にもやるべき手続きが数多く存在します。ご自身で全て対応しようとすると多大な時間がかかるだけでなく、会社法に則った複雑な手続きに不安を感じることもあるでしょう。
そんなときは、企業法務のアウトソース・サービスALSP(代替法務サービス事業者)である**「クラウドリーガル」**の法務サポートを利用するのがおすすめです。「クラウドリーガル」では、専門家である弁護士・司法書士が会社設立を代行支援するサービスをご提供しています。オンラインで書類作成から申請まで幅広い業務を依頼できるため、本業に集中しながらスムーズに会社を設立できます。
さらに、「クラウドリーガル」は設立後の法務体制構築までサポートします。個人事業主からの法人化手続きを支援し、そのまま「社内法務」や「顧問弁護士」として伴走支援が可能です。子会社設立、登記変更、社内規程整備など、企業の成長ステージで発生するあらゆる法務課題に対応し、貴社の事業を法務面から力強くバックアップします。
【クラウドリーガルによる企業法務の支援の例】
- 弁護士・司法書士・専門士業への法律や労務相談(Webチャット・リモート面談・電話)
- 弁護士監修の契約書ひな形
- 契約書自動作成機能
- 契約書レビュー(リーガルチェック)
- 独自カスタム契約書ドラフト作成
- 社内規程整備・作成
- 知的財産等の商標登録代行・調査
- 法令調査(リーガルリサーチ)
- 広告審査
- 薬機法チェック
- 株主総会や取締役会の運営支援、株主対策
- 内部通報窓口(法令違反、ハラスメント等)
- 会社設立(新規設立や子会社等)、登記変更等の代行支援
- IPO準備
- 資本政策(ファイナンス)支援
- 法務デューデリジェンス(DD)
- 契約交渉支援、など
また、近年は会社運営に係わる取締役会議事録や株主総会議事録の電子化が進んでいます。議事録を電子化する場合は、従来の紙への署名・押印に代わり、電子署名を用いることが可能です。その際は、電子署名やタイムスタンプの機能を搭載した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」がおすすめです。「WAN-Sign」の導入により、セキュリティを確保しながら取締役会議事録や株主総会議事録の電子化を進められます。経営書類以外にも一般的な機密保持契約書(NDA)や業務委託契約書・売買契約書・受発注書類などから人事労務系の雇用契約書・誓約書なども電子契約することが出来るため、事業が拡大する前に「WAN-Sign」のような法務DX基盤を導入しておくことで業務負担なくスムーズに事業拡大も可能になるでしょう、どうぞお気軽にお問い合わせください。
関連記事:取締役会とは?役割とメリット、開催の流れ、効果的な運営方法を解説
企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」(バーチャル法律事務所)と、NXワンビシアーカイブズが提供する電子契約サービス「WAN-Sign」や各種BPOサービス(AI契約管理、機密文書保管、電子化、電子帳簿保存など)を組み合わせることで、会社設立から日々の契約業務、文書管理まで、法務・総務領域のDXを最大化します。
AI×弁護士がつくる、日本初の企業法務アウトソース・サービ(ALSP)「クラウドリーガル」
会社設立やその後の法務体制構築でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。









