業務委託契約書に収入印紙は必要?ケース別の印紙代と金額を抑えるポイント
目次[非表示]
- 1.業務委託契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケース
- 1.1.収入印紙が必要なケース
- 1.2.収入印紙が不要なケース
- 2.業務委託契約書に貼る収入印紙の金額一覧表
- 3.業務委託契約書の収入印紙の金額を抑えるポイント
- 3.1.2号文書に該当する場合は契約金額を税抜きで記載する
- 3.2.原本の枚数を減らす
- 3.3.電子契約で締結する
- 4.業務委託契約書の収入印紙の貼り方・消印の押し方
- 4.1.業務委託契約書の収入印紙の貼り方
- 4.2.業務委託契約書の消印の押し方
- 5.業務委託契約書の収入印紙について知っておくべきポイント
- 5.1.印紙税の負担割合について当事者間で相談しておく
- 5.2.収入印紙を貼り忘れるとペナルティが課せられることがある
- 5.3.電子契約の場合は契約書・覚書ともに収入印紙が不要
- 5.4.写し・副本・謄本は課税文書に当たらないので収入印紙は不要
- 6.まとめ
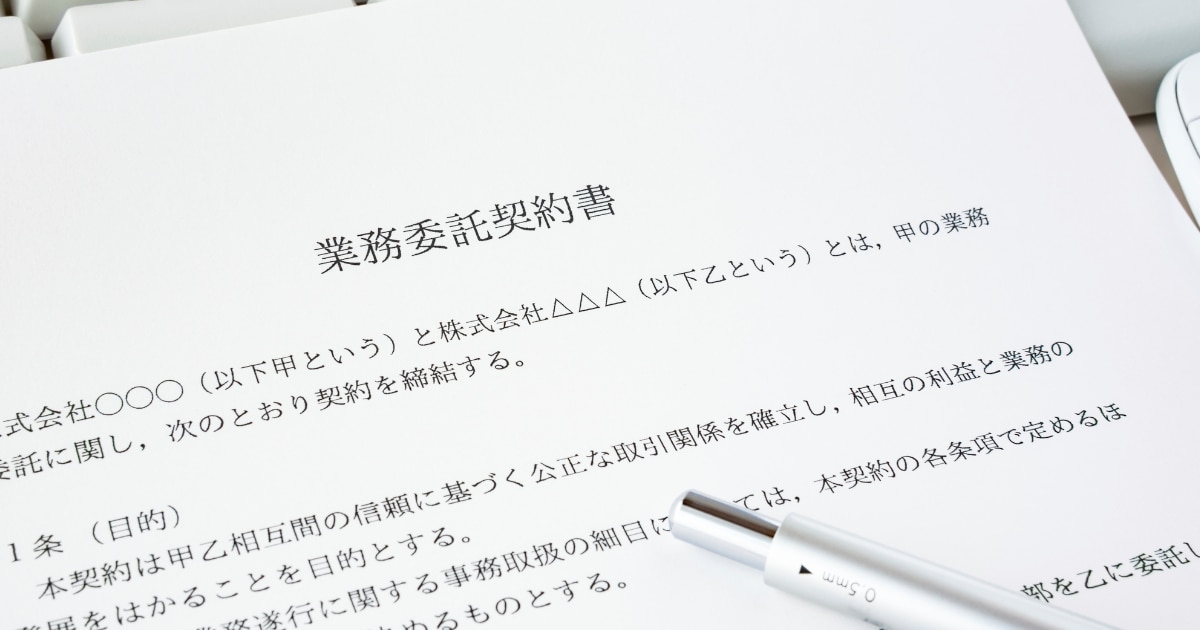
自社の業務を外注する場面では「業務委託契約書」を作成し契約を締結します。その際、契約内容によっては契約書が課税文書に該当し、収入印紙の貼付が必要となることがあります。収入印紙の必要性を適切に判断して、正確に契約手続きを進めましょう。
この記事では、業務委託契約書における収入印紙の取り扱いについて解説します。印紙代の金額を抑えるポイントや、収入印紙の貼り方・消印の押し方もお伝えするため、ぜひ契約業務で参考にしてみてください。
業務委託契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケース
業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、場合によって異なります。初めに、業務委託契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケースをそれぞれご紹介します。
収入印紙が必要なケース
請負に関する契約書(2号文書)
請負契約書とは、仕事の完成や成果物に対して報酬を支払う契約書です。「請負に関する契約書(2号文書)」は課税文書であるため、収入印紙が必要となります。具体的には、「工事請負契約書」「広告契約書」「会計監査契約書」などが該当します。
【参考】「No.7102 請負に関する契約書」(国税庁)
継続的取引の基本となる契約書(7号文書)
「継続的取引の基本となる契約書(7号文書)」は課税文書であるため、収入印紙が必要です。特定の取引先との継続的な取引を契約する場合に用いられます。具体的には、「売買取引基本契約書」「下請基本契約書」「代理店契約書」などが該当します。
【参考】「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」(国税庁)
収入印紙が不要なケース
外部へ業務を委託する際、以下のケースでは契約書の収入印紙の貼付は不要です。
- 委任契約や準委任契約を締結するケース
- 「請負に関する契約書(2号文書)」の契約金額が1万円未満のケース
- 電子契約で締結するケース
基本的に、委任契約書・準委任契約書は課税文書に該当しないケースが一般的です。場合によっては、収入印紙が必要なケースもあるため、個別の状況に応じて判断しましょう。また、課税文書である2号文書の中でも、契約金額が1万円未満なら非課税となります。電子契約書の場合は課税文書に該当しないとされるため、収入印紙は不要です。
業務委託契約書に貼る収入印紙の金額一覧表
ここでは、業務委託契約書に貼る収入印紙の金額をご紹介します。2号文書と7号文書のそれぞれの金額を確認してみましょう。
請負に関する契約書(2号文書)の場合
「請負に関する契約書(2号文書)」の印紙代(印紙税額)は、書面に記載された契約金額に応じて変わります。また、契約金額が1万円未満の契約書は非課税となります。金額ごとの印紙代は以下の通りです。
記載された契約金額 | 税額 |
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
【出典】国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の場合
「継続的取引の基本となる契約書(7号文書)」の印紙代は、1通につき4,000円となっています。なお、契約期間が3カ月以内で、かつ更新の定めのない契約書は、7号文書に該当しません。
業務委託契約書の収入印紙の金額を抑えるポイント
業務委託契約書に貼付する収入印紙の金額は、以下の方法で抑えられる可能性があります。契約業務のコスト削減へ向けて、ぜひ参考にしてみてください。
2号文書に該当する場合は契約金額を税抜きで記載する
「請負に関する契約書(2号文書)」に税抜き・税込みの価格をそれぞれ記載し、消費税額が明確に分かる状態となっている場合は、消費税分を含めない金額で印紙税を納付できます。場合によっては、印紙代を抑えられる可能性があるでしょう。
【参考】「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」(国税庁)
原本の枚数を減らす
収入印紙は、当事者が署名押印を行った契約書の原本に貼付する必要がありますが、写し・副本・謄本への貼付は不要です。そのため、原本を1部のみ作成し、その他はコピーで対応することで、印紙代を抑えられます。ただし、原本を紛失するリスクには十分に注意しましょう。
電子契約で締結する
電子契約書は紙の契約書と異なり、課税文書には該当しないとされています。そのため、電子契約で締結した業務委託契約書には、収入印紙を貼付する必要がありません。契約業務を電子化し、印紙代を抑える方法も有効です。
業務委託契約書の収入印紙の貼り方・消印の押し方
収入印紙の貼付が必要な業務委託契約書は、以下の通り対応しましょう。ここでは、収入印紙の貼り方・消印の押し方を解説します。
業務委託契約書の収入印紙の貼り方
収入印紙を貼る位置に法的な決まりはないものの、一般的には書類の左上のスペースに貼付することが多いです。あるいは、署名欄の横に貼付するケースもあります。収入印紙の裏面に糊をつけて、はがれないようにしっかりと貼り付けましょう。
業務委託契約書の消印の押し方
書類に収入印紙を貼付した後は、必ず「消印」を行う必要があります。その際は、書類と収入印紙の両方にまたがるようにして、印鑑をはっきりと押しましょう。あるいは、本人・代理人が書類と収入印紙の両方にまたがるように署名を行う方法でも対応可能です。
業務委託契約書の収入印紙について知っておくべきポイント
最後に、業務委託契約書における収入印紙の取り扱いについて、知っておくべきポイントをご紹介します。契約業務のご担当者様は、改めてチェックしておきましょう。
印紙税の負担割合について当事者間で相談しておく
契約書の印紙税は、当事者が折半して負担するケースが一般的です。あらかじめ負担割合について相手先と相談しておきましょう。なお、「印紙税法」の第3条においては、課税文書の作成者に印紙税を納める義務があることや、課税文書が共同作成の場合は連帯して印紙税を納める義務があることが記載されています。
(納税義務者)第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
【引用】「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」(e-Gov 法令検索)
収入印紙を貼り忘れるとペナルティが課せられることがある
課税文書に収入印紙を貼付しない場合は、本来納めるべき印紙税を納付していない状態となります。場合によっては過怠税(税務上の義務違反に対して課される税金)を徴収されるなど、ペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。
電子契約の場合は契約書・覚書ともに収入印紙が不要
業務委託契約を電子契約で締結する場合、収入印紙は不要です。また、契約書の内容を一部変更するための覚書を作成する場合も、電子契約であれば覚書の収入印紙が不要となります。電子化することで印紙代の負担がなくなり、契約業務のコスト削減が期待できます。
写し・副本・謄本は課税文書に当たらないので収入印紙は不要
基本的に、契約書の写し・副本・謄本は課税文書には当たらないため、収入印紙は不要です。ただし、対象の書類に当事者が署名押印を行った場合は、契約の成立を証明する課税文書と見なされる可能性があるため注意しておきましょう。
まとめ
ここまで、業務委託契約書における収入印紙の取り扱いについて解説しました。電子契約を導入すれば、業務委託契約書をはじめとした契約を締結する際の印紙代を抑えることが可能です。
低コストで高機能かつ最高水準のセキュリティを標準搭載した電子契約を実現するなら、NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」をおすすめします。初期費用0円から始めやすく、コストパフォーマンスの高さが魅力です。契約業務のご担当者様は、資料ダウンロードやお問い合わせをご検討ください。









