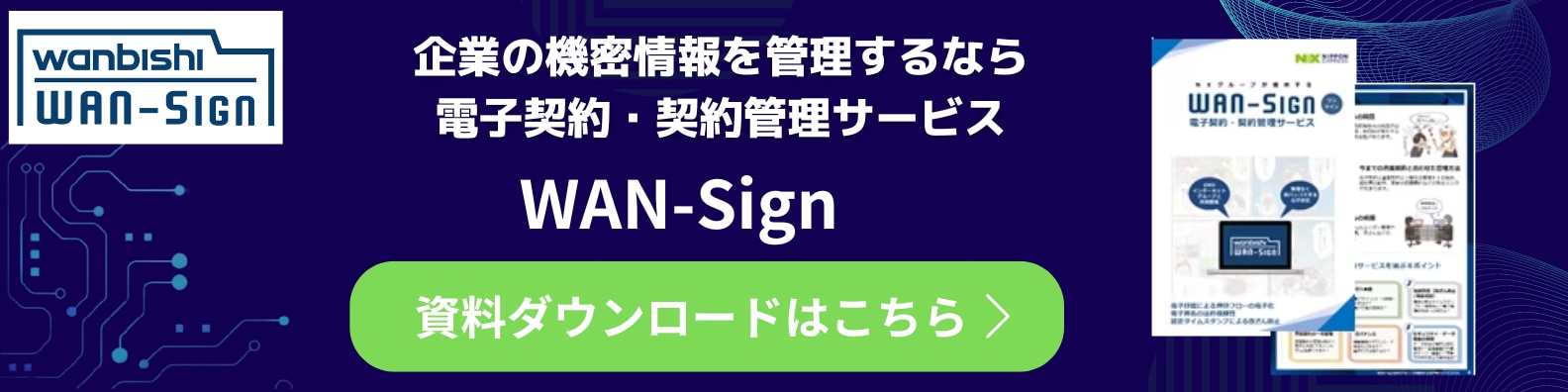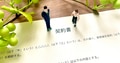個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業に顧問弁護士は必要?導入のメリットや顧問料の費用相場
目次[非表示]
- 1.顧問弁護士とは何か
- 1.1.顧問弁護士の基本的な定義
- 1.2.顧問弁護士と一般弁護士の違い
- 1.3.顧問弁護士の役割
- 1.4.顧問弁護士の必要性
- 1.5.社内法務部門がある場合の顧問弁護士との連携
- 1.5.1.社内法務部門の役割
- 1.5.2.顧問弁護士との共同作業の事例
- 1.5.3.効果的な連携方法
- 2.顧問弁護士の主な業務
- 3.顧問弁護士を導入するメリット
- 3.1.顧問弁護士のメリット①:顧問弁護士・法律顧問等の存在の公言
- 3.2.顧問弁護士のメリット②:法的リスクの軽減
- 3.3.顧問弁護士のメリット③:経営判断の支援
- 3.4.顧問弁護士のメリット④:企業ガバナンス・社内コンプライアンスの強化
- 4.顧問弁護士を導入するデメリット
- 5.顧問弁護士の費用相場
- 6.顧問弁護士の選び方のポイント
- 7.個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業における顧問弁護士活用の具体例
- 7.1.トラブル未然防止
- 7.2.効率的な法務体制の構築
- 7.3.コスト削減
- 8.顧問弁護士契約の見直し時期
- 9.顧問弁護士に関するよくある質問と回答
- 10.まとめ

会社経営では法律に関わるさまざまな問題が発生する可能性があります。万が一のトラブル発生時に備えて、弁護士との顧問契約を検討していたり、リスク対策として既に顧問契約を締結している個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業も少なくありません。一方で個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の場合は事業の規模に適した法務サービスを利用する方法もあります。
この記事では、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の法務担当者の方へ向けて、顧問弁護士の必要性、導入のメリット、顧問料の費用相場などを解説します。また、従来型の顧問弁護士や顧問法律事務所よりも費用を抑えながら、顧問弁護士や社内法務として利用できる企業法務アウトソース・サービスALSP(代替法務サービス事業者)もご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。ALSP(Alternative Legal Service Provider)は米国・欧州を中心にグローバルで拡大しており、国内の個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の顧問弁護士の課題にも素早く対応できる新たな選択肢・方法となります。
顧問弁護士とは何か
顧問弁護士は、法人や個人が法的な問題に対処するために契約する専門家です。始めに、顧問弁護士の基本的な定義や役割などの基礎知識を解説します。
顧問弁護士の基本的な定義
顧問弁護士とは、法人や個人が法的問題に対処するために契約を結ぶ弁護士のことです。法的な助言や指導によって依頼主の法的なトラブルを予防し、円滑な業務運営のサポートを行います。具体的には契約書の作成や法令遵守のためのアドバイスを行い、依頼主と密接に連携しながら問題解決を図る重要な役割を担っています。顧問弁護士は企業の日常的な法律業務全般に関与し、契約は長期的に締結されるのが一般的です。
顧問弁護士と一般弁護士の違い
顧問弁護士と一般弁護士は、依頼主との関係性や業務内容に違いがあります。顧問弁護士は法人や個人と長期間にわたって契約を結び、継続的な法律相談や助言を行います。それに対して、一般弁護士は特定の事案ごとにスポットで依頼を受けることが多いです。そのため、顧問弁護士は依頼主のビジネス全体を理解し、予防策を講じる役割を果たします。一方、一般弁護士は問題が発生したときに解決する役割を担います。
顧問弁護士の役割
顧問弁護士には、法律の専門家としてクライアント(顧問先企業)の相談を受け付けたり、法的なトラブルを未然に防いだり、発生したトラブルを解決へ導いたりする役割があります。顧問弁護士の専門分野は多岐にわたり、企業法務、労務問題、知的財産などのさまざまな分野に精通しています。また、企業の要望に応じて契約書の作成やレビュー・リーガルチェック、労働契約のチェック、新規ビジネス立上げ時の法令調査やリスク精査、商標等知的財産の登録・調査、会社登記・登記変更の手続き、株主対策や株主総会・取締役会の運営支援、社内規程整備など幅広い業務を担います。また、法的なトラブルが発生した場合には迅速に対応して解決策を提示します。このほかに、多様性による人権やプライバシー、公益通報制度・内部通報制度による法令違反やハラスメント等など労務問題への対応も増えてきており、定期的にコンプライアンス研修やセミナーを開催して、企業の法令遵守を支援する役割もあります。
顧問弁護士の必要性
個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の経営には法的なリスクの不安がつきものです。昨今は企業内で発生するハラスメントやコンプライアンス関連の事件が後を絶ちません。しかし、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業は大企業とは異なり、社内に法務専任担当者や法務部門が設置されていないケースや、企業内弁護士(インハウスローヤー)を確保していないケースが多いのが実情です。こうした状況で法的なトラブルが発生した場合、問題解決が困難になると予想されるでしょう。顧問弁護士は、そんな個人事業主(スタートアップ)・中小企業の法的リスク対策の観点から必要とされています。
社内法務部門がある場合の顧問弁護士との連携
社内法務部門の役割
社内法務部門は、企業内で発生する法的な問題を解決するために設置されます。主な役割は法的リスクの評価と予防です。各部門と連携しながら、契約書のレビュー・リーガルチェックや法的文書の作成、コンプライアンスの管理を行います。また、トラブルが発生した場合には速やかに対応策を講じます。このほかに、法改正や新たな規制に対応するための情報収集や社員教育を行い、企業全体の法的な理解の底上げに貢献します。
顧問弁護士との共同作業の事例
顧問弁護士と社内法務部門が共同作業するケースがあります。例えば、契約書の内容を精査し、両者で法的リスクが存在しないことを確認します。訴訟リスクが高い案件では、顧問弁護士が専門的なアドバイスを提供し、社内法務部門が対策を講じます。また、自社にコンプライアンス違反の疑いがある場合は共同で調査を進め、解決策を見出します。顧問弁護士と社内法務部門の協力によって、企業は法的リスクの効果的な回避が可能です。
効果的な連携方法
顧問弁護士と社内法務部門の効果的な連携を実現するためには、ミーティングでのこまめな情報共有が欠かせません。また、定期的に勉強会やセミナーを開催し、顧問弁護士が最新の法改正情報や法的知識を共有することも重要です。このように社内法務部門と顧問弁護士が信頼関係を構築すると、迅速かつ正確な対応が可能となり企業の法的リスク軽減が期待できます。
顧問弁護士の主な業務
ここでは、顧問弁護士の主な業務内容を解説します。顧問契約を締結するとどのようなサポート内容を利用できるのか、具体的に確認してみましょう。
顧問弁護士の主な業務①:契約書の作成とレビュー・リーガルチェック
契約書の作成とレビュー・リーガルチェックは、顧問弁護士の主要な業務の一つです。まず、契約書の作成では、企業の利益を最大限に守るために、詳細で明確な条項を定める必要があります。しかし、複雑な法律用語や条項が多いため、専門知識が必要です。また、レビュー・リーガルチェックの作業では、既存の契約書に潜む法的リスクを発見し、修正することが求められます。このようにして、企業の法的リスクを減らし、安心して事業を進められるのです。
契約書の適切な管理は、企業にとって非常に重要です。契約書が不十分なものであると、後々のトラブルや損害賠償請求などの法的問題が発生する可能性が高くなります。そのため、顧問弁護士が関与することにより、法的なリスクを軽減し、企業活動を円滑に進めることが可能となります。信頼できる契約書は企業の信頼性を高め、取引相手との関係をより強固にするでしょう。
顧問弁護士の主な業務②:労務問題の対応
労務問題の対応も顧問弁護士の重要な役割です。まず、労働契約書の作成や就業規則の策定、改訂などを行います。これにより、企業と従業員の間のトラブルを未然に防止できます。また、人権・プライバシーなど従業員からのクレームや労働争議が発生した場合に、迅速に適切な対応を取ることで、企業の運営に支障をきたさないようにします。また、公益通報制度・内部通報制度に適した整備をすることで事態に迅速に対応することもできます。顧問弁護士は、労働法に精通しているため、専門的なアドバイスを提供することが可能です。
さらに、労務問題の予防策として、定期的な職場環境のチェックや、従業員とのコミュニケーションを促進するための仕組み作りも助けます。このように、労務問題に対する予防措置を講じることで、社員が安心して働ける環境を整えられます。この結果、企業全体の生産性や士気の向上にもつながることでしょう。
労務問題に対応することは、企業の健全な運営に欠かせません。適切な助言を受けることで、企業は法的なトラブルを回避し、従業員との信頼関係を築けます。それが、企業の長期的な成功につながるのです。
顧問弁護士の主な業務③:訴訟対応と紛争解決
訴訟対応と紛争解決は、顧問弁護士の最も責任重大な業務の一つです。まず、訴訟の準備段階では、必要な証拠の収集や書類の作成、法廷での戦略の立案を行います。これによって、クライアントの利益を最大限に守るための準備が整います。さらに、裁判が始まった場合には、法廷での弁論や、各種法的手続きを遂行します。
次に、紛争解決では、調停や仲裁といった方法を用いることが一般的です。これにより、裁判に至らずに解決できます。調停や仲裁は、時間やコストを節約し、双方にとって負担の少ない方法となります。顧問弁護士は、クライアントの利益を第一に考え、最適な解決方法を探求するのです。
訴訟対応や紛争解決における顧問弁護士の役割は極めて重要です。迅速で的確な対応が求められるため、専門知識と経験が必要となります。法的な争いを避けつつ、企業の利益を守るためには、信頼できる顧問弁護士の存在が欠かせません。企業の健全な運営と成長において、法的な問題を未然に防ぐことが大切だからです。
顧問弁護士を導入するメリット
顧問弁護士に依頼すると、企業経営で発生するさまざまな法務事務がスムーズになります。ここでは、顧問弁護士を導入するメリットをご説明します。
顧問弁護士のメリット①:顧問弁護士・法律顧問等の存在の公言
弁護士と顧問契約を締結している企業は、自社のWebサイトや会社概要などで顧問弁護士や法律顧問について表記することが可能です。このように顧問弁護士や法律顧問の存在を公言することで、ステークホルダーに対して「コンプライアンスや法務対応に力を入れている企業である」と印象づけられるのがメリットです。
顧問弁護士のメリット②:法的リスクの軽減
顧問弁護士は、「契約書のチェック」「法規制の確認」などの予防策を講じて、法的な問題が発生する前に企業活動の法的リスクを軽減する役割を果たします。万が一、法的トラブルが発生してしまった場合も、法律の専門家が支援するため早期に適切な対策を採ることが可能です。企業側は顧問弁護士の助言により法的なリスクを最小限に抑えられ、安心して通常業務に集中できるようになります。取引先や顧客からの信頼を獲得でき、企業の信頼性が向上します。
顧問弁護士のメリット③:経営判断の支援
顧問弁護士は、経営判断を下すプロセスにおいて重要なパートナーとなります。法律の専門知識を活用して経営者や役員の相談相手を務め、正確かつ迅速に判断を下せるよう手厚くサポートします。具体的には、新規ビジネスの立ち上げ、資金調達、合併と買収(M&A)といった重要な経営判断において法的な観点からアドバイスを提供します。経営者が法的リスクを正しく認識し、適切な対応を取ることで、企業の持続的な成長を促進できるでしょう。
顧問弁護士のメリット④:企業ガバナンス・社内コンプライアンスの強化
企業がガバナンスや法令遵守(コンプライアンス)を徹底するためには、内部統制と社員教育が不可欠です。顧問弁護士はこれらの社内コンプライアンス強化の役割を担い、社内に法令遵守を根付かせます。具体的には、研修やセミナーを通じて社員に法的知識を共有し、定期的な監査で法令違反がないかをチェックします。社員一人ひとりの法令遵守の意識を高め、違反行為を未然に防げます。
顧問弁護士を導入するデメリット
弁護士と顧問契約を結ぶ場合、以下のデメリットに注意しておきましょう。自社の予算や目的に合わせて顧問弁護士を導入することが大切です。
顧問弁護士のデメリット①:顧問弁護士の費用(顧問料)がかかる
弁護士と顧問契約を締結すると、以降は月額費用が発生してランニングコストの負担が生じます。法的なトラブルの有無にかかわらず、原則として毎月一定の費用がかかる点に注意しておきましょう。ただし、顧問料は法人の経費として扱うことが可能です。
顧問弁護士のデメリット②:顧問弁護士が対応できない案件もある
非常に専門性の高い分野の知識が求められる場面では、顧問弁護士が対応できない可能性があります。万が一、顧問弁護士で対応が不可能となってしまったら、改めて対応可能な弁護士を探して、一から相談・依頼をしなければなりません。こうした事態に備えて、自社の事業と関連する相談内容に幅広く対応できる弁護士と顧問契約を結ぶことが大切です。
顧問弁護士の費用相場
顧問弁護士の費用(顧問料)は、一般的に月額制が採用されています。顧問料の一般的な相場は3万円~7万円が目安です。なお、日本弁護士連合会が2009年に実施したアンケート調査のデータによると、中小企業と顧問契約を締結する場合の月額顧問料に関して、多くの弁護士が「3万円」から「5万円」と回答しています。一方、近年は弁護士業務の専門分化が進んだ背景から、企業法務を中心的に取り扱う専門性の高い弁護士ほど顧問料が高額になる傾向が見られます。
【出典】日本弁護士連合会「アンケート結果にもとづく中小企業のための弁護士報酬の目安」
URL:https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/smeguide.pdf
顧問弁護士の選び方のポイント
弁護士による顧問サービスを利用する場合、どのような観点で顧問弁護士を選べば良いのでしょうか。ここでは、顧問弁護士の選び方のポイントについてお伝えします。
企業のニーズに合った専門性を持つ弁護士を選ぶ
企業の法的リスクを最小限に抑えてビジネスを成長させるためにも、自社のニーズに合った専門領域の顧問弁護士を選ぶことが重要です。例えば、IT業なら知的財産に強い弁護士、小売業なら契約法に詳しい弁護士が適しているでしょう。業種や事業内容に合った専門領域を持つ弁護士に依頼することで、効果的なリーガルサポートを受けられます。専門事業を広範囲で展開している企業だと対応分野に応じて複数人の顧問弁護士との顧問契約も必要になってきます。
企業が信頼関係を築ける弁護士を選ぶ
信頼できる弁護士には内部情報を安心して共有できるため、社内の事情に即したアドバイスを受けられます。また、緊急時に迅速に対応してもらえるという安心感もあります。日常的に弁護士との信頼関係を構築していると、トラブルが発生した際の対応もスムーズに連携して進めやすくなるでしょう。顧問弁護士とは人と人の関係になるため相談のし易さ作りなどコミュニケーションを前提とした選定が必要となります。知識・専門性があっても気軽に相談できない環境では意味がありません。
企業の予算に応じたプランを選ぶ
顧問弁護士や顧問法律事務所にかかる料金は一般的に高額となるため、予算に応じたプランを選ぶことが大切です。料金プランには、月額制の料金プランや時間単位の料金プランなどの種類があります。コストと導入効果のバランスを見極めて、自社に最適なプランや体制を選びましょう。
なお、近年は顧問弁護士や顧問法律事務所に依頼する以外にも、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業が利用しやすい士業相談のサービスが登場しています。例えば、「企業法務アウトソーシングサービスALSP(代替法務サービス事業者)」「弁護士相談サービス」「バーチャル法律事務所」などです。これらのサービスを活用すれば、顧問契約と比較して費用を抑えながら、専門家からオンラインで必要な法務のサポートを受けられる体制を整備できます。法律事務所(弁護士法人)や弁護士と直接契約する以外の方法もあるため、自社の予算に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。
関連記事:ALSP(代替法務サービスプロバイダー)とは?従来の法務サービスとの違いやメリット・デメリット
個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業における顧問弁護士活用の具体例
顧問弁護士は、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業においても法律問題の解決から予防法務まで幅広い業務を担っています。ここでは、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業における顧問弁護士の活用方法をご紹介します。
トラブル未然防止
個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の契約書作成や契約書レビュー・リーガルチェックを顧問弁護士に依頼することで、契約に関するトラブルを未然に防げます。また、顧問弁護士は従業員との労務トラブルの防止にも貢献し、企業の安定運営に役立てられます。トラブルが起きる前に対策を採ることで、企業の信頼性を高められます。
効率的な法務体制の構築
個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業は顧問弁護士のアドバイスを受けながら法務体制を構築できます。例えば、顧問弁護士が法律に関わる重要な文書のテンプレートを準備したり、従業員にコンプライアンス研修を実施したり、法務チェックを行ったりできます。企業運営がスムーズになり、法的リスクを低減させて問題の発生を防止できます。
コスト削減
個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業は弁護士と顧問契約を結ぶことで、法的なトラブルが発生した際に迅速に対応でき、訴訟費用や専門家への報酬金の発生を抑えられます。顧問契約には一定の費用がかかるものの、顧問弁護士との連携によって企業活動を法的リスクの少ない環境で行えるため、結果的にはコストの削減につながるのです。
顧問弁護士契約の見直し時期
ここでは、顧問弁護士契約の見直し時期について解説します。担当弁護士による法的サポートの充実度や弁護士費用などを踏まえて、現状の顧問弁護士契約の見直しを検討してみましょう。
顧問弁護士の契約期間と更新のタイミング
顧問弁護士契約の契約期間は、一般的に1年から3年程度に設定されることが多いものの、具体的な期間は個別の契約によります。契約終了前に更新の可否を判断するためには、少なくとも半年以上前から準備を始めることが推奨されます。十分な準備期間を確保して、見直しと検討を行いましょう。また、更新時には法的リスクや業務環境の変化を考慮して、契約内容を見直すことが大切です。
顧問弁護士のパフォーマンス評価のポイント
顧問弁護士のパフォーマンスを評価する際には、まず弁護士が提案する法的アドバイスの質が重要です。企業の法的リスクを低減し、適切な経営判断をサポートする役割を果たしているかをチェックしましょう。また、レスポンスの早さも重要なポイントです。問題が発生した際に迅速に対応できるかを確認してみてください。また、弁護士のサービスに対して費用が妥当であるか見直すことが大切です。これらのポイントを総合的に評価して、顧問弁護士のパフォーマンスを把握しましょう。顧問契約の内容により月内上限設定の問題で相談をセーブしているなど法務運営上の再点検も必要だと思われます。
企業の新たなニーズに対応するための変更
新規事業への参入や立上げ、新しい法制度や規制が導入されると、新たな法的リスクが発生する可能性があるため、契約内容を見直して変更を加えることが求められます。また、企業の業務内容や事業範囲が拡大した場合も、新たなニーズに対応できるよう契約を修正することが重要です。定期的に顧問弁護士とコミュニケーションを取り、具体的な対策を講じる必要があります。これにより、企業は法的なリスクを最小限に抑えながら円滑な業務運営を実現できます。
顧問弁護士に関するよくある質問と回答
最後に、顧問弁護士に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
Q.顧問弁護士の費用はどれくらいかかる?
顧問弁護士の費用は、事務所の規模、地域、契約内容によって異なります。一般的には月額制で料金が設定され、月額料金は平均して数万円から数十万円ほどかかる場合が多いです。
なお、顧問弁護士には「固定料金型」「時間料金型」「成果報酬型」の3つの料金形態があります。固定料金型は毎月一定の額を支払う形式です。時間料金型は、実際にかかった時間に応じた額を支払う方式です。成果報酬型は成功報酬を支払う方式になります。
どの料金形態が最適かは、企業の状況やニーズによって異なります。事前に複数の弁護士事務所に相談して比較検討することが重要です。
Q.顧問弁護士に依頼するべき緊急時とは?
顧問弁護士に依頼するべき緊急時に該当するのは、契約トラブルや労働紛争などです。トラブルの発生時には、企業は速やかに事実関係を整理し、証拠や資料を早急に準備しましょう。
緊急時には、まず冷静に状況を把握することが大切です。法律問題が絡む場合には迅速に顧問弁護士に相談しましょう。なかには24時間相談可能な窓口を設けている弁護士事務所もあります。
Q.顧問弁護士を解任する場合の手続きは困難?
顧問弁護士を解任する際は、まず契約書を確認し、解任の条件や手続きを確認する必要があります。契約期間中でも解任が可能な場合がありますが、一般的には解任の通知期間が設けられているケースが多いです。
弁護士に対して解任の意思を伝えるには、書面またはメールで正式に通知しましょう。また、その際は理由を明確にすることが望ましいといえます。解任後も残務がある場合や未払いの費用が残っている場合は、しっかりと清算することが大切です。並行して、新たな顧問弁護士を選任する準備を進めることをおすすめします。
まとめ
ここまで、顧問弁護士の必要性、導入のメリット、顧問料の費用相場などをご紹介しました。弁護士と顧問契約を締結することで、法律の専門家に法務面の相談やトラブル対応を依頼できるようになります。その一方で、個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)・中小企業の場合は顧問契約による費用負担でお悩みのケースが少なくありません。
そこでおすすめなのが、企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」(バーチャル法律事務所)です。中小企業や個人事業主(スタートアップ/ベンチャー)が利用しやすい料金プランで、月額1万~顧問弁護士や社内法務の役割を果たします。「クラウドリーガル」は、ALSP(代替法務サービス事業者)のため多種多彩な弁護士・専門士業のスケール体制を完備しており、様々な法務・労務課題に迅速に対応ができます。Webシステム(チャット・リモート面談・電話)によるコミュニケーション方法で、「いつでも」「どこからでも」「気軽に」高度な法務サービスを受けることができます。契約書の自動作成、契約書レビュー・リーガルチェックから法務・労務の相談サポート、法令調査(リーガルリサーチ)、社内規程整備、商標等知的財産の登録、広告審査、新規会社設立・登記変更手続き、内部通報窓口、資本政策(ファイナンス)、株主総会・取締役会の支援などを低コストで充実したサービス内容でご提供しています。既存の顧問弁護士との使い分け・併用や連携もできるため、大手企業・上場企業でも利用が可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
AI×弁護士がつくる、日本初の企業法務アウトソース・サービス(ALSP)「クラウドリーガル」
関連記事:リーガルテックとは?市場規模とサービスの種類、導入時のポイント
企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」(バーチャル法律事務所)とNXワンビシアーカイブズの提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」や「AI契約管理」「機密文書保管」「電子化(スキャン代行)」「機密書類抹消」「電子帳簿保存」「契約事務BPOサービス」と組合せることで法務DXの最大化を実現します。