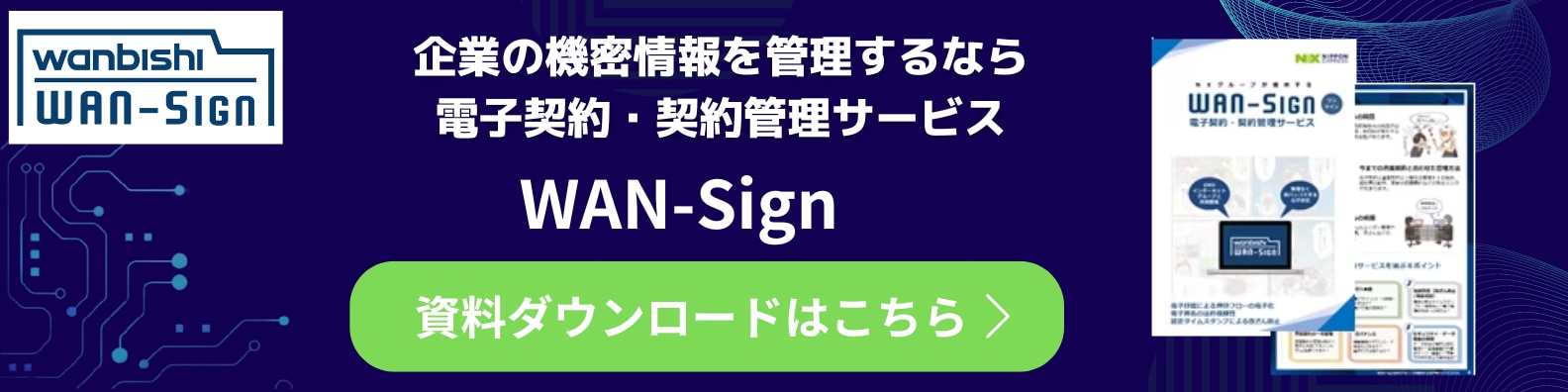電子契約の法的効力とは?電子署名法や電子帳簿保存法で求められる要件
(更新日:2024年11月28日)
目次[非表示]
- 1.電子契約の定義
- 2.電子契約の法的効力
- 3.電子契約における電子署名と電子サイン
- 4.電子署名と電子サインの法的効力の違い
- 4.1.①電子署名の法的効力
- 4.2.②電子サインの法的効力
- 5.電子署名法で求められる要件
- 6.電子帳簿保存法で求められる要件
- 6.1.①電子帳簿での保存要件
- 6.2.②電子取引での保存要件
- 7.e-文書法で求められる要件
- 8.電子契約に関して知っておくべき法律
- 9.電子契約を導入する主なメリット
- 9.1.①業務の効率化
- 9.2.②コストの削減
- 9.3.③契約書の保管スペースの削減
- 9.4.④契約のリードタイムの短縮
- 10.電子契約を導入する際の注意点
- 10.1.①電子化に対応していない契約がある
- 10.2.②取引先との合意が必要になる
- 10.3.③電子契約専用の業務フローの策定が必要になる
- 10.4.④電子帳簿保存法の保存方法に対応する
- 10.5.⑤契約の保存年限、電子署名の有効期限に注意する
- 10.6.⑥セキュリティ対策を徹底する
- 11.電子契約の導入手順
- 11.1.①導入前の準備
- 11.2.②電子契約システムの選定
- 11.3.③社内および取引先との調整
- 11.4.④導入およびマニュアルの準備
- 12.電子契約の法的効力に関するよくあるQ&A
- 12.1.電子契約が法的効力を持つ根拠は?
- 12.2.有効性を持つためのポイントは?
- 12.3.電子契約書は紙の契約書と同等の証拠能力がある?
- 13.「WAN-Sign」で業務効率化

近年のビジネスシーンではオンライン上で取引先と契約締結する「電子契約」が普及しつつあります。こうしたクラウドサービスを利用して契約手続きをする場合、電子契約の証拠力を心配しているご担当者様も多いのではないでしょうか。
電子契約では紙の契約書のような手書きでの署名や押印を行わないものの、各種サービスには法的効力と有効性が担保される機能が搭載されています。この記事では、電子契約の法的効力を解説するとともに、導入メリットや注意点をお伝えします。
電子契約の定義
電子契約とは、電子データで作成された契約書に電子署名を使用して締結される契約のことをいいます。書面契約とは異なり、契約書が電子データとして存在するため、作成から管理まですべてオンライン上で行うことが可能です。
電子契約は紙のように物理的に保管する必要がないため、紛失や自然災害に伴う破損・汚損などのリスクが軽減されます。また、印刷に必要な紙やインクなどのコストがかからずコスト削減に役立ち、また、社内のペーパーレス化の促進に役立ちます。
契約に必要な手続きはすべてオンライン上で電子的に行われるため、契約業務にかかる印刷・製本・郵送などの作業工数を削減することも可能です。
電子契約の法的効力
書面契約とは異なり、電子契約は直接署名や押印ができないため、法的効力が懸念されることもあるでしょう。
しかし、電子契約の法的効力については、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条によって認められています。
電子署名法第3条は以下の通りです。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号および物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
このように、電子的に作成された文書であっても、当事者による電子署名が行われていれば、法的効力と有効性が担保されるという仕組みです。
電子署名は、第三者機関による厳格な本人確認が行われたうえで発行される電子証明書を用いることが一般的なため、本人性と非改ざん性が保証されます。また、電子証明書は高度な暗号化技術によって保護されているため、解析や悪用のリスクが最小限に抑えられているのもポイントです。
関連記事:電子契約とは?メリット、書面契約との比較とともに解説
電子契約における電子署名と電子サイン
電子契約では、従来の押印や手書きの署名にあたる手続きを電子的に行うことで、文書の証拠力が認められるようになります。ここでは、電子契約の法的有効性を担保する技術について解説します。
①電子署名とは?
電子署名とは、公開鍵暗号技術により電子文書の本人性・非改ざん性を担保する技術です。国内では「電子署名法」によって要件が定義されています。紙の書類における押印や署名に該当し、文書の主体を明確にする役割があるほか、文書の偽造防止にもつながります。電子署名には、当事者型と立会人型の2種類が存在します。
当事者型の仕組み
当事者型では、契約締結する双方が電子認証局による本人確認を実施し、それぞれ本人名義の電子証明書を用いて署名を行います。第三者機関である電子認証局により本人性が担保されるため信用性の高さが特徴で、法的な証明力や真正性がより高くなる方法です。証明書委任による代理署名にも対応できます。なお、電子契約サービス「WAN-Sign」では、電子署名の当事者型も採用されています。
立会人型の仕組み
立会人型のなかでも、一般的なメール認証の仕組みをご紹介します。
メール認証の場合、契約締結する双方のメールアドレスで認証を実施し、電子署名を行います。多くの場合、電子契約サービスを提供している事業者の電子証明書を使うので、利用時の負担を軽減できるのが特徴です。
メール認証することで、文書の署名者情報にメールアドレスの情報が含まれるようになります。「アクセスコードの付与」や「本人確認書類の添付」などの方法で本人性を高めることも可能です。
②電子サインとは?
現状、国内の法律では電子サインの明確な定義がなされておらず、幅広い解釈があります。電子署名法上の「電子署名」との対比で呼ぶ場合の「電子サイン」は、タブレットによる手書きサインや承諾など、電子文書の証明に関わる電子的プロセスの総称を指すことが一般的です。一方で、当事者型電子署名を「電子署名」、立会人型電子署名を「電子サイン」と記載するケースもあります。どちらの用法で使用されているかは文脈から判断しましょう。
電子署名と電子サインの法的効力の違い
ここでは、電子署名と電子サインの法的効力の違いについて解説します。
①電子署名の法的効力
電子署名とは電子サインの一種であり、電子署名法が定める要件を満たした署名方法です。
電子署名には電子署名法の要件を満たすために、電子証明書を使用することが一般的です。また、同時にタイムスタンプを付与することで長期的に真正性を確保できます。
電子証明書は第三者機関によって厳格な本人確認が行われたうえで発行されるものであり、電子文書の本人性を担保します。
一方で、タイムスタンプは電子文書が作成や編集された正確な時刻を記録するものであり、電子文書が改ざんされていないことを証明します。
電子署名は、一般的な電子サインに比べて「本人であること」「改ざんされていないこと」を証明するための仕組みが施されているため、法的効力があります。
②電子サインの法的効力
電子サインとは、紙の文書に署名する代わりに電子的な方法を用いて押印・署名する方法全般を指す言葉であり、電子署名より広義な意味を持ちます(場合によっては立会人型電子署名のみを指すこともあります)。
例えば、電子文書に対して「タッチペンで署名」「メールアドレスとパスワードによる認証を行って署名」「生体認証を行って署名」などは、すべてが電子サインという扱いになります。
▼電子サインに含まれる概念
- 電子署名
- 電子印鑑
- デジタル署名 など
このように、電子サインは複数の概念を指す言葉であるため、必ずしも法的効力がないわけではありません。
電子署名のように、本人性や非改ざん性などが証明できる電子サインであれば、法的効力を持たせることが可能です。
基本的に電子署名以外の電子サインは、一定の有効性は認められても裁判で証拠として使用できるとは限りません。
電子署名法で求められる要件
電子署名法とは電子署名の法的有効性を定義した法律であり、具体的には電磁的記録の真正な成立の推定と特定認証業務に関する認定の制度を定めています。2001年に施行された法律であり、正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」です。
電子署名に関する定義や要件については、電子署名法第2条1項にてまとめられています。
第二条
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用元:電子署名法第2条1項
上記をまとめると、電子署名としての要件を満たすためには「本人性」と「非改ざん性」を担保する必要があることが分かります。
しかし、これらの要件は極めて抽象的であるため、電子署名法第3条および電子署名における最新の解釈を確認しておくことが重要です。
関連記事:電子契約できない契約書とは?相手の事前承諾が必要な例と見分ける際の注意点
電子帳簿保存法で求められる要件
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などの書類の保存処理にかかる負担を軽減し、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
取引に関する書類に記載される取引情報を含んだ電子データをやり取りした場合の当該データの保存義務や方法についても、電子帳簿保存法で定められています。
電子帳簿保存法は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分されており、それぞれ保存要件が異なるため注意が必要です。
ここでは、「電子帳簿等保存」と「電子取引」に焦点を当てて要件を解説します。
①電子帳簿での保存要件
電子帳簿等保存の保存要件は、「優良」と「その他」に分けられます。
「優良」とは、さまざまな要件を満たすことで青色申告特別控除が適用できるものを指しています。優良な電子帳簿として優遇措置を受けるためには、一般的な保存要件に加えて訂正・削除の履歴が確認できる状態、関連する他の帳簿との関係性が確認できる状態、検索できる状態などを確保したうえで届出書の提出が必要です。
一方で、「その他」は最低限の要件を満たしている電子帳簿のことを指しており、以下のような内容になっています。
▼「その他」の保存要件
- システム関係書類(システム概要書・仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)を備え付けていること
- 保存・保管場所にパソコンやディスプレイ、プリンターなどを備え付け、記録事項を整然とした状態で速やかに出力できること
- 税務職員による質問検査権に基づく記録のダウンロードに応じられるようにしておくこと
上記の要件は書面で保存する場合でも同様であり、「税務職員による質問検査権に基づく記録のダウンロードに応じられるようにしておくこと」については「優良」の検索要件を満たしている場合は不要です。
②電子取引での保存要件
電子取引の保存要件は、「真実性の要件」と「可視性の要件」に分けられます。それぞれの具体的な要件は以下のとおりです。
▼真実性の要件
- タイムスタンプが付与された後に、取引情報の授受を行う
- 取引情報の授受後に速やかにタイムスタンプを付与し、保存の実行者または監視者に関する情報を確認できるようにする
- 記録事項の訂正や削除を行った場合にその事実を確認できるシステムを利用する、もしくは訂正や削除ができないシステムを利用して保存する
- 正当な理由がない訂正や削除を防止するための事務処理規定を定め、それに沿った運用を行う
真実性の要件については、上記のいずれかを満たす必要があります。
▼可視性の要件
- 保存場所にパソコンやディスプレイ、プリンターなどの出力機器とシステムの操作説明書を一緒に備え付け、保存しているデータを速やかに見られる状態にしておくこと
- システムの概要書・仕様書を備え付けておくこと
- 取引日付・取引金額・取引先で検索できること
- 日付または取引金額の範囲指定で検索できること
- 2つ以上の検索項目を組み合わせて検索できること
速やかに必要なデータにアクセスできるようにしておくことが、可視性の要件を満たすうえで重要なポイントになります。
なお、売上高が1,000万円以下で、税務調査の際に保存データをダウンロードするよう求められた場合に速やかに応じることができる状態であれば、検索機能の確保は不要です。
関連記事:電子契約で変更になる社内規程|新たに必要な電子署名管理規程とは?
e-文書法で求められる要件
e-文書法とは、商法や税法、会社法や保険業法などで書面での保管が義務付けられている書類の電子保存を認める法律です。
e-文書法は通称であり、正式には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律を総称したものです。
▼e-文書法で求められる要件
- 見読性:保存したデータが読みやすい、見やすい状態であること
- 完全性:データ作成後に改ざん等されていないこと
- 機密性:情報漏洩や盗難、不正アクセスなどが防止されていること
- 検索性:必要に応じて保存データを探せること
上記はe-文書法の基本的な要件であり、文書を電子化する際にすべてを満たさないといけないわけではありません。すべての対象文書で必須とされるのは「見読性」のみであり、文書の種類によって満たすべき要件が異なるため、注意が必要です。
電子契約に関して知っておくべき法律
電子契約にはさまざまな法律が関係しており、適切に導入するためにはそれぞれの法律を知っておくことが大切です。
▼電子契約に関係する主な法律
法律名 | 概要 |
|---|---|
民法 | 契約を成立させるためのルールを定めた法律 |
民事訴訟法 | 成立した契約を証拠として扱うための条件を定めた法律 |
電子署名法 | 電子署名の法的有効性を定めた法律 |
電子帳簿保存法 | 電子帳簿を有効な形で保存するためのルール・要件を定めた法律 |
電子契約法 | 消費者が電子商取引の申込みで操作ミスをした場合の救済や電子商取引での契約成立のタイミングを定めた法律 |
デジタル改革関連法 | 押印・書面の交付などを求める手続きの見直しを行った法律 |
IT書面一括法 | 紙での交付が義務付けられていた書類の電子的な交付を認める法律 |
e-文書法 | 保存が義務化されている文書の電子的な保存を認める法律 |
印紙税法 | 電子契約において印紙税が非課税であることなどを認めた印紙税に関する法律 |
電子契約の普及に伴い、関連する法律も定期的に改正や見直しが行われているため、電子契約を導入する際は最新の情報を確認することをおすすめします。
関連記事:【2024年最新】電子契約の法改正まとめ|何が変わったか、注意点を解説
電子契約を導入する主なメリット
電子契約を導入すると、どんなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、電子契約へ移行した際に企業が得られるメリットをご紹介します。
①業務の効率化
電子契約では紙の契約書が不要となるため、従来の契約業務における印刷・押印・サインの記入・郵送といった手作業が不要となります。ペーパーレス化を推進し、効率的に手続きを進められます。また、全ての手続きがオンライン上で完結するので、契約手続きのための出社が不要となり、リモートワークの推進にもつながるでしょう。
②コストの削減
電子契約でペーパーレス化が進めば、紙に関わるコスト削減を実現できます。例えば、用紙代・インク代・切手代といった経費を削減することが可能です。また、前述した通り電子契約書は課税文書ではないと見なされるので、印紙税の負担も抑えられるでしょう。契約件数の多い企業では、大きなコスト削減の効果が期待できます。
③契約書の保管スペースの削減
電子契約の場合、契約書は電子的に保存するため、物理的な保管スペースは必要ありません。契約書を含む帳簿書類は、各種法律で保存期間が定められています。例えば、会社法では原則10年、法人税法では原則7年、電子帳簿保存法では原則7年にわたり保存が必要です。電子化すれば長期間にわたり紙の書類をキャビネットで管理する負担をなくせます。
④契約のリードタイムの短縮
電子契約なら契約のリードタイムを短縮してスムーズな取引を実現できます。契約手続きがオンラインで完結するため、担当者間の書類のやり取りでタイムラグが発生しません。従来は郵送だけで数日かかっていた手続きを、より短期間でこなせるようになります。また、担当者が出張や外出で社外にいるときも、オンラインで手続きが可能です。
電子契約を導入する際の注意点
電子契約は、自社だけで完結するものではありません。社内はもちろん、取引先ともコミュニケーションを取り、慎重に検討することが重要です。
ここでは、電子契約を導入する際の注意点を紹介します。
①電子化に対応していない契約がある
契約に関連する書類のなかには、書面化や書面での交付が義務づけられているものがあります。
誤って電子化した場合は法的な罰則があるため、導入の際は注意が必要です。書面化義務が定められている契約は以下などがあります。
- 事業用定期借地契約
- 企業担保権の設定または変更に関する契約
- 任意後見契約
しかし、法改正によって書面化義務が緩和された事例もあるため、今後変更される可能性があります。
電子契約を導入する際は、最新の情報を確認したうえで進めることが大切です。
②取引先との合意が必要になる
契約は取引先があってはじめて成立するものです。
自社だけで電子契約を取り入れても、取引先が対応していなければ電子契約の締結はできません。
電子契約を適切に導入するためには、検討する段階で取引先とコミュニケーションをとり、双方で合意することが重要です。
場合によっては取引先が拒否反応を示すことも予想されますが、電子契約のメリットや法的効力を丁寧に説明することで同意を得られる可能性があります。
③電子契約専用の業務フローの策定が必要になる
電子契約は書面契約とは異なり、業務の流れが異なるため、専用の業務フローを新たに策定する必要があります。
電子契約の導入は現場の混乱を招くことが予想されるため、事前に研修や勉強会を設け、周知することが大切です。
また、導入当初は社内文書のみ電子化を行い、使用感を確かめながら電子契約に移行する方法もあります。
物理的な紙ではなく、電子データで契約書を管理するため、情報の取り扱いについても徹底することが重要です。
④電子帳簿保存法の保存方法に対応する
紙の契約書から電子契約へ移行する場合、電子帳簿保存法のルールに則って書類を保存する社内体制を整備する必要があります。
電子帳簿保存法では取引の種類に応じて電子書類の保存方法にさまざまな要件が定められています。法的な要件を満たして書類を適切に管理するためにも、電子帳簿保存法に準拠した電子契約サービスを選びましょう。
⑤契約の保存年限、電子署名の有効期限に注意する
電子契約は、紙の契約書と同様に各種法律で保存期間が定められています。書類を長期保存する際は、保存期間中に電子署名が有効期限切れとならないよう注意が必要です。
一般的な電子署名の有効期限は2~3年であることが一般的です。それに対して、各種法律における契約書の保存期間は7~10年と定められています。電子署名の有効期限を延長したり、最長10年の有効期限を有する「長期署名」を採用したりといった対策を検討すると良いでしょう。
⑥セキュリティ対策を徹底する
電子契約へ移行する際は、社内の機密情報を情報漏洩から守るために、セキュリティ対策を徹底しましょう。電子契約サービスを導入する際は、サービス提供事業者ごとのセキュリティ対策の内容をチェックすることが大切です。
例えば、ユーザー権限設定やIPアドレスに基づいたログイン制限といったセキュリティ機能の有無を確認すると良いでしょう。また、サービス提供事業者自身の情報管理体制にも着目してサービスを選定すると安心です。
電子契約の導入手順
最後に、電子契約の導入手順をご紹介します。電子契約への移行を検討しているご担当者様は、ぜひ参考にしてみてください。
①導入前の準備
導入前の準備として、現状の契約業務を見直して、電子化によって改善すべき部分を明らかにしましょう。そのためにも、まずは業務フローを洗い出すのが効果的です。自社の契約手続きの進め方や作業内容を書き出して改善点を確認し、システム導入の目的を定めます。
②電子契約システムの選定
近年は多くの事業者が電子契約システムを提供しています。数多くのシステムがある中で自社に適したシステムを選定することが大切です。導入目的・組織の規模・予算などに応じてシステムの機能や料金プランを比較検討しましょう。その際は、電子帳簿保存法への対応やセキュリティ対策も重視するようおすすめします。
③社内および取引先との調整
導入する電子契約システムが決まったら、続いて社内外の調整を行います。自社の現場に対して、システム導入にともなう業務フローの変更点を周知するとともに、懸念点のヒアリングを実施すると良いでしょう。また、取引先に対しては電子化について十分に説明した上で理解を得て、今後の取引の進め方を調整します。
④導入およびマニュアルの準備
導入へ向けた最終準備として、新たな業務フローや電子契約システムの操作方法をマニュアル化して、社内研修を実施します。本稼働前に一部の業務のみシステムへ移行するのも一つの手です。システムの初期設定やセキュリティ対策などを実施し、準備が整ったら運用をスタートさせます。
電子契約の法的効力に関するよくあるQ&A
電子契約が法的効力を持つ根拠は?
電子契約は、電子署名法第3条により、法的効力が認められています。電磁的記録に電子署名が行われている場合、その契約は真正に成立したものと推定されます。
電子署名では、第三者機関による本人確認や電子証明書の活用により、署名者の本人性や文書の非改ざん性が保証されるため、紙の契約書と同等の信用性と法的効力を持つ仕組みになっています。
有効性を持つためのポイントは?
電子契約の有効性を確保するには、「本人性」と「非改ざん性」を担保することが重要です。電子署名法に基づく電子署名では、第三者機関による本人確認を経た電子証明書の使用やタイムスタンプの付与により、契約文書の真正性と改ざん防止が保証されます。
また、電子サインの場合も、本人性や非改ざん性を証明できる方法を用いることで、法的効力を持たせることが可能です。
電子契約書は紙の契約書と同等の証拠能力がある?
電子契約書は電子署名法に基づく電子署名が行われていれば、紙の契約書と同等に法的効力と証拠能力が認められます。
電子署名により署名者の本人性と文書の非改ざん性が担保されるため、裁判などでも有効な証拠として扱われます。
ただし、電子署名以外の一般的な電子サインの場合は、法的効力は限定的で、証拠として使用できるかはケースによります。
「WAN-Sign」で業務効率化
オンライン上で電子データとして作成され、場所や時間を問わず締結できる電子契約は、企業の業務効率向上に役立ちます。電子契約の法的効力は法律で認められており、書面契約と同等の信用性と正当性が担保されています。
しかし、電子契約は自社だけではなく取引先にも影響するため、導入する際には事前確認と合意が必要です。また、業務フローについても書面契約とは異なるため、運用方法にも注意しながら進めることが大切です。
「WAN-Sign」では、情報を取り扱うプロフェッショナルとして貴社の課題に即した電子契約・契約管理サービスをご提供します。電子契約システムに精通した専属担当者が、「WAN-Sign」の導入と導入後の利活用を無料でサポートし、スムーズな運用を支援します。
1to1でのサポート対応はもちろんのこと、導入用のマニュアルもご用意し、万全なサポート体制で電子契約サービスの導入を徹底サポートします。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。