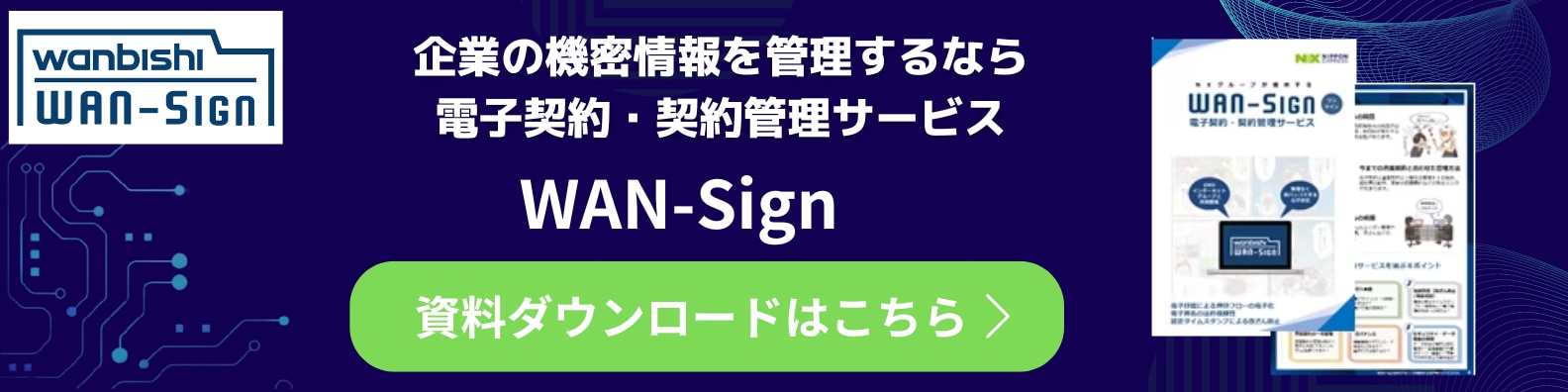電子契約の普及率とは?導入することで得られる効果や課題を紹介
(更新日:2024年12月26日)
目次[非表示]
- 1.電子契約の市場規模と成長予測
- 1.1.国内の電子契約サービスの市場規模
- 1.2.電子契約サービスの成長予測
- 2.電子契約の普及率
- 3.電子契約の普及率が上がっている背景
- 3.1.DXの推進
- 3.2.法整備の進展
- 3.3.勤務形態の多様化
- 3.4.①業務効率の向上
- 3.5.②コストの削減
- 3.6.③リモートワークへの対応
- 3.7.④保管スペースの削減
- 3.8.⑤コンプライアンスの強化
- 4.電子契約の主な課題
- 4.1.①セキュリティ対策
- 4.2.②運用体制
- 4.3.③電子化できない契約
- 4.4.④取引先の協力
- 5.電子契約の導入事例
- 5.1.【事例1】日本通運株式会社 札幌支店様
- 5.2.【事例2】日本瓦斯株式会社様
- 5.3.【事例3】北九州市役所様
- 6.電子契約の普及率が上がる今こそ、電子契約サービスの導入検討を!

近年のビジネスシーンでは書面契約から電子契約への移行が進み、普及率が年々高まっています。なぜ多くの企業で電子契約が取り入れられているのでしょうか。本記事では、電子契約の導入を検討している担当者の方へ向けて、電子契約の市場規模や普及率、導入効果などを解説します。
ペーパーレス化や脱ハンコの推進などの観点から、電子契約に関心を持っている方も多いのではないでしょうか。業務工数やコストの削減に役立つ電子契約の魅力をチェックしてみましょう。
なお、電子契約に関する基礎知識は以下の関連記事で解説しています。担当者の方は、ぜひ本記事と併せてご覧ください。
関連記事:電子契約とは?仕組みや流れ、有効性、メリットをわかりやすく解説
電子契約の市場規模と成長予測
ビジネスシーンでは徐々に電子契約への移行が進み、契約締結に利用するサービスのニーズがますます高まっている状況です。初めに、電子契約サービスの市場規模や成長予測をご紹介します。
国内の電子契約サービスの市場規模
ITコンサルティング・調査会社の株式会社アイ・ティ・アールが発表したプレスリリースによると、2021年度における電子契約サービス市場の売上金額は157億2,000万円に達したとされています。売上金額は前年度の2020年のデータと比較して56.1%の増加となり、市場規模は大きく拡大している状況です。
出典:ITRプレスリリース(2022年10月27日)
URL:https://www.itr.co.jp/topics/pr-20221027-1
電子契約サービスの成長予測
同じく株式会社アイ・ティ・アールのプレスリリースによると、電子契約サービス市場は今後も引き続き大きく拡大すると見込まれています。この先も導入企業や市場に参入するベンダーが増加すると考えられており、2026年度の売上金額は453億円に達すると予測されています。2022年以降は法改正にともない不動産業界への電子契約の普及が進み、近年は公的機関への導入も始まっている状況です。電子契約サービスの需要は、より多くの業界へ広まり、導入率が高まっていくと考えられています。
出典:ITRプレスリリース(2022年10月27日)
URL:https://www.itr.co.jp/topics/pr-20221027-1
電子契約の普及率
国内では新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるDX推進やリモートワーク(テレワーク)の普及などを背景に、電子契約の認知・普及が進んでいる状況です。総務省が公表する電子契約の利用状況に関する資料によると、2024年1月の調査結果で電子契約を「利用している」と回答した企業の割合は77.9%でした。
同調査のデータを時系列で見ると、2021年1月に実施された調査以降で普及率が上昇傾向にあることがわかります。2020年1月の調査では電子契約を「利用している」と回答した企業の割合は48.8%でしたが、2021年1月の調査では67.2%まで大きく伸びました。その後の普及率は、2022年には72.9%、2023年には76.8%、2024年には77.9%と着実に数値を伸ばしています。
海外に限らず、国内のビジネスシーンでも電子契約の利便性や導入メリットに注目し、新たに電子契約サービスを活用する企業が多くなりました。現状では約7割以上の企業が電子契約を利用しており、契約業務のデジタル化・ペーパーレス化が急務となっています。
関連記事:電子契約とは?メリットとデメリットを紹介
出典:「組織における文書の電子化又は DXに係る課題~統計委員会デジタル部会(2024年6月14日開催)資料」(総務省)p6
電子契約の普及率が上がっている背景
なぜ電子契約の普及率が上昇傾向にあるのでしょうか。近年、電子契約の普及率が上がっている背景として考えられることをご紹介します。
DXの推進
DX推進の施策の一環として契約業務の電子化を進める企業が少なくありません。近年は民間企業に限らず公的機関でもDX推進の取り組みが重視されています。電子署名やタイムスタンプなどのデジタル技術を活用することにより、法的有効性を保ちながら契約業務を電子化することが可能です。
法整備の進展
社会のデジタル化にともない、電子化に関する法整備が進展しています。例えば、電子帳簿保存法やe-文書法では、契約書を含むさまざまな書類のデータ保存のルールが定められました。また、電子署名法では書類が契約書として認められるための電子署名の要件が定められています。
勤務形態の多様化
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、ビジネスシーンではリモートワークが普及し、働き方が多様化しました。在宅勤務をはじめとした勤務形態の多様化にともない、従業員がオフィス外で働くケースを想定して、契約関係をはじめとしたさまざまな手続きのオンライン化が進んでいます。
電子契約がもたらす主な効果
電子契約を導入することで、企業にさまざまな効果がもたらされます。電子契約サービスによって自社の課題やニーズを満たせるか見極めるためにも、効果を把握しておくことが重要です。
ここでは、電子契約がもたらす5つの効果をご紹介します。
①業務効率の向上
電子契約では、印刷の手間や郵送時の待ち時間が発生せず、業務効率化が期待できます。電子契約は電子データで作成され、オンライン上でやりとりが行われるためです。従来の書面契約のように、契約書の印刷・製本・郵送などの手間はかかりません。
②コストの削減
電子契約を導入すると、契約業務全般のコスト削減が期待できます。例えば、電子契約では電子データを用いるため、印刷に必要な紙やインクなどのコストがかかりません。また、電子文書には印紙税が課税されず、収入印紙代が不要となるのもポイントです。
関連記事:電子化と紙での保管、どちらがお得?~メリット・デメリットを比較する~
③リモートワークへの対応
電子契約はオンライン上で業務を完結できるため、リモートワークでも対応が可能です。従業員は書類に押印するために出社するという必要がなく、負担軽減につながります。また、電子契約は締結する時間や場所を問わないため、社内のリモートワーク推進に役立ちます。
④保管スペースの削減
書面契約の書類は一定期間保存する必要があり、保管スペースの確保が必要となります。それに対して、電子契約は電子データであるため、物理的な保管スペースが必要ありません。契約書管理がスムーズになり、担当者の負担を抑えられます。
⑤コンプライアンスの強化
書面契約では紙の書類を郵送・受け渡しする際、書類が今どこにあるのかすぐに把握しにくいのが難点です。一方、電子契約なら業務フローの全てのプロセスがツール上で可視化されるため、進捗管理や確認作業がしやすくなり、締結漏れのリスクを軽減できます。
また、書面契約には倉庫など保管場所での紛失・劣化・情報漏洩などのリスクが存在します。電子契約なら担当者ごとにアクセス権を付与できるため、権限のない従業員や第三者が書類を閲覧できない状態となり、コンプライアンス強化につながります。
電子契約の主な課題
業務効率化やコンプライアンス強化をはじめとして、電子契約は企業に多くのメリットをもたらします。ただし、電子契約にも課題があるため、導入前に理解しておくようおすすめします。ここでは、電子契約の課題を4つ紹介します。
①セキュリティ対策
電子契約のデータはインターネット上で取り扱われ、クラウドや自社サーバーで管理するのが一般的です。こういった特徴から、電子契約にはサイバー攻撃のリスクがあるのが注意点です。導入の際はセキュリティ対策が必須となるため、ベンダーやサービスごとのセキュリティ機能をしっかりと見極めた選び方を意識しましょう。
②運用体制
電子契約は従来の契約業務とはフローが大きく異なるため、導入後は運用体制の見直しが必要になります。また、情報の取り扱い方法も書面契約と変わるので、社内ルールの見直しが必要です。電子契約の導入準備では、社内研修や勉強会などの機会を設けて、全社的に周知しましょう。
③電子化できない契約
契約書の中には、現状は電子化が認められていないものがあります。電子契約に関する法律は将来的に改正される可能性が考えられるため、常に最新情報を確認し、適切に対応しましょう。2024年11月現在、電子化できない契約の例として以下が挙げられます。
【電子化できない契約の例(2024年11月現在)】
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
- 農地の賃貸借契約書
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 など
④取引先の協力
電子契約では、自社と取引先で同じシステムを利用して署名を行います。そのため、電子契約を導入するためには、取引先から了承を得ることが不可欠です。全ての取引先に電子契約のメリットや目的を丁寧に説明しましょう。取引先がどうしても電子契約に応じるのが難しい場合は、一部の取引先のみ書面契約を継続することになります。
電子契約の導入事例
電子契約の導入により、契約業務のさまざまな課題を解決した企業が多くあります。最後に、電子契約の導入事例をご紹介します。
【事例1】日本通運株式会社 札幌支店様
グローバル物流企業の日本通運株式会社様は、北海道エリアを管轄する札幌支店で電子契約サービス「WAN-Sign」を先行導入しました。支店での膨大な量の契約管理の課題解消へ向けて、書面契約と電子契約を一元管理できるサービスを選択。手厚いサポートを利用しながら、業務工数の大幅な削減を実現しました。
【事例2】日本瓦斯株式会社様
総合エネルギー企業の日本瓦斯株式会社様は、DX推進へ向けて電子契約サービス「WAN-Sign」を導入しました。導入の決め手となったのは、金融機関への導入実績や、詳細な権限設定ができる契約管理機能です。最も締結数の多い「ガス供給契約書」を電子化することで、業務効率化やペーパーレス化による大きな効果を得られました。
【事例3】北九州市役所様
北九州市役所様は、北九州市のDX推進計画の一環として、電子契約サービス「WAN-Sign」を導入しました。全庁での電子化・ペーパーレス化推進を目指して、電子契約の導入を検討。公的機関ならではの運用開始までの準備がハードルとなったものの、受注者側が電子契約サービス事業者と契約する「事業者主体型」にて無事に電子契約の導入を実現しました。
電子契約の普及率が上がる今こそ、電子契約サービスの導入検討を!
ここまで、電子契約の市場規模や普及率、普及した背景などを解説しました。電子契約は国内でも年々普及率が高まる傾向にあり、市場規模は将来的にさらに拡大すると見込まれています。導入によって多くの効果が期待できるため、積極的な利活用がおすすめです。
『WAN-Sign』は、4,000社以上の情報資産を管理するNXワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービスです。
自社所有の国産データセンターで機密文書や個人情報を保管し、厳重な監視体制と監視機器による情報管理で様々なリスクを徹底的に排除します。
初期費用は0円で、電子契約の締結や契約管理、セキュリティやユーザー管理などの機能をオプション費用なく利用でき、さらにユーザーIDの発行数が無制限です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。