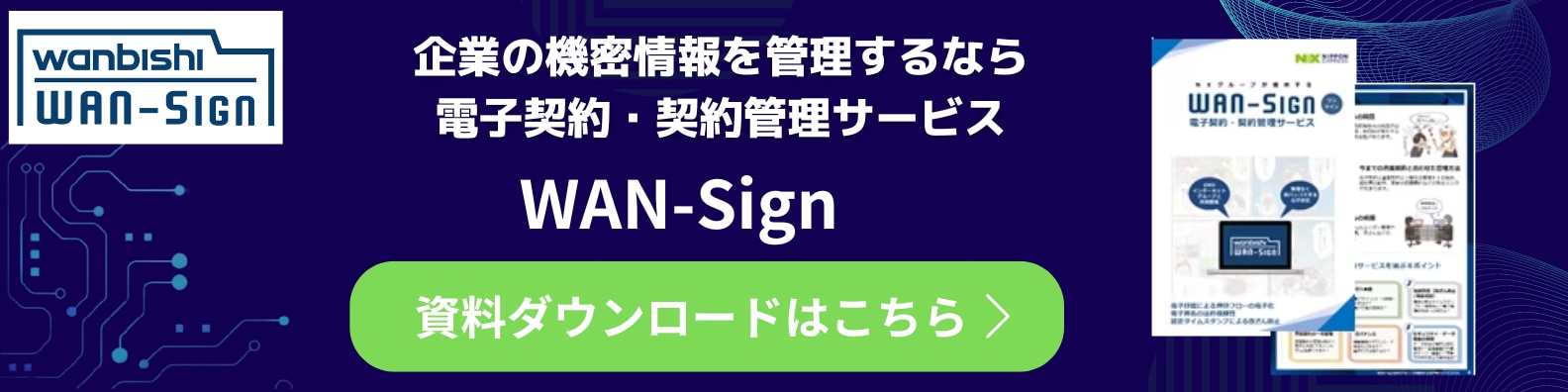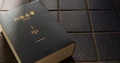【2024年最新】電子契約の種類とおすすめサービス10選、比較ポイントも解説
(更新日:2024年12月26日)
目次[非表示]
- 1.そもそも電子契約とは?
- 1.1.①書面契約との違い
- 1.2.②電子契約の法的効力
- 1.3.③電子署名の仕組み
- 2.電子契約の種類
- 3.電子契約サービスの基礎知識
- 3.1.電子契約サービスとは?
- 3.2.電子契約サービスの主な機能
- 4.電子契約サービスのタイプの種類
- 4.1.契約書作成から管理まで一括対応できるタイプ
- 4.2.書面契約書も一元管理できるタイプ
- 4.3.スモールスタートしやすいタイプ
- 4.4.多言語に対応できるタイプ
- 5.電子契約サービスおすすめ10社を徹底比較
- 5.1.①WAN-Sign
- 5.2.②電子印鑑GMOサイン
- 5.3.③イースタンプ
- 5.4.④DocuSign
- 5.5.⑤Adobe Acrobat Sign
- 5.6.⑥マネーフォワード クラウド契約
- 5.7.⑦SMBCクラウドサイン
- 5.8.⑧かんたん電子契約 for クラウド
- 5.9.⑨クラウドサイン
- 5.10.⑩CONTRACTHUB@absonne
- 6.電子契約サービスの比較ポイント
- 7.電子契約サービス導入の流れ
- 7.1.①導入目的を明確にする
- 7.2.②現状の契約業務を把握
- 7.3.③電子契約に移行する契約の範囲の検討
- 7.4.④電子契約サービスの比較・選定
- 7.5.⑤導入することを社内や取引先に周知
- 7.6.⑥電子契約システムを本導入
- 8.電子契約サービスを導入するメリット
- 8.1.①業務の効率化
- 8.2.②コスト削減
- 8.3.③契約締結までのリードタイムを短縮
- 8.4.④リモートワークへの対応
- 8.5.⑤コンプライアンス強化
- 9.電子契約サービス導入時の注意点
- 9.1.①電子契約に移行できない契約の存在
- 9.2.②サイバー攻撃のリスク
- 9.3.③取引先との合意
- 9.4.④業務フローの変更が必要
- 10.電子契約サービスの導入にあたり注意すべき法律
- 11.必要な電子契約の種類・機能に応じてサービスを選びましょう

電子文書に法的効力を持たせて取引の信用性を高めたい場合、法的要件を遵守した信頼性の高い電子契約サービスの利用をおすすめします。電子契約サービスは、各社で提供する機能やカスタマイズ性が異なるため、自社ビジネスの法的な要件や、セキュリティ基準などを満たせるかどうかが重要な選定ポイントです。また、電子契約サービスには多くの種類があり、それぞれ特徴も異なります。自社に合うタイプを選んで、契約業務のさらなる効率化を目指しましょう。
この記事では、電子契約の概要や種類、電子契約サービスの種類や導入のポイントなどを解説します。また、2024年における電子契約サービスのおすすめ10社を挙げ、各社の特徴や提供している機能、費用などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも電子契約とは?
電子契約とは、紙ではなく電子ファイルを使用し、インターネット上で契約を締結する行為です。電子契約は、電子文書に電子署名を行うことで取り交わされます。企業にとっては、業務効率化とコスト削減を実現できる点が大きなメリットです。
ここでは、電子契約と書面契約の具体的な違いや法的効力、電子署名の仕組みについて詳しく解説します。
①書面契約との違い
電子契約と書面契約の最大の違いは、契約を交わす媒体が電子データか物理的な紙を用いているか、という点です。電子契約はデータのやり取りで完結するため、オンラインで契約できます。
その他、電子契約と書面契約の主な違いは以下の通りです。
電子契約 |
書面契約 |
|
|---|---|---|
契約媒体 |
PDFデータ |
紙 |
署名方法 |
・電子署名 |
・署名 |
送付方法 |
インターネットなど |
・郵送 |
保管場所 |
・自社サーバー |
・社内キャビネットや倉庫へ物理的に保管 |
上記の比較表の通り、電子契約と書面契約ではさまざまな違いがあります。例えば、書面の場合は手書きサインや印鑑が必要でしたが、電子契約では電子署名や電子サインなどを利用して契約できます。メールなどで簡単に送付できるため、スピーディーに業務を進められるのもメリットです。物理的な保管場所を取らず、スペースの削減にもつなげられます。
②電子契約の法的効力
電子契約は法的に有効であり、書面契約と同様に利用できます。しかし、電子契約に法的証拠力を持たせるためには、当事者間の意思によって契約が交わされたことを証明する必要があります。
電子署名法の規定に基づき、電子署名が施された電子データは『本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等』に該当し、書面契約書と同等の効力を有します。
③電子署名の仕組み
電子署名とは、電子文書が改ざんされていない旨を証明できる技術です。文書の内容を「ハッシュ値」という文字列に変換し、暗号化して送信します。
ハッシュ値は「公開鍵暗号方式」で暗号化され、受信者は「公開鍵」を使ってハッシュ値を複号します。復元したハッシュ値と、受信した文書から新たに作成したハッシュ値が同一であれば、電子文書が改ざんされていないと確認できます。
また、送信された公開鍵が本人のものであると証明するのが「電子証明書」です。信頼のおける第三者機関(電子認証局)により発行されます。加えて、電子署名に「タイムスタンプ」を組み合わせることで、電子文書の作成日時の証明が可能になります。こちらも第三者機関によって発行され、ハッシュ値に変換されて送られるのが特徴です。
電子契約の種類
電子契約は、当事者型と立会人型の2種類に分けられます。ここでは、それぞれの署名方法の違いについて詳しく解説します。
①当事者型
当事者型とは、電子契約を行う当事者がそれぞれ電子署名を行う方法です。
例えば、A社とB社が電子契約を交わす際は、それぞれの名義で電子署名を行います。身近な例では、マイナンバーカードの署名用電子証明書が同じ仕組みです。電子署名を発行するためには、免許証やパスポートなどの身分証明書の発行と同様に、認証サービス事業者へ本人証明をしなければいけません。
厳格な本人確認を行っている証拠になるため、本人性の担保力が強い契約締結が可能です。
②立会人型
立会人型とは、サービス提供事業者が電子署名を実行する方法です。例えば、C社とD社が電子契約を交わす際は、第三者のサービス提供事業者であるE社が電子署名を行い、契約を締結します。
『電子署名法第3条』によると、「電子署名が本人の意思に基づき行われている場合は、本人による電子署名に該当する」との見解を示しています。そのため、立会人型の電子署名でも法的効力は有効で、契約上の問題は発生しません。
立会人型のメリットとしては、当事者が電子署名を発行する必要がないため、取引相手に負担をかけず迅速に契約できる点が挙げられます。
関連記事:電子契約とは?メリット、書面契約との比較とともに解説
電子契約サービスの基礎知識
電子契約を行う際は、電子契約サービスを利用する方法が一般的です。概要や主な機能を確かめてみましょう。
電子契約サービスとは?
電子契約サービスとは、専門業者が提供する専用のプラットフォーム・ソフトウェア・ツールなどを利用し、電子書面での契約書の作成・署名・管理などを行うサービスのことです。
従来の紙の契約書や手続きをデジタル化し、効率化・迅速化・コスト削減を実現するとともに、電子署名(電子証明書)を行って文書に法的効力を持たせることができます。
初期費用0円で基本的な機能を利用できるサービスもあれば、有料プランでより高度な機能やセキュリティを利用できるサービスもあります。そのため、複数社のサービスを比較検討し、自社ビジネスにより適している1社を選定することが重要です。
電子契約サービスの主な機能
一般的な電子契約サービスには、電子文書を用いた契約プロセスにおける基本的な機能が搭載されています。
基本機能 |
概要 |
電子署名 |
デジタル技術で契約書にある電子署名を実行する |
テンプレート作成 |
契約書のテンプレートを作成し、再利用やカスタマイズを容易にする |
ワークフロー管理 |
契約プロセスの進捗状況を管理し、承認者への通知や自動化されたワークフローを提供する |
ドキュメント管理 |
契約書の保存やアクセス制限、契約期限管理などを行い、契約書の一元管理をサポートする |
署名状況の追跡とリマインダー |
署名の進捗状況をリアルタイムに追跡し、未署名の通知やリマインダーを送信する |
モバイル対応 |
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスからも契約書の作成や署名を可能にする |
システム連携機能 |
外部システムとの統合をサポートし、CRMやドキュメント管理システムなどとの連携を可能にする |
セキュリティ対策とコンプライアンス |
データの暗号化やアクセス制御、監査ログなどのセキュリティ対策を実施し、法的要件に準拠する |
カスタマーサポート |
ユーザーへのサポートやトレーニングを提供し、問題解決に寄与する |
レポーティングと分析 |
契約プロセスのデータを収集し、分析やレポーティングを行い、効率や改善のポイントを把握する |
上記の機能以外にも一部のサービスでは、特定の機能に特化していたり独自の文書管理機能を有していたりするため、重要な選定ポイントとなります。
電子契約サービスのタイプの種類
電子契約サービスには複数の種類があり、企業によって適したタイプは異なります。こちらでは、主な電子契約サービスのタイプをご紹介します。それぞれの特徴やメリットについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
契約書作成から管理まで一括対応できるタイプ
契約書管理業務では異なる形式の書類を複数取り扱ったり、入力項目が多かったりと、煩雑になりやすいことが課題とされます。契約書類が多い企業では、担当者の負荷が増えてしまうことも課題のひとつです。こうした業務の効率化におすすめできる電子契約サービスが、契約書作成から管理までを一つのシステムで行えるタイプです。契約書の発行や送付、管理などをまとめて対応でき、複数のシステムを使い分ける必要がないところが魅力です。
書面契約書も一元管理できるタイプ
電子契約を取り入れたとしても、紙の契約書を完全になくすのは難しいケースがあります。例えば、取引先の企業が書面契約書を希望する場合や、電子化が認められていない契約書を発行する場合が挙げられます。
従来の書面の契約書と電子契約を併用していく場合、管理が煩雑になりやすいのが課題です。書面契約書と電子契約を一元管理できるタイプの電子契約サービスなら、ひとつのシステム上でまとめて検索や閲覧などを行えます。過去に作成した契約書類を一緒に管理したいといったニーズにも対応できます。
スモールスタートしやすいタイプ
電子契約サービスの中には、シンプルな機能を備えており低価格で利用できるものがあります。導入費用や月額費用を抑えて低コストで始めたい、部署単位で電子化を取り入れたいといったケースに有効です。契約件数が少ない企業や個人事業主などにも適したタイプといえます。
また、電子契約サービスを利用したことがなく、安価で試してみたいという企業にもこういったタイプがおすすめです。無料プランを利用可能なサービスもあるため、コスト重視の場合はチェックしてみましょう。
多言語に対応できるタイプ
海外との取引が多い場合は、多言語対応の電子契約サービスも選択肢に入れると良いでしょう。加えて、取引先のある国で導入企業数が多い電子契約サービスなら、相手方が利用している可能性も高まります。海外との電子契約の導入をスムーズに進めやすくなるでしょう。
電子契約サービスおすすめ10社を徹底比較
電子契約サービスは多くのベンダーから提供されています。自社に合う製品を選ぶことが大切です。ここからは、電子契約サービスでおすすめの10社のサービスの特徴や費用体系を紹介します。
①WAN-Sign
『WAN-Sign』は、豊富な機能と高度なセキュリティを標準装備し、当事者型署名から立会人型署名、文書管理に至るまで提供する電子契約・契約管理サービスです。
電子契約の締結や契約管理、セキュリティ、内部統制、ユーザー管理などの機能を初期費用無料で提供し、さらに業界最高水準の内部統制機能で安全性を確保しています。
従来の紙媒体での書類と電子文書を合わせた一元管理も安全に実現する、ハイブリッドな電子契約サービスです。書面契約と電子契約を併用していきたい場合や、過去の書面契約書も同じシステム上で管理したい場合にもおすすめです。
②電子印鑑GMOサイン
導入社数350万社以上の導入実績を誇る『電子印鑑GMOサイン』は、締結レベルの高い電子文書の契約も安全にサポートするサービスです。他社の電子契約サービスと比べて、長期署名に対応した⽴会⼈型の電⼦署名を比較的安価に提供しており、コスト削減に寄与しています。
電子帳簿保存法に準拠した安心・安全の電子契約サービスや豊富な支援実績により、数多くの企業に選ばれています。
③イースタンプ
『イースタンプ』は、実印タイプと認印タイプの2種類の電子署名に対応している電子契約サービスです。
電子署名タイプや電子サインタイプでの契約、タイムスタンプ、スキャンでの文書保存などをワンパッケージで提供しています。
ベーシック・プラチナという2種類のサポート体制で、顧客の悩みや課題に寄り添った柔軟なサービスを提供しているのが特徴です。
④DocuSign
『DocuSign』は多言語対応の電子署名サービスです。世界各国で利用されている実績があるため、多彩な国との取引がある企業にも向いています。
マルチデバイス対応のサービスで、無料ダウンロードできるモバイルアプリは、iOSやAndroidなどの端末で使用できます。保存済みの契約書はラベリングされるため、スムーズに検索でき、必要なときにすぐに目的の書類を見つけ出せるようになります。連携可能な外部システムも多く、組織内の文書管理効率化に役立つでしょう。
⑤Adobe Acrobat Sign
大企業での導入実績が豊富な『Adobe Acrobat Sign』は、PDF形式での電子署名の作成や共有をサポートしているサービスです。MicrosoftやSalesforce、Workday、その他のアプリとの連携に幅広く対応できます。
Adobe Acrobat Signは、世界各国の最高レベルのコンプライアンス要件に対応したAdobe Signを使用しており、ビジネスの業種や地域に関係なく、電子契約のコンプライアンスを推進しています。
身近なオフィスツールで手軽に電子署名を作成でき、より透明性のある電子契約を実現するソリューションです。
⑥マネーフォワード クラウド契約
『マネーフォワード クラウド契約』は、電子文書における契約書の申請・承認・締結・保存・管理などの機能を網羅した電子契約・契約管理システムです。
電子契約だけではなく、紙媒体での契約書も一元管理し、さらに他社の電子契約から受領したデータに関しても取り込むことが可能です。
契約書送信料と契約書保管料が無料のサービスであり、契約書の送信件数・保管件数に応じた課金もないため、コストパフォーマンスにも優れています。
⑦SMBCクラウドサイン
弁護士が監修する『SMBCクラウドサイン』は、各種法律に遵守した信頼性の高い契約プロセスと、高度なセキュリティを備えた電子契約サービスです。
メガバンクの厳格なセキュリティ基準で電子文書の定期的なモニタリングを行い、なりすましや改ざんなどのリスク因子を排除しています。
国内で最も電子契約の利活用が進んでいる企業の一つであるSMBCグループへの導入ナレッジとノウハウを活かした、充実のサポート体制もSMBCクラウドサインの強みです。
⑧かんたん電子契約 for クラウド
『かんたん電子契約 for クラウド』は、電子署名とタイムスタンプにより信頼性の高い電子契約をクラウド上で支援するサービスです。
認定タイムスタンプで国内屈指のシェアを誇るセイコーソリューションズが提供するサービスであり、金融機関に対する豊富な導入実績があります。
各社のタイムスタンプ・電子署名一括検証機能や、紙媒体の契約書のスキャンや保存、複数の契約当事者が存在する契約書への電子署名などにも幅広く対応しています。
⑨クラウドサイン
『クラウドサイン』は、導入社数250万社以上、累計送信件数1,000万件以上の実績を持つ電子契約サービスです。
電子署名法に遵守したクラウド型の電子契約をサポートしており、弁護士によるサービス全体の監修や、各種認証制度を満たした万全のセキュリティ体制でデータを保護しています。
多機能なプロダクトを備えたユーザビリティの高いシステムを提供し、スムーズな導入にも寄与しています。
⑩CONTRACTHUB@absonne
『CONTRACTHUB@absonne』は、電子契約サービス市場において従業員1,000名以上の大企業での導入が広く進んでいるサービスです。
大量の取引に対応できる文書管理機能やフロー管理など豊富な機能が標準搭載されており、契約プロセスの改善に寄与しています。
導入企業の要件に合わせた細かい設定も可能で、高い柔軟性を備えた電子契約サービスです。
電子契約サービスの比較ポイント
複数の電子契約サービスから自社に適した1社を選定するためには、以下の比較ポイントを確かめてみてください。
- 自社のビジネスで必要な法律面と商習慣に対応できるか
- 自社のビジネスで必要なセキュリティ要件を満たしているか
- 契約件数あたりの送信料は適正か
- 文書管理機能の有無
- 使用中の外部システムとの連携性(API・SSOなど)
- 当事者型署名と立会人型署名のどちらに対応可能か など
電子契約サービスの製品数は多く、さまざまなタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。そのため、まず自社のビジネスに必須となる機能が備わっているかを確認することが重要です。法律や商習慣、セキュリティ要件など、自社に必須となる条件をしっかりと調べておきましょう。
自社に導入済みの既存システムとの相性もチェックしておくことが大切です。連携可能なシステムであれば、業務の自動化を進めやすくなります。
また、電子契約サービスは長く使っていくことになるため、コストパフォーマンスも気になるところです。導入費用や月額利用料などの料金が予算を超えそうな場合は、契約内容を確認してみましょう。不要なオプションが含まれている場合、必要なものだけに絞り込めば予算内に収まる可能性があります。実績や信頼を備えた電子契約サービスを選びたい場合には、公式Webサイトに掲載されている導入実績や導入事例を参考にすると良いでしょう。
実際にサービスを体験したうえで導入を検討したい場合には、お試し体験の利用もおすすめです。実際に触れてみることで、操作性の良いUIか、使い勝手は良いかなどをチェックできます。無料トライアルを利用できるサービスを探してみましょう。
電子契約サービス導入の流れ
電子契約サービスは、事前に導入までの流れを把握しておくことが重要です。ここでは、導入までの流れを一つずつ詳しく解説します。
①導入目的を明確にする
まずは、電子契約サービスを導入する目的を明確にします。
目的を明確化せずに導入した場合、機能が複雑すぎて使いこなせないサービスを導入してしまったり、自社に必要な機能が備わっていなかったりと、さまざまな問題が発生する可能性があります。
電子契約サービスの導入目的を明確にする際は、具体的に解決したい課題を洗い出し、実現したいことをリストアップし、言語化することが重要です。具体的な導入目的の例は、以下を参考にしてください。
- 印紙税や郵送費用などのコストを削減したい
- 契約業務の作業工数を減らしたい
テレワーク中の従業員も契約業務に参加できるようにしたい など
何を目的に電子契約サービスを導入するか明確にしておくことで、自社のニーズにあった体制などがわかり、電子契約サービスを選びやすくなります。
②現状の契約業務を把握
次に、現状の契約業務の運用方法を把握します。電子契約は書面契約とは業務の流れが異なるため、現状の運用方法や業務フローと照らし合わせたうえで、必要に応じて社内ルールを変更することになるでしょう。
なお、適切な社内ルールを構築するためには、取り扱っている契約の種類や作成頻度、作成期間、保管方法など、細部に至るまで細かく確認することが重要です。
③電子契約に移行する契約の範囲の検討
電子契約へ移行する導入範囲を検討します。導入当初は自社と取引先の双方が不慣れであるため、最初からすべての契約を電子契約へ移行するのは困難です。そのため、自社と取引先の状況に合わせて、導入範囲を検討する必要があります。
最初は、重要度の低い文書から電子契約に切り替えていき、従業員が業務フローに慣れてきた段階で少しずつ導入範囲を広げていくことを推奨します。そのためにも、まずはどの文書を電子契約へ移行するか検討しておきましょう。
④電子契約サービスの比較・選定
電子契約サービスを導入する際は、複数のサービスを比較することが重要です。電子契約サービス導入後のサービス変更には、膨大な手間とコストがかかるため、しっかり選定しましょう。そのためにも、最初から一つのサービスに絞るのではなく、複数サービスを比較しながら選定することが重要です。
比較する際は文書管理機能の有無や外部システムとの連携性のほか、セキュリティ要件を満たしているか、送信料は適正か、などを重視することを推奨します。
⑤導入することを社内や取引先に周知
次に、契約業務の変更内容や決裁者などを、社内・取引先に周知します。実際に契約業務に携わる担当者には、電子契約サービスの操作方法や運用ルールを正確に伝え、対象者が多い場合には説明会の実施も検討する必要があるでしょう。
また、社内だけではなく取引先によっては電子契約に触れた経験がない可能性もあるため、利用するメリットや契約方法を正確に伝えることも重要です。
⑥電子契約システムを本導入
準備が整った後は、自社のニーズに最適と思える電子契約システムを導入します。当初は電子契約に移行しやすい契約のみに適用し、少しずつ定着させていくことが重要です。
電子契約サービスを導入するメリット
実際に電子契約サービスを導入することで、企業にはどのような効果があるのでしょうか。ここでは、導入後に得られるメリットについて詳しく解説します。
①業務の効率化
電子契約サービスを導入することで、契約締結に関わる業務効率を向上できます。
従来までの書面契約の場合、契約書の印刷や製本、収入印紙の貼付、封入、投函など、1つの契約を締結するまでに多くの事務作業が必要でした。しかし、電子契約サービスを利用することでオンライン上にて契約を締結できるため、従来の業務フローを大幅に削減し、業務効率化につなげられます。
また、オンライン上で契約書の作成・送信が可能なため、リモートワーク中の従業員が契約業務を行える点も大きなメリットです。
②コスト削減
電子契約システムを導入すると、紙やインク、印紙などのコストがかかりません。
書面契約は法律により収入印紙を貼ることが義務付けられており、1件あたり200円から数十万円の費用がかかる場合もあります。また、書面契約を作成するためのインク代や印刷代、郵送代などの事務経費もかかるため、こうしたコストを削減できる点は大きなメリットです。
電子契約サービスの利用にはランニングコストなどが必要になりますが、それを差し引いてもコスト削減につながる可能性は高いと考えられます。
③契約締結までのリードタイムを短縮
電子契約では、契約書を郵送したり取引先へ持っていったりする必要がありません。
紙の契約書は、取引先から手元に戻ってくるまでに約1週間程度かかります。万が一相手が受け取れなければ返送されるため、さらに長い期間がかかる場合もあります。
しかし、電子契約であれば印刷、製本、郵送などの一連の手続きを削減でき、リアルタイムでオンライン上にて契約を締結できるため、待ち時間が発生しにくい仕組みです。スピードが重視されるビジネスでは、リードタイムが短縮できる点は大きなメリットといえます。
④リモートワークへの対応
オンライン上で行われる電子契約は、リモートワークしている従業員も対応できます。
新型コロナウイルス感染症の流行により、リモートワークという新しい働き方が急速に普及しています。しかし、書面契約ではハンコが必要、製本できないなど、さまざまな理由で従業員が会社へ出勤せざるを得ない状況に陥るケースが少なくありませんでした。
電子契約は紙とハンコが不要であり、時間と場所を選ばずに契約を締結できるため、リモートワーク中の従業員を担当者にすることも可能です。オフィスにいなくても契約業務を円滑に進められる体制を構築しておけば、幅広い働き方に対応できます。
⑤コンプライアンス強化
電子契約サービスを導入することで、コンプライアンス強化が期待できます。
電子契約サービスでは、データの閲覧範囲や承認者の設定、IPアドレスによるアクセス制限などを行えます。また、タイムスタンプにより改ざん検知が可能であり、改ざんを防止することもできます。書面のような物理的な紛失や破損、情報漏洩などの心配もありません。
電子契約サービス導入時の注意点
電子契約サービスを導入する際は、どのようなポイントに気をつければ良いのでしょうか。ここでは、導入時の注意点を詳しく解説します。
①電子契約に移行できない契約の存在
契約書の中には、書面での交付が義務付けられているものがあります。書面契約での締結が義務付けられている契約書は、当然ながら電子契約が締結できません。
法令が改正されることで、電子契約で利用できる契約書の種類も増加が予測されますが、現時点では誤って電子化した場合は法的な罰則を受ける可能性があります。
法律により、書面化が必須と義務化されている主な契約書は以下の通りです。(2024年11月現在)
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
- 企業担保権の設定または変更を目的とする契約 など
企業によっては、完全なペーパーレス化は難しいでしょう。紙の契約書と電子契約の併用も検討するのがおすすめです。
②サイバー攻撃のリスク
電子契約サービスはインターネットに接続されており、サーバーにデータを保管するため、サイバー攻撃の被害に遭うリスクがあります。しかし、紙の契約書でも紛失や情報漏洩のリスクはゼロではありません。そのため、いずれの方法を利用する場合でも、リスクを完全にゼロにするということは難しいのが現状です。
とはいえ、電子契約サービスには情報漏洩や改ざんを防ぐためのセキュリティ対策が講じられているため、過度に心配する必要はありません。電子契約サービスを選ぶ際は、高度なセキュリティ対策を実施しているベンダーを探すことも大切です。
③取引先との合意
自社が電子契約サービスを導入しても、取引先が電子契約に対応していなければ契約を交わせない可能性があります。
特に、当事者型署名を行う場合は、契約相手も同じ電子契約サービスの導入が必要となります。ただし、主流である立会人型署名では、相手方には同じサービスの導入や費用が発生しないケースが一般的です。
しかし、いずれにせよ取引先の理解と協力は不可欠であるため、丁寧に説明を行い、合意を得たうえで運用を進めることが望ましいでしょう。
④業務フローの変更が必要
電子契約を導入する場合は、書面契約とは異なる業務フローが必要となります。これまで紙の契約に慣れていた担当者が心理的な抵抗感を覚えることもあるため、導入時は業務フローの見直しや周知を行い、最適化を目指すことが重要です。
導入に際して手間はかかりますが、電子契約に切り替えることで業務効率化も叶えられます。加えて、利用中の顧客管理システムなどと他のシステムとの連携が可能なものを選べば、さらなる効率化も実現可能です。従業員の負担軽減につながるため、導入メリットが大きいことを伝えて社内の理解を得ましょう。
電子契約サービスの導入にあたり注意すべき法律
電子契約は、電子帳簿保存法をはじめとした法律を守って実行する必要があります。そのためにも、関連する法律をしっかりと確認しておくことが重要です。以下では、電子契約サービスを取り入れる際に知っておきたい主な法律をご紹介します。
電子帳簿保存法
電子契約を適切に運用するためには、電子帳簿保存法を遵守する必要があります。
電子帳簿保存法では、電子契約を行った際のデータの保存条件などに関して細かいルールが定められています。また、電子契約サービスの導入後は、規定に基づいた税務調査が行われるケースもあるため、適切な方法で電子契約データを管理しなければいけません。
電子契約サービスを選ぶ際は、電子帳簿保存法の要件を満たす機能を持つものを選びましょう。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による「JIIMA認証制度」では、電子帳簿保存法に対応している製品に認証が与えられます。認証を受けた製品にはパッケージにロゴの使用が認められるため、判断材料のひとつにしてもよいでしょう。
電子署名法
「電子署名」は電子署名法によって定義されています。加えて、電子署名の行われた電子文書は、紙の契約書と同じ法的効力があると記されています。
電子署名を実行するときは、電子署名法で示す要件を満たさなくてはいけません。有効な契約書を発行するためには、電子署名法に対応した電子契約サービスを選ぶことも大切です。
民法
企業同士や企業と個人などの契約では、民法の「契約方式自由の原則」によって、法令に定めがある場合を除いて「書面作成が必須ではない」と示されています。この原則があることで、電子契約でも有効な契約ができるといわれています。
必要な電子契約の種類・機能に応じてサービスを選びましょう
電子契約の種類や電子契約サービスの種類、比較ポイントや導入時の注意点などを解説しました。法的効力のある電子契約を交わすためには、電子契約サービスを活用しましょう。関連法律に対応しているシステムであれば、よりスムーズかつ安心して契約業務を進められます。その際は、サービスの種類によって対応できる署名の種類や機能性、セキュリティ強度などが異なるため、複数社を比較してより適切なものを選ぶことが大切です。自社のビジネスに合うサービスを探しましょう。
電子契約サービスをお探しの場合は、ぜひ『WAN-Sign』をご検討ください。『WAN-Sign』は、当事者型・立会人型の両方の署名に対応し、さらに紙媒体とデジタルでの契約書を一元管理できる電子契約・契約管理サービスです。
業界最高水準のセキュリティと内部統制機能で電子契約に安心をもたらし、サービスの導入前から導入後まで専任の担当者が丁寧にサポートします。
法的リスクを回避しながら、電子契約・文書管理をデジタルソリューションで効率化したい方は、お気軽にご相談ください。
>>お問い合わせ
>>資料ダウンロード