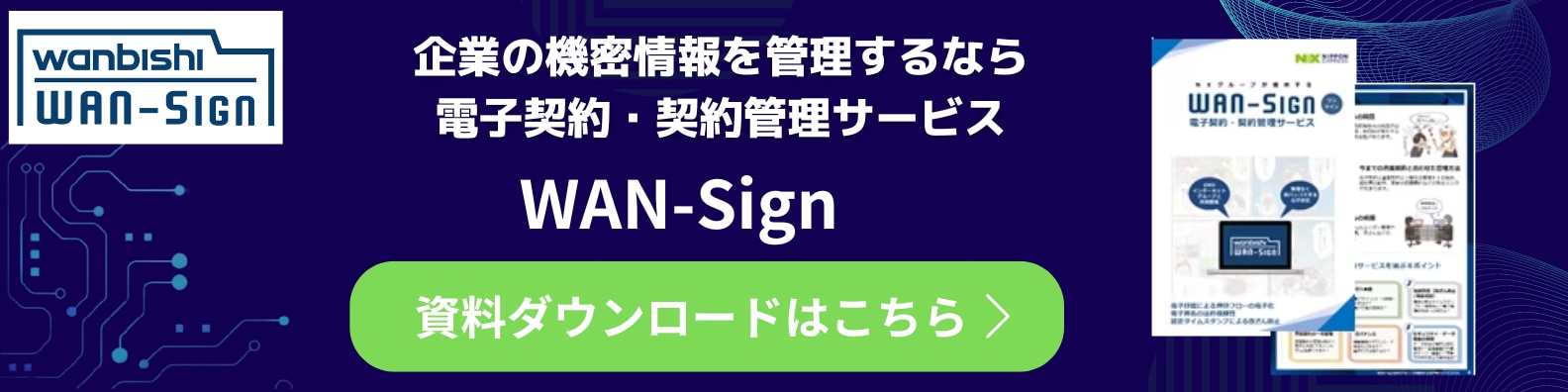電子契約と書面契約書の違い│ひな形を作成する際の表現や注意点
(更新日:2024年12月26日)
目次[非表示]
- 1.電子契約とは?
- 2.書面契約書と電子契約の違い
- 3.電子契約のひな形を作成するメリット
- 3.1.作成時間を短縮できる
- 3.2.契約更新がスムーズになる
- 3.3.押印位置を固定化できる
- 4.書面契約書と電子契約における文言の違い
- 4.1.後文
- 4.2.契約書を表す文言
- 4.3.写しと原本に関する文言
- 4.4.書面契約書を電子契約に流用する際に変更すべき表現
- 5.電子契約のひな形を作成する際のポイント
- 5.1.日付は西暦・和暦を統一する
- 5.2.契約内容に合わせて条項を追加・変更する
- 6.電子契約に対応可能な書類
- 6.1.業務委託契約書
- 6.2.秘密保持契約書
- 6.3.発注書(申込書、発注請書)
- 7.法律により電子契約に求められる要件
- 7.1.電子帳簿保存法により求められる要件
- 7.2.e-文書法により求められる要件
- 8.電子契約の法的効力
- 9.契約書のひな形作成などの業務効率化には電子契約サービスの導入がおすすめ

電子契約の文面は、書面契約書とは作り方が異なる部分があります。また、契約におけるトラブルを防ぐための証明方法や、改ざん防止の方法などにも違いがあります。業務効率化へ向けて電子契約のひな形を作成する場合は、電子契約と書面契約書の違いを理解しておきましょう。
この記事では、電子契約と書面契約書の違いを解説するほか、電子契約へ移行するにあたり、ひな形での具体的な書き方や注意点までお伝えします。ぜひ参考にしてみてください。
電子契約とは?
電子契約とは、電子データによって作成された契約書のことです。
電子ファイルは物理的に保管する紙とは異なり、サーバーやデータセンターなどのオンライン上で保管されます。また、電子契約は電子署名法に準拠して電子署名を行えば、法的な効力を持たせることも可能です。
具体例として、オンラインショッピングやソフトウェアのライセンス契約、企業間での契約や取引、行政機関によるサービスなど、さまざまなシーンで電子契約が活用されています。
書面契約書と電子契約の違い
従来の書面での契約書とデジタル形式の電子契約の違いは、以下のような点にあります。
項目 |
書面契約書 |
電子契約 |
|---|---|---|
書類の媒体 |
紙ベース |
電子データ |
本人性の担保 |
署名や捺印 |
電子署名の実行 |
改ざん防止の方法 |
物理的な変更の検出 |
公開鍵暗号方式の署名、タイムスタンプ |
送付方法 |
郵送、手渡しなどの物理的な配送 |
電子メール、オンラインフォーム、電子署名プラットフォームなど |
保管方法 |
書類のファイリング |
デジタルストレージやクラウドサービスへの保存 |
印刷の有無 |
あり |
なし |
電子契約は物理的な形で存在する書面契約書とは異なり、デジタル形式で存在し、電子データとして扱われます。本人性は捺印ではなく電子署名によって担保され、改ざん防止のために公開鍵暗号方式のデジタル署名が採用されます。また、電子契約はデジタルストレージやクラウド上に保存するため、物理的な保管スペースは不要です。
関連記事:電子契約とは?メリットとデメリットを紹介
電子契約のひな形を作成するメリット
電子契約へ移行する場合は、業務効率化の観点からひな形を作成すると良いでしょう。ここでは、電子契約のひな形を作成するメリットをご紹介します。
作成時間を短縮できる
電子契約のひな形があれば、書類作成にかかる時間を大幅に短縮できます。ひな形を活用すると、相手方に合わせて必要な箇所を変更するだけで簡単に契約書を作成できます。取引先とのやり取りの件数が多い企業ほど、書類交付の手間を減らすことができ、業務効率化の効果を期待できるでしょう。
契約更新がスムーズになる
電子契約のひな形は、初回の契約締結時だけでなく、契約更新のタイミングでも業務効率化に役立ちます。契約更新の際に契約締結日などの一部の内容を変更するだけで、速やかに対象案件の契約書を作成できるためです。
押印位置を固定化できる
電子契約のひな形で押印位置を固定化すると、押印の有無を効率的にチェックできるようになり、契約担当者の確認作業がスムーズになります。確認作業の手順が容易になれば、契約担当者の異動や退職にともない引き継ぎが生じた際も安心です。
書面契約書と電子契約における文言の違い
書面契約書と電子契約では、書類に記載する一部の文言の書き方に違いがあります。それぞれの文言の違いを押さえておきましょう。
後文
後文とは、契約書の末尾に記載される定型の文章のことです。書面契約書では一般的に、契約者の氏名・契約日時・書類の通数・書類の保管方法などが記載されます。ただし、書面契約書と電子契約では運用が異なることから、以下のように後文の内容を見直す必要があります。
【書面契約書の後文の記載例】
本契約の成立を証するため、甲および乙は本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、それぞれ1通を保有する。 20〇〇年〇〇月〇〇日 |
【電子契約の後文の記載例】
本契約の成立を証するため、甲および乙は本電磁的記録を作成し、各自電子署名を行い、双方が電磁的記録を保管する。本契約においては、本電磁的記録を原本とし、本電磁的記録を印刷した文書は写しとする。 |
電子契約へ移行する際は、記載例を参考に変更点をご確認ください。具体的に変更すべきポイントについて、以降の小見出しで解説していきます。
契約書を表す文言
書面契約書では、契約書のことを「本書」や「書面」などの文言で表現します。電子契約のひな形では、これらの文言を「電磁的記録」や「本契約書ファイル」などの文言に置き換えるのが望ましいでしょう。
写しと原本に関する文言
電子契約の後文には、電子データを「原本」、電子データを印刷した文書を「写し」とするための文言を入れると良いでしょう。原本と写しの混乱を避けるためにも、「本契約においては、本電磁的記録を原本とし、本電磁的記録を印刷した文書は写しとする」といった形で明記しましょう。
書面契約書を電子契約に流用する際に変更すべき表現
書面契約書のひな形を電子契約の作成時に流用する場合は、具体的に以下の表現を変更する必要があります。
【変更すべき表現の例】
- 「事前の書面による承諾なしに」→「事前の書面または双方が合意した方法による電磁的記録による承諾なしに」などへ変更
- 「本書を2通作成」→「本電磁的記録を作成」などへ変更
- 「記名押印(署名捺印)のうえ」→「電子署名を措置し」などへ変更
- 「甲・乙各1通を保有」→「双方が電磁的記録を保管する」などへ変更
電子契約では、印鑑の押印や手書きのサインが不要となり、代わりに電子署名を行います。書面契約書のひな形に記載された文言を変更せずに使用すると、思わぬトラブルにもつながりかねないため注意が必要です。業務の電子化へ向けて、該当の表現をチェックしておきましょう。
電子契約のひな形を作成する際のポイント
続いて、電子契約のひな形を作成する際に押さえておきたいポイントをお伝えします。一般的な契約書のテンプレートを活用する場合は、自社の業務に合わせて調整を加えましょう。
日付は西暦・和暦を統一する
契約書に記載する契約締結日などの日付は、文書内で西暦・和暦をいずれか一方に統一し、両方が混在しない状態にするのが望ましいでしょう。その理由は、西暦・和暦の混在によって生じる混乱やミスなどを避けるためです。なお、西暦・和暦のどちらを選択しても、法的な効力に違いはないとされています。
契約内容に合わせて条項を追加・変更する
一般的に配布されている契約書のテンプレートを使用する際は、そのまま自社のひな形として使うのは避けて、全体的な内容を確認した上で必要に応じて条項の追加・変更を行いましょう。テンプレートの内容が自社の業務に適さない場合は、契約業務に不備が生じてしまうおそれがあります。
電子契約に対応可能な書類
電子署名に関する法整備が進んだ昨今、電子契約に対応可能な書類は以下のように多数存在します。一部の書類は、紙の書面での締結が義務付けられている場合もあります。
- 業務委託契約書
- 業務請負契約書
- 秘密保持契約書
- 発注書(申込書、発注請書)
- 代理店契約書
- 取引基本契約書
- 雇用契約書
- 委任契約書(準委任契約書)
- 工事請負契約書
- 下請法第3条書面など
ここでは、電子契約に対応可能な「業務委託契約書」「秘密保持契約書」「発注書(申込書、発注請書)」に関して、特徴や電子化するメリットをご紹介します。
業務委託契約書
業務委託契約書は、業務の委託者(発注者)が受注者側(受託者)へ業務委託を依頼する際に必要な契約書です。契約金額が記載されている場合は請負契約とみなされ、印紙税の対象となります。電子契約に移行すると、契約書がデジタル形式で取り扱われるため、印紙税がかからないのがメリットです。業務委託契約を多くのスタッフと結ぶサービス業などでは、電子化により契約業務の手間や工数を大幅に削減できます。
秘密保持契約書
秘密保持契約書とは、営業や技術に関する機密性の高い情報に対し、目的以外の使用や第三者への開示を禁止するために締結する契約書です。
秘密保持契約書は、取引開始前に締結されるケースが多く、定型的な文章で作成および使用されるのが一般的です。そのため、オンライン上で契約書作成・確認・署名を行う電子契約に移行しやすいというメリットがあります。特に短期間での効率的な確認や署名が必要な場合は、秘密保持契約書の電子化が有効です。
発注書(申込書、発注請書)
発注書・申込書・発注請書などの業務で使用頻度の高い書類は、よく電子契約へ移行されます。これらの書類は、注文内容が毎回ある程度決まっているため、テンプレート化が容易なケースが多いです。電子契約サービスを利用して契約書をテンプレート化することで、オンライン上での作成で送信が簡単にできるため、受発注の手続きや作業工数を大幅に削減できます。
また、発注書は件数が多くなる場合があり、紙媒体での管理にはコストや手間がかかります。電子契約に移行することでサーバー上にデータを保管できるため、取引に関する情報の検索や抽出、追跡が容易になる点もメリットです。
法律により電子契約に求められる要件
電子契約を導入する際は、「電子帳簿保存法」や「e-文書法」などの法律で定められた要件を満たす必要があります。ここでは、法律により電子契約に求められる要件をご紹介します。
電子帳簿保存法により求められる要件
電子帳簿保存法は、請求書・領収書・契約書・見積書などの国税関係帳簿書類のデータ保存に関する法律です。電子契約においては、電子的にやり取りした契約書のデータを保存する際、以下の要件を満たす必要があります。
- 改ざん防止の措置を取ること
- 日付・金額・取引先などの条件で検索できること
- ディスプレイやプリンターなどを備え付けること
2024年1月以降、電子的にやり取りしたデータは、電子データのままでの保存が義務づけられています。電子データを紙に印刷しての保存は認められないため注意しましょう。
e-文書法により求められる要件
e-文書法とは、『民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律』と『民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』の2つの法律をまとめたものです。
e-文書法では、電子契約の利用において、見読性・完全性・検索性を確保することが求められています。
項目 |
説明 |
|---|---|
見読性 |
契約書の内容が明確に表示され、読みやすいフォーマットやレイアウトで提供されていること |
完全性 |
作成時点での内容が改ざんされず、原本のまま保存されること。また、電子署名やハッシュ関数で完全性を確保すること。 |
検索性 |
契約内容に関して、データの適切なインデックス化とキーワード検索により、効率的な情報検索が可能であること。 |
前述した電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類が対象となります。それに対して、e-文書法は国税関係帳簿書類のほか、医療・建築・保険をはじめとした広い範囲の文書が対象となるのが主な違いです。
電子契約の法的効力
電子契約は、特定の要件を満たすことで法的効力を持たせることが可能です。
電子署名法の第2章・第3条では、適切な電子署名を実行することで、法的効力を有する旨が説明されています。
第三条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
電子署名や認証手段が使用されていない電子契約については、契約書の完全性や真正性が保証されず、法的効力が制限される可能性があります。そのため、電子契約サービスを利用する際は、各法律に準拠しているかどうかが重要な選定ポイントです。
関連記事:電子契約の法的効力とは?電子署名法や電子帳簿保存法で求められる要件
契約書のひな形作成などの業務効率化には電子契約サービスの導入がおすすめ
ここまで、電子契約と書面契約書の違いのほか、ひな形を作成する際の表現や注意点まで解説しました。電子契約は電子署名によって本人性の担保や、改ざん防止ができることが特徴です。ひな形を作成する際は、書面契約書との文言の違いに注意しておきましょう。社内の契約手続きの業務効率を改善するなら、電子契約・契約管理サービスの『WAN-Sign』がおすすめです。
『WAN-Sign』は、当事者型署名から立会人型署名まであらゆる仕組みの署名に対応しています。各種法律に準拠した法的効力を持つ電子契約の作成・送信、書面契約書との一元管理など多機能を標準装備しています。法的なルールに準拠した契約締結や保管が可能で、法改正にも対応できます。
電子契約への移行を安心して進めたい方は、導入前からサポートが手厚い『WAN-Sign』をぜひご利用ください。
>>お問い合わせ
>>資料ダウンロード