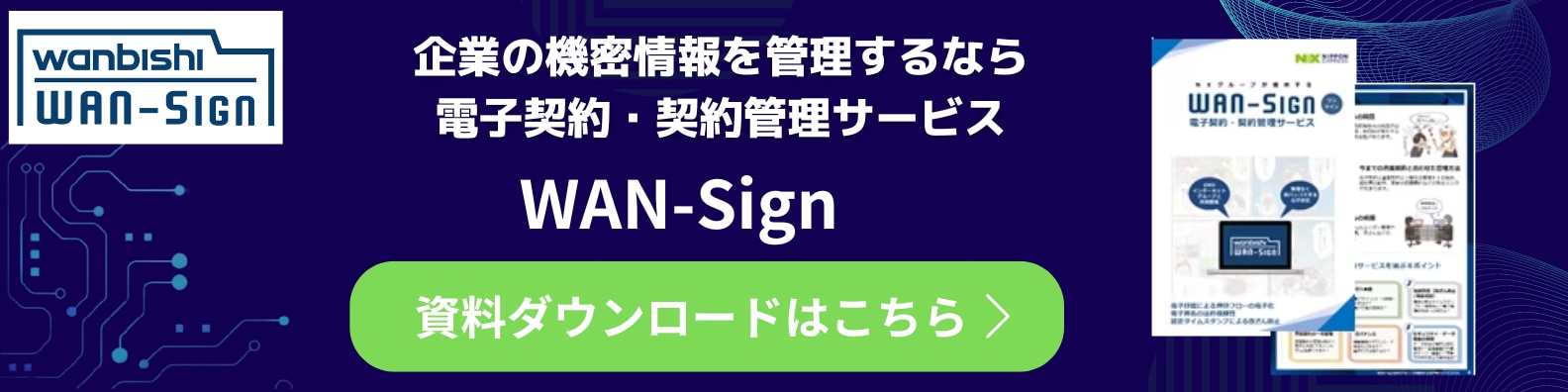APIの具体的な利用例を紹介! システム部門でなくてもわかる連携の仕組み
目次[非表示]
- 1.APIとは?
- 1.1.APIとは何か?
- 1.2.人間のコミュニケーション
- 1.3.システムのコミュニケーション
- 2.APIの利用例
- 2.1.企業サイトへの地図の埋め込み
- 2.2.家計簿アプリとクレジットカード利用明細の連携
- 2.3.SNSの情報取得や投稿
- 2.4.経理システムと会計ソフトの連携
- 2.5.ECサイトでの決済システムの導入
- 2.6.クラウドサービスでのファイルの自動連携
- 2.7.POSレジとの連携
- 2.8.基幹システム間のデータ連携・機能拡張による取引の効率化
- 3.APIを実装する流れ
- 3.1.Step1. 目的や実装したい機能の明確化
- 3.2.Step2. APIの提供会社にユーザー登録
- 3.3.Step3. APIキーとシークレットキーの取得
- 3.4.Step4. 仕様を確認してAPIを実装
- 4.APIの利用例に関するよくあるQ&A
- 4.1.APIを活用する際の注意点は?
- 4.2.Web APIで主流なのは?
- 4.3.APIを叩くとはどういう意味ですか?
- 5.まとめ

ビジネスシーンでよく聞く「API」とは、一体どのような機能のことを指し、導入によって何ができるようになるのでしょうか。APIは電子契約・契約書管理のシステムでも活用されており、業務効率化に役立つため、連携の仕組みを理解しておきましょう。
この記事では、APIに関する基礎知識のほか、利用例や業務で実装する流れまで解説します。システム部門以外のご担当者様にもイメージしやすいようにご説明するため、ぜひ参考にしてみてください。
APIとは?
初めに、「API」に関する基礎知識を解説します。APIの仕組みについて、身近なコミュニケーションの例に置き換えてわかりやすくお伝えします。
APIとは何か?
APIとは、「システム同士がやり取りするための、システム間の共通言語」のことを指します。英語の「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の頭文字を取った用語です。
以下では、APIの仕組みをより理解しやすくするために、「人間のコミュニケーション」と「システムのコミュニケーション」に例えながら解説します。
人間のコミュニケーション
国内のビジネスシーンでは、日本語が共通言語として使われています。そのため、取引先へ契約業務を依頼する際は「秘密保持契約を締結したいので、申請をお願いします」と日本語で依頼することで、取引先が内容を理解して事務手続きを行えます。ところが、突然フランス語で「Je souhaite conclure un accord de confidentialité, alors veuillez postuler.」と依頼したら、取引先は依頼内容を理解できず、事務手続きを行えなくなってしまうでしょう。このように、複数の企業が円滑にコミュニケーションを取るためには、どの言語を使って依頼するかのルールが重要となっているのです。
システムのコミュニケーション
前述した人間のコミュニケーションと同様に、異なるシステム同士のコミュニケーションでも「共通言語」が重要となります。システム間のコミュニケーションにおいて、共通言語に該当する仕組みの一つが「API」です。複数のシステム間でやり取りが必要な際にAPIを用いると、システム同士が自動で情報のやり取りができるようになります。こうした連携によって、システムの業務効率化や利便性向上の効果が期待できるのです。
ここまでお伝えしたように、APIとは「システム同士がやり取りするための、システム間の共通言語」を指します。共通言語であるAPIがあれば、異なるシステム同士を連携させて、より効率的で便利にシステムを利用できるようになります。
APIの利用例
それでは、APIを活用すると具体的にどのようなことを実現できるのでしょうか。ここでは、日常生活で利用するシステムの活用例をご紹介します。
企業サイトへの地図の埋め込み
企業サイトに掲載された本社所在地の住所とともに、Googleマップで地図が表示されている場合があります。このケースでは、企業サイトとGoogleマップがAPI連携することで、Webサイト上に地図情報を表示してユーザーの利便性を高めています。
家計簿アプリとクレジットカード利用明細の連携
一部の家計簿アプリには、クレジットカードの利用金額や銀行の口座残高が自動で登録される便利な機能が搭載されています。こちらは、アプリケーション同士がAPI連携することで、利用金額や口座残高のデータを取得しています。
SNSの情報取得や投稿
SNS間のAPI連携によって、既存のSNSアカウントを利用して、別のSNSでのログインや投稿ができるようになります。新規アカウントを開設することなく、簡単に複数のSNSでの情報取得や投稿を実現できます。
経理システムと会計ソフトの連携
経理システムと会計ソフトのAPI連携により、経理システムに入力したデータが会計ソフトに自動で登録されます。一方のシステムに入力するだけで作業が完了するため、データを転記する手間がなくなり、業務効率化に貢献できます。
ECサイトでの決済システムの導入
ECサイトにクレジットカード決済の機能が搭載されている場合があります。こちらはAPI連携によってECサイトと決済システムが連携する仕組みで、EC事業者は自社で決済システムを開発することなく、セキュリティの高い決済方法を導入できます。
クラウドサービスでのファイルの自動連携
複数のクラウドサービス間でAPI連携によってデータのやり取りを行う場合があります。これにより、異なるクラウドサービス間でデータを速やかに共有することが可能です。より柔軟にデータの利活用や分析ができるようになります。
POSレジとの連携
飲食店などで用いられるPOSレジを、レシピ管理システムや分析ツールとAPI連携させる方法もあります。連携によって売上や顧客のデータを詳細に分析したり、分析結果を新規メニュー開発に反映させたりできます。
基幹システム間のデータ連携・機能拡張による取引の効率化
企業の複数の基幹システムをAPI連携でつなぐことで、大規模なデータ連携・機能拡張を実現できます。これにより、特定の業務に特化した基幹システムをより幅広い業務で活用できるようになり、取引先とのやり取りの効率化につながります。例えば、API連携により、受注に関わる書類発行・送付の自動化や、注文データと在庫データの自動連携などが可能になります。
ここまで、さまざまなAPI連携の具体例をご紹介しました。APIを利用することで、異なる機能を持つシステム同士が補完し合い、サービスの利便性がより高まります。API連携は、サービス提供者と利用者の双方に大きなメリットをもたらしているのです。
APIを実装する流れ
ここでは、APIを実装する手順を4つのステップでご紹介します(※あくまで一例であり、異なる場合があります)。自社で開発するほかに、API連携の機能を搭載したサービスを導入する方法もご検討ください。
Step1. 目的や実装したい機能の明確化
初めに、自社のAPI連携の目的や実装したい機能を明確にします。また、対象のサービスでAPIが提供されているか、事前に確認しておくこともポイントです。
Step2. APIの提供会社にユーザー登録
続いて、APIの提供会社でのユーザー登録を行います。ユーザー登録の際は、主に「サービスの名称」「APIの利用目的」「APIを利用するサイトのURL」などの情報を登録します。
Step3. APIキーとシークレットキーの取得
APIの提供会社による審査が完了したら、「APIキー(=アプリケーションやユーザーの認証情報)」と「シークレットキー(=セキュリティ確保のための認証情報)」の取得を行います。
Step4. 仕様を確認してAPIを実装
取得したAPIキーとシークレットキーを利用して、仕様書の通りに自社サービスへの実装を行いましょう。また、API連携の機能を搭載したサービスを導入すれば、自社で実装しなくても、サービスを提供している会社のエンジニアのサポートを得ながら環境を構築することが可能です。
APIの利用例に関するよくあるQ&A
APIを活用する際の注意点は?
APIを活用する際には、利用規約と料金体系の確認、セキュリティ対策、レート制限の遵守、エラー処理の実装、信頼できる提供元の選定、そして提供終了のリスク管理といった注意点があります。
これらの点を事前に理解し、適切な対応を行うことで、APIを安全かつ効率的に利用できます。
Web APIで主流なのは?
Web APIで広く利用されている方式の一つに「REST」があります。
RESTはシンプルで扱いやすい点が特徴です。
多くのWebサービスで現在も採用されており、近年は「GraphQL」など新しい方式の活用も広がっています。
APIを叩くとはどういう意味ですか?
「APIを叩く」とは、システム同士が情報をやり取りするために、APIを使ってリクエスト(要求)を送ることを指します。
APIは「システム間の共通言語」なので、APIを叩くことで別のシステムからデータを取得したり、操作を実行したりできるようになります。
まとめ
ここまで、APIに関する基礎知識や利用例、業務で実装する流れまでお伝えしました。APIとは「システム同士がやり取りをするための、システム間の共通言語」のことです。共通言語であるAPIによって、システム間での連携が可能となり、より利便性が高まります。API連携で契約業務を効率化するなら「WAN-Sign」がおすすめです。
電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、API連携に対応しています。そのため、現在ご利用中のサービスや社内の基幹システムとも柔軟に連携することが可能です。API連携によって、既存の業務環境のままスムーズに電子契約へ移行し、業務効率化を実現していただけます。契約業務の手間や工数が多く課題を感じているご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせや資料ダウンロードをご利用ください。契約業務の効率化をサポートいたします。
「WAN-Sign」を用いたAPI活用術について詳しくは、ダウンロード資料でご案内しています。以下のページのフォームからお申し込みください。
「WAN-Sign」と連携可能なシステムや、システムの詳細については、どうぞお気軽にNXワンビシアーカイブズまでお問い合わせください。各種検証やエンジニアによるフォローを承ります。
API連携の仕組みや、メリット・デメリットについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の関連記事も併せてご覧ください。
API連携の仕組みはどうなっている?メリットやデメリット、活用事例
>>資料ダウンロード