発注書と発注請書の違いは?それぞれの役割と記載項目、注意点を解説
目次[非表示]
- 1.発注書・発注請書に関する基礎知識
- 1.1.発注書(注文書)とは?
- 1.2.発注請書(請書、注文請書)とは?
- 1.3.発注書と発注請書の違い
- 1.4.発注書と発注請書を作成する取引の流れ
- 2.発注書・発注請書を作成する理由
- 2.1.発注書を作成する理由
- 2.2.発注請書を作成する理由
- 3.発注書・発注請書に記載する項目
- 3.1.発注書に記載する項目
- 3.2.発注請書に記載する項目
- 4.発注書・発注請書を作成する際の注意点
- 4.1.発注書を作成する際の注意点
- 4.2.発注請書を作成する際の注意点
- 5.まとめ
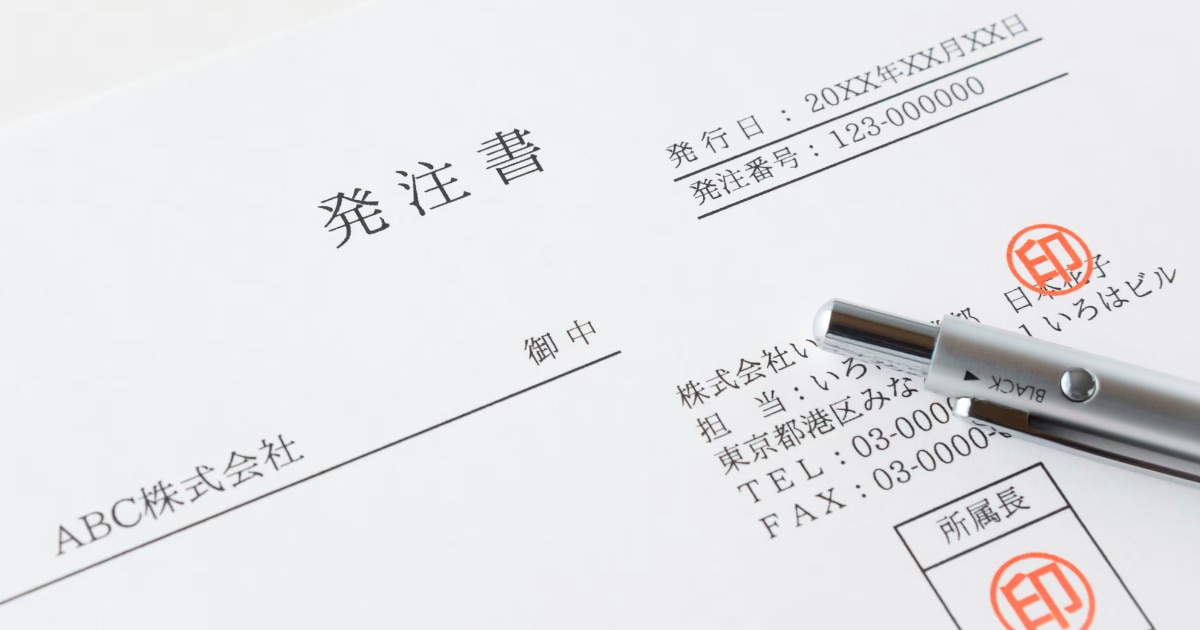
ビジネスシーンでは、企業間の取引を正確に進めるために、発注側・受注側の企業がそれぞれ書類を発行します。このうち発注側が発行する「発注書」は注文内容を証明する書類、受注側が発行する「発注請書」は注文の承諾を証明する書類です。
この記事では、「発注書」と「発注請書」の違いや、それぞれの書類の役割について解説します。書類の記載項目や、発行する際の注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
発注書・発注請書に関する基礎知識
初めに、「発注書」と「発注請書」のそれぞれの特徴をご説明した上で、違いを解説します。基礎知識として改めて確認してみましょう。
発注書(注文書)とは?
「発注書」とは、商品・サービスを注文する発注側の企業が、注文内容を証明するために発行する書類です。「注文書」とも呼ばれます。発注書には、注文内容を明確にして証拠を残す役割があります。
発注請書(請書、注文請書)とは?
「発注請書」とは、商品・サービスを納品する受注側の企業が、注文を正式に承諾したことを証明するために発行する書類です。「請書」や「注文請書」とも呼ばれます。発注請書には、注文を承諾し取引の成立を証明する役割があります。
発注書と発注請書の違い
発注書と発注請書は書類の発行者に違いがあります。「発注書」は発注側が発行する書類であるのに対して、「発注請書」は受注側が発行する書類です。
発注書と発注請書を作成する取引の流れ
発注書と発注請書は、取引の流れの中で、一般的に以下のタイミングで発行されます。ここでは、その他の書類の発行を含め、取引の全体的な流れをご紹介します。
|
発注側が見積もりを依頼する
↓
受注側が「見積書」を発行して金額を提示する
↓
発注側が「発注書」を発行して注文する
↓
受注側が「発注請書」を発行して取引が成立する
↓
受注側が商品・サービスを納品して「納品書」を発行する
↓
発注側が納品物の内容を確認して「検収書」を発行する
↓
受注側が「請求書」を発行して代金を請求する
↓
発注側が代金を支払う
|
発注書・発注請書を作成する理由
「発注書」と「発注請書」は、なぜ取引にあたり作成する必要があるのでしょうか。ここでは、作成する理由を書類別に解説します。
発注書を作成する理由
発注者が受注者に対して申込みの意思を示すため
発注書には、発注側の企業からの申込みの意思表示としての役割があります。書類を受領した受注側の企業は、正式な発注を受けて安心して納品までの準備を進めやすくなります。
発注者と受注者で商品・サービスの仕上がりのイメージを共有するため
発注書を発行すると、発注側の企業は発注内容を取引先へ明確に伝えることが可能です。商品・サービスの仕上がりイメージなどの情報を事前に共有し、トラブルを防止する意味合いがあります。
発注請書を作成する理由
受注側が発注書による申込みを承諾する意思を示すため
発注請書には、受注側の企業が発注内容を正式に承諾する意思表示としての役割があります。書類を受領した発注側の企業は、発注が無事に受理されたことを確認できます。
発注・受注の事実および内容を明確化しトラブルを防ぐため
発注請書の発行によって、受発注の内容を明確に記録することで、数量や金額などのミスを避けやすくなります。納品前に両者が合意した内容が明らかになり、コミュニケーションの齟齬によるトラブルを避けることにつながります。
発注書・発注請書に記載する項目
「発注書」と「発注請書」を作成する際は、書面に以下の項目を盛り込むと良いでしょう。発注側のご担当者様は、書き方の参考にしてください。
発注書に記載する項目
発注側の企業は、発注書に以下の項目を記載しましょう。特に、発注内容は誤りがないよう正確に記載することが重要です。
項目 |
記載時のポイント |
宛先(受注者) |
発注書の送付先を記載します。 |
発行番号・発行日(取引日) |
書類の発行番号と発行日を記載します。 |
件名 |
案件名などを記載します。 |
発注者の情報(会社名・住所) |
発注者の会社名や住所などを記載します。 |
発注内容(商品概要・単価・合計金額) |
発注する商品名・単価・数量・合計金額などを記載します。 |
納期・支払い条件 |
発注側と受注側の双方で合意した納期や支払い条件などを記載します。 |
備考 |
その他に記載すべき事項があれば、必要に応じて追記します。 |
発注請書に記載する項目
受注側の企業は、発注請書に以下の項目を記載します。発注請書は発注書を受領した後に発行する書類のため、取引の流れに合わせて適切な発行日を設定しましょう。
項目 |
記載時のポイント |
宛先(発注者) |
発注請書の送付先を記載します。 |
発行番号・発行日(取引日) |
書類の発行番号と発行日を記載します。発注書の発行日よりも後の日付を設定します。 |
件名 |
案件名などを記載します。 |
受注者の情報(会社名・住所) |
受注者の会社名や住所などを記載します。 |
受注内容(商品概要・単価・合計金額) |
受注する商品名・単価・数量・合計金額などを記載します。 |
納期・支払い条件 |
発注側と受注側の双方で合意した納期や支払い条件などを記載します。 |
備考 |
その他に記載すべき事項があれば、必要に応じて追記します。 |
発注書・発注請書を作成する際の注意点
最後に、「発注書」と「発注請書」の作成で注意したいポイントをお伝えします。取引先と適切に手続きを進めるために、以下の注意点を押さえておきましょう。
発注書を作成する際の注意点
下請法に基づき、親事業者には発注書の発行が義務づけられている
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」においては、下請取引を適正化する目的で、親事業者に発注書の交付が義務づけられています。下請取引に該当する場合、親事業者は業務を委託する際ただちに取引内容・金額・支払期日・支払方法などを記載した発注書を下請事業者に対して交付する必要があります。
【参考】「下請代金支払遅延等防止法」(中小企業庁)
発注書でも場合によっては印紙税の課税文書となる可能性がある
発注書は基本的には印紙税の課税対象ではありません。ただし、発注書が契約の成立を証明する「契約書」に該当すると見なされるケースでは、課税文書となる可能性があります。詳しくは国税庁の質疑応答事例をご確認ください。
【参考】「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」(国税庁)
一定の保存期間がある
発注書は取引を記録する重要な書類のため、法律で一定期間の保存が義務づけられています。法人の場合は7年間、個人事業主の場合は5年間の保存が必要です。
発注請書を作成する際の注意点
収入印紙を貼り付ける必要がある
発注請書の中でも、請負についての契約書に該当する場合は印紙税の課税対象となります。課税対象の書類を発行する際は、契約金額に応じた税額分の収入印紙を貼り付けましょう。ただし、電子文書で発行する場合は印紙の貼り付けが不要になります。
【参考】「No.7102 請負に関する契約書」(国税庁)
一定の保存期間がある
発注書と同様に、発注請書も法律で一定期間の保存が義務づけられています。保存期間は、法人の場合は7年間、個人事業主の場合は5年間です(ただし、一部保存期間が異なる場合もあります)。
まとめ
ここまで、「発注書」と「発注請書」の違いや役割、書類の記載項目、発行する際の注意点を解説しました。どちらの書類も、受発注の取引を証明する重要な役割があります。ただし、発行手続きに手間がかかることから、近年は書類を電子化する企業が多くなっています。電子文書は業務効率化に役立つほか、印刷・郵送・印紙税などのコストを削減できることがメリットです。
NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、契約業務の電子化に貢献します。電子証明書やメール認証によって電子契約を実現できるため、これまで紙で発行していた契約書や発注書、発注請書などを安全に電子化することが可能です。契約業務の効率化でお悩みのご担当者様は、お気軽に無料の資料ダウンロードやお問い合わせをご検討ください。
>>高機能で安心・安全な電子契約・契約管理を実現できるWAN-Sign









