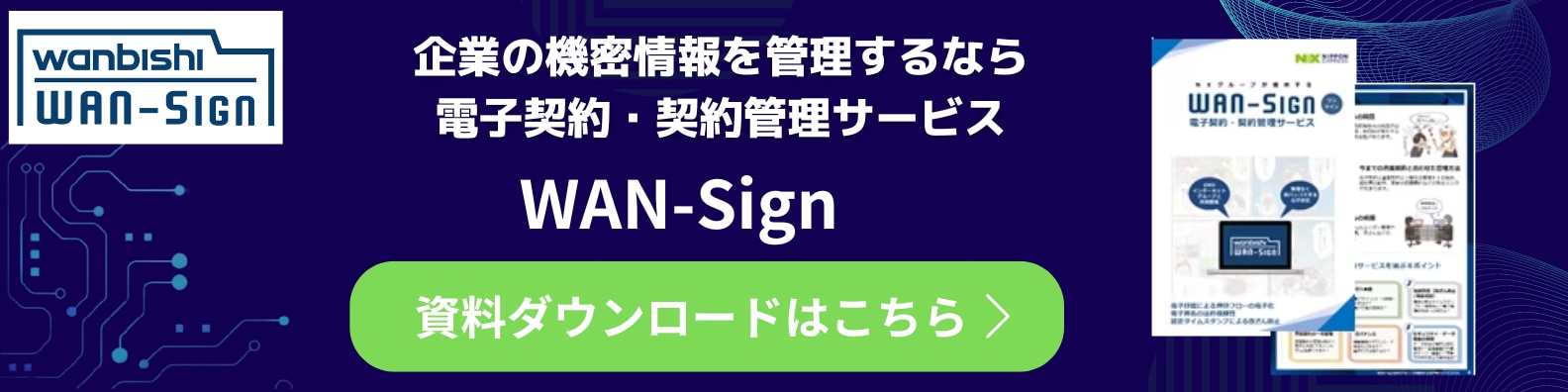不動産取引の電子契約の流れと事例|電子化できる・できない契約は?
目次[非表示]
- 1.不動産取引における電子契約の現状
- 1.1.そもそも電子契約とは?
- 1.2.不動産取引の電子化は2022年5月から全面解禁
- 2.電子契約できる・できない不動産契約
- 2.1.電子契約できる主な不動産契約
- 2.2.電子契約できない主な不動産取引
- 3.不動産取引における電子契約の流れ
- 3.1.Step1.入居申込み・購入申込み
- 3.2.Step2.契約書や重要事項説明書の電子交付
- 3.3.Step3.IT重説の実施
- 3.4.Step4.電子署名による電子契約締結(オンライン契約)
- 3.5.Step5.締結完了・入居・引渡し
- 4.不動産取引の電子契約のメリット
- 4.1.契約者同士の日程調整がしやすい
- 4.2.契約締結がスピーディーになる
- 4.3.印紙税が不要でコスト削減につながる
- 4.4.契約書類の検索がしやすい
- 5.不動産取引の電子契約のデメリット・注意点
- 5.1.インターネット環境が必要になる
- 5.2.電子契約サービスの利用には一定の費用がかかる
- 5.3.セキュリティ対策とデータのバックアップが必要になる
- 5.4.取引先に電子契約利用の同意を得る必要がある
- 6.不動産取引の電子契約を行う際に注意すべき法律
- 7.まとめ
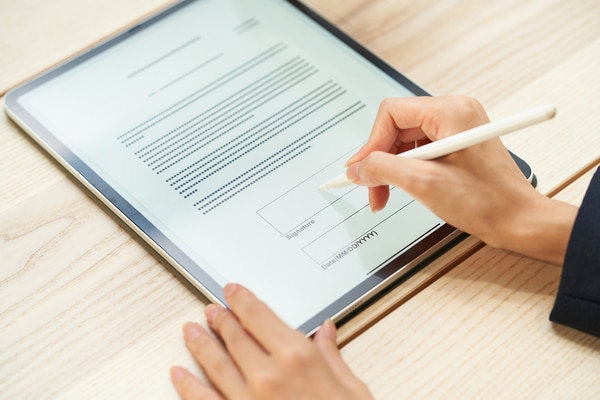
「宅地建物取引業法(宅建業法)」や「借地借家法」の法改正にともない、2022年5月から不動産取引での電子契約が全面解禁されました。現状は、多くの不動産取引がオンラインで契約を結べる状況となっています。デジタル化により業務効率の改善やコスト削減などのメリットが期待できるため、紙での契約から電子契約への切り替えを検討してはいかがでしょうか。
この記事では、不動産取引の電子契約の流れや、電子化できる・できない契約の種類、電子契約のメリット・デメリットといった基礎知識をご紹介します。不動産業務の効率化へ向けて契約の電子化を検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産取引における電子契約の現状
初めに、現状の不動産取引において電子契約が可能となっている契約の種類をご紹介します。不動産業界の電子化の動向を改めて確認してみましょう。
そもそも電子契約とは?
電子契約とは、オンラインで電子的に契約を締結する仕組みのことです。従来の契約で用いられていた紙の書類やハンコによる押印などが全て電子化されます。電子書類はメールやクラウドなどを経由して相手方に共有され、契約システム上で締結が行われるのが一般的です。なお、電子契約は紙とハンコを用いた従来の契約と同様に法的な効力を持ちます。
関連記事:電子契約とは?メリット、書面契約との比較とともに解説
不動産取引の電子化は2022年5月から全面解禁
2021年5月12日に成立した「デジタル改革関連法」に基づいて、「宅地建物取引業法」や「借地借家法」が改正され、2022年5月から不動産取引の電子化が全面解禁されました。法律が改正される前は、一部の書類のみ書面での交付が必須とされていたものの、法改正以降はほぼ全ての書類の電子化が認められています。また、書面への押印義務も廃止されています。
【出典】国土交通省「ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について」
URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
電子契約できる・できない不動産契約
ここでは、電子契約できる・できない不動産契約の例をご紹介します。業務効率化へ向けて契約業務の電子化を検討している担当者の方は、対応可否を確認してみましょう。
電子契約できる主な不動産契約
現状、不動産業界の契約業務は全面的に電子化が認められています。例えば、今後は以下の不動産契約も電子契約が可能です。これらの契約を締結する場合、書類を交付する必要がありますが、いずれも電磁的方法で発行して構いません。
媒介契約書
宅地建物取引業者に不動産の売買・賃貸・交換などの仲介を依頼するための契約書です。
重要事項説明書
宅地建物取引士による重要事項説明(重説)で用いられる書類です。重要事項説明には、消費者に契約内容に関する重要な情報を十分に理解してもらう意味があり、法律上で実施が義務づけられています。
賃貸借契約書
マンションやアパートなどの賃貸物件を貸し借りするために、貸主と借主が締結する契約書です。
売買契約書
売主と買主が締結する契約書です。例として、土地や建物の不動産売買を行う場面において用いられる「不動産売買契約書」が挙げられます。
定期借地権設定契約書
長期間にわたり土地を貸し借りするために、貸主と借主が締結する契約書です。
定期建物賃貸借契約書
一定期間にわたり賃貸物件を貸し借りする際、契約期間の満了後に賃貸借が終了する契約を締結するための契約書です。
電子契約できない主な不動産取引
事業用定期借地に関する契約書
事業用の用途で土地を貸し借りする際、契約期間の満了後に更地返還する契約を締結するための契約書です。契約を締結する場合は公正証書により作成する必要があるため電子契約できません。
企業担保権の設定または変更が目的の契約書
企業担保権(=金融機関からの借入の際に企業価値全体を担保とするもの)の設定や変更を目的とした契約書です。公正証書による契約締結が必要となるため電子契約できません。
任意後見契約書
ここまでご紹介した不動産取引以外にも、「任意後見契約書」も公正証書による契約締結が必要であるため電子契約が認められていません。任意後見契約書とは、判断能力の低下に備えて本人が任意後見人を選任するための契約書です。
不動産取引における電子契約の流れ
不動産取引で電子契約をする流れを解説します。以下のステップで契約締結を進めましょう。
Step1.入居申込み・購入申込み
不動産業者や物件によっては、オンラインでの入居・購入に対応しています。近年は不動産業界のDX推進や消費者ニーズの多様化にともない、Webカメラで物件の内見を行ったり、ビデオ通話アプリで接客を受けたりできるようになりました。入居希望者・購入希望者がWebサイトから問い合わせを行い、オンライン上で申込みを行います。
Step2.契約書や重要事項説明書の電子交付
電子化した契約書や重要事項説明書を相手方に共有します。書類を電子的に発行する場合は、トラブル防止の観点から電子契約サービスを利用すると良いでしょう。オンラインで署名を実施する機能が搭載されているため、タイムスタンプにより手続きの履歴が残り、適切な手順に従って契約した事実を記録できます。
Step3.IT重説の実施
オンラインで重要事項説明を実施します。宅地建物取引士による重要事項説明は、一定の条件を満たせばオンラインで実施することが可能です。オンラインで重要事項説明を行うことは、「IT重説」や「オンライン重説」などと呼ばれます。
IT重説は対面の場合と同様に、宅地建物取引士が説明を行わなければなりません。また、説明を実施する環境に関して、以下の条件を満たすことが必須です。双方向的なコミュニケーションを確保するために、ビデオ会議ツールを導入しましょう。
|
IT重説の実施にあたり、映像・音声を通じて説明内容を問題なく理解できるよう適切な機器やサービスを導入し、環境を整備することが大切です。IT重説の実施方法について、詳しくは国土交通省のマニュアルをご確認ください。
【参考】「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明 実施マニュアル概要」(国土交通省土地・建設経済局 不動産業課)
Step4.電子署名による電子契約締結(オンライン契約)
IT重説が完了し、相手方から内容に同意を得られたら、電子契約サービスを利用して重要事項説明書への電子署名を行います。続いて、契約書への電子署名を行ったら、電子契約締結(オンライン契約)が完了です。契約締結後は、電子契約サービスで契約書と重要事項説明書を保管できます。
関連記事:建設業でも電子契約は利用可能?必須要件と導入のメリット
Step5.締結完了・入居・引渡し
オンラインでの契約締結後の流れは、基本的には書面契約と同様です。入居希望者への鍵の引き渡し、または購入希望者への物件の引き渡しが行われます。
不動産取引の電子契約のメリット
不動産取引で電子契約を利用するメリットを解説します。業務効率化を推進するために、ぜひ電子契約を活用しましょう。
契約者同士の日程調整がしやすい
オンラインで不動産契約を締結する場合、ビデオ会議ツールを活用していつでもどこでも重要事項説明を実施できるようになります。対面で締結するケースのように、移動時間や距離による制約を受ける心配がありません。遠方でもオンライン対応によってスケジュールの柔軟性が高まるため、両者の日程調整をしやすいのが大きなメリットです。
契約締結がスピーディーになる
不動産契約を電子契約に切り替えることで、契約締結までの手間と時間を大幅に削減できます。その理由は、紙の書類で手続きをする場合に発生する印刷・製本・封入・発送といった多くの手作業が不要となり、速やかに資料の送信が可能なためです。業務フローが効率化され、スピーディーな契約業務を実現できるでしょう。
印紙税が不要でコスト削減につながる
紙の書類を電子化すると、書類に貼付する収入印紙が不要となるため、印紙税の負担をなくせます。このほかにも、ペーパーレス化によって書類の印刷にかかる「紙代」や「インク代」、書類を発送する際に必要となる「封筒代」や「郵送費」などを削減できるため、コストカットにつながります。これらの全てのコストが削減されることで、年間で換算すると大きな金額の経費削減を実現できます。
契約書類の検索がしやすい
電子契約サービスで保管された契約書類は、システムの検索機能を利用してスムーズに探すことが可能です。日付・取引先名・案件名・金額といった条件を指定するだけで、条件に合致する書類が迅速に見つかります。膨大な紙の書類の中から物理的に探すよりも手間を省けるので、管理業務の効率が高まります。
不動産取引の電子契約のデメリット・注意点
不動産取引を電子化する場合は、いくつか注意しておきたいポイントがあります。続いて、不動産取引の電子契約のデメリット・注意点を解説します。
インターネット環境が必要になる
電子契約を締結するには、両者ともにインターネット環境を整備しなければなりません。その際は、明確にコミュニケーションが取れるよう、ビデオ会議ツールの通信中に映像・音声の大幅な乱れがない状態を確保することが重要です。IT重説に必要な環境の条件を満たせない場合、電子契約ができない点に留意しましょう。
電子契約サービスの利用には一定の費用がかかる
電子契約に切り替える場合、電子署名やタイムスタンプの機能のほか、管理機能やセキュリティ機能が搭載された電子契約サービスを導入すると便利です。ただし、電子契約サービスの利用料金が発生することを押さえておきましょう。導入によって見込める業務効率化やコスト削減などのメリットを考慮しながら、サービス利用をご検討ください。
セキュリティ対策とデータのバックアップが必要になる
電子契約で作成した重要な電子ファイルは、不正アクセスによる情報漏えいや改ざんなどのリスクから守るために、保管場所に適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。また、万が一電子ファイルが破損した場合に備えて、バックアップを取っておくことも重要です。機密情報を含む電子契約書を安全に保存する社内体制を用意しなければなりません。
取引先に電子契約利用の同意を得る必要がある
不動産取引で電子契約を利用する場合は、事前に取引先に電子契約の利用に関して同意を得ておく必要があります。なかでも「媒介契約書」「重要事項説明書」「37条書面(契約締結時書面)」などは、宅建業法において取引先による承諾が必須とされています。同意を得られない場合や、承諾後に相手方から書面契約への変更の希望があった場合は、従来と同様に書面交付を行う必要がある点に留意しておきましょう。
不動産取引の電子契約を行う際に注意すべき法律
不動産取引の電子契約を行う場合、電子署名や電子データの取り扱いに関して、以下の法律に則って運用が求められます。ここでは、押さえておくべき「電子署名法」と「電子帳簿保存法」の概要をご紹介します。
電子署名法
「電子署名法」とは、従来の手書きの署名(サイン)や押印と同等に電子署名を通用させるための法律です。一定の要件を満たす電子署名が行われた場合、その電子文書は本人の意思に基づいて作成された文書と見なされます。また、電子署名法の施行後は、一定の基準を満たす認証サービスを内閣総理大臣および法務大臣が認定する制度が導入されました。
【参考】「電子署名及び認証業務に関する法律」(e-Gov法令検索)
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、契約書を含む国税関係帳簿書類をデータ保存するための法律です。事業者の取引に関わるあらゆる電子データの保存義務や適切な保存方法が、「電子取引」「電子帳簿・電子書類関係」「スキャナ保存」の各制度で定められています。契約書面を電子化する際は、電子帳簿保存法に則ってデータを保存する必要があります。
【参考】「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(e-Gov法令検索)
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025/
まとめ
ここまで、不動産取引の電子契約の流れや、電子化できる・できない契約の種類、電子契約のメリット・デメリットなどを解説しました。現状、不動産業界における多くの契約手続きはオンラインで実施できます。電子契約を実現するには、インターネット環境や電子契約サービス導入などの環境整備が必要となります。不動産会社のご担当者様は、電子契約への切り替えにあたり必要な準備を確認してみましょう。
電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、電子署名法・電子帳簿保存法に対応したおすすめの電子契約サービスです。4,000社以上の機密書類管理ノウハウを踏襲した契約管理機能を搭載。セキュリティ対策と内部統制機能が充実し、データセンター保全体制が整っているので、電子契約を安心してお任せいただけるのが魅力です。不動産業界の電子契約は「WAN-Sign」にご相談ください。