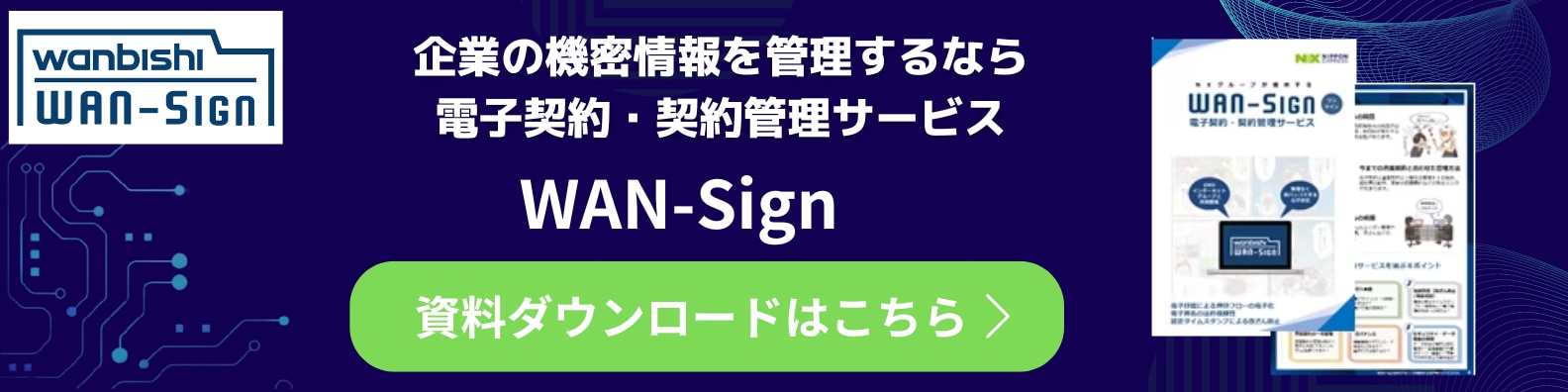電子契約が進まない理由はリスクがあるから?スムーズな導入方法も紹介
(更新日:2024年12月26日)
目次[非表示]
- 1.そもそも電子契約とは?
- 1.1.電子契約とは
- 1.2.電子契約の種類
- 1.3.電子契約の有効性を担保するもの
- 1.4.書面契約との違い
- 2.電子契約の現状
- 2.1.企業が電子契約を導入する理由
- 2.2.電子契約の普及率
- 3.電子契約の普及が進まない主な理由・リスク
- 3.1.①取引先の理解を得ることが難しい
- 3.2.②一部の契約は書面での締結が義務付けられている
- 3.3.③業務フローの変更に伴う社内説明・調整が必要になる
- 3.4.④電子帳簿保存法への対応が必要になる
- 3.5.⑤契約締結日のバックデートに対応できない
- 3.6.⑥電子契約サービスの乗り換えが難しい
- 3.7.⑦サイバー攻撃を受けるおそれがある
- 3.8.⑧書面契約との混在が負担になる場合がある
- 3.9.⑨なりすましのリスクがある
- 3.10.⑩電子署名の有効期限が切れるリスクがある
- 3.11.⑪電子ファイルに対する心理的懸念がある
- 4.電子契約の主な導入メリット
- 4.1.コスト削減につながる
- 4.2.業務を効率化できる
- 4.3.契約締結までの期間を短縮できる
- 4.4.コンプライアンスやガバナンスを強化できる
- 4.5.契約手続きの状況を可視化できる
- 4.6.テレワークに対応しやすい
- 5.今こそ導入のタイミング!電子契約への移行をスムーズに実現する方法
- 5.1.①取引先へ電子契約を導入するメリットを伝える
- 5.2.②取引先によって締結方法を使い分ける
- 5.3.③取引先に対する導入説明会を開催する
- 5.4.④書面と電子文書の一元管理に対応する
- 5.5.⑤セキュリティ対策を導入する
- 6.導入しやすい電子契約サービス「WAN-Sign」の特徴
- 7.電子契約には一定のリスクはあるものの、対策可能でメリットが多い

電子契約は利便性が高く、業務効率化やコスト削減を実現できる点が大きな魅力です。その一方で、「書面契約と比べてリスクがあるのでは?」と懸念し、自社への電子契約の導入をためらっているケースもあるでしょう。
電子契約にはリスクが存在するものの、起こり得るトラブルを把握した上で対策することが可能です。書面契約書とは異なるメリットがあるため、ぜひ従来の書面契約から切り替えをご検討ください。
この記事では、電子契約の概要や種類、普及率の現状や普及が進まない理由などをご紹介します。また、電子契約のメリットやスムーズに移行するためのポイントなども解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも電子契約とは?
電子契約の現状やリスクについて知る前に、基礎知識を押さえておきましょう。ここでは、電子契約の概要や種類、有効性を担保する仕組み、書面契約との違いなどについて解説します。
電子契約とは
電子契約とは、電子データの契約書に「電子署名」を行うことで契約を締結する方法のことです。紙の契約における印鑑の代わりに電子署名や電子印鑑と呼ばれる仕組みを使用し、紙と同様にセキュリティ性を担保しています。
電子署名では、署名者が本人であることを担保する「電子証明書」や、データが改ざんされていないことを示す「タイムスタンプ」という仕組みが使われています。このような技術を用いることで、電子契約は書面契約と同等の法的効力を持って契約を締結できるのです。
関連記事:電子契約とは?4つのメリットを解説
電子契約の種類
電子契約は、電子署名の実行方法によって「当事者型」と「立会人型」に分けられます。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
当事者型
当事者型では、契約を交わす当事者同士が自ら電子署名を行います。この方法を実行するためには、当事者それぞれが認証局に申請して電子証明書を発行してもらわなければいけません。発行に際してはコストが生じる上、手続きの時間がかかる点に留意が必要です。
準備期間が必要で費用がかかるものの、本人性を証明しやすいのは当事者型のメリットです。なりすましのリスクを低下させることができ、法的効力も強いと考えられています。初めての相手との取引や、高額な金額が動く取引などに向いているといえます。
立会人型
立会人型とは、契約の当事者ではなく第三者(電子契約サービス事業者)が電子署名を実行する方式です。「事業者型」と呼ばれることもあります。第三者が電子署名を行いますが、契約する本人の意思によって署名されるとみなされ、法的効力が生まれるとされています。
立会人型の認証は、一般的に電子メールで行われます。取引相手に電子証明書の用意を要求する必要がなく、双方にとって負担が少ない点がメリットです。準備の手間がかからず、手軽に利用できるため、幅広い企業で採用される方法といえます。
当事者型と立会人型のどちらの電子署名が合うかは、企業の方針によって異なります。ただ、電子契約サービスのなかには、当事者型と立会人型のどちらにも対応できるハイブリッド型のサービスもあります。必要に応じて両方を使用できるサービスも検討してみましょう。
電子契約の有効性を担保するもの
電子契約に書面契約のような効力を持たせるためには、以下のような技術が使われます。それぞれの特徴を解説します。
電子署名・電子サイン
電子署名と電子サインは同じ意味で使われることもありますが、厳密には異なるものです。電子署名は電子サインの一種であり、特に法的な有効性が高い点が特徴です。「公開鍵暗号方式」を用い、署名した人物が本人である旨を証明できます。電子契約サービスで電子契約する場合は、基本的に電子署名を行うことになるでしょう。
電子サインは、電子文書の取引における署名や本人確認などの電子プロセス全般のことです。例えば、タブレット端末に表示された契約書にタッチペンで名前を記入したものは電子サインといえます。
電子署名は「電子署名法」において定義されていますが、電子サインは日本の法律において定義が明確にされていないという点も異なります。両者の違いを把握して使い分けるようにしましょう。
電子証明書
電子証明書は電子的な形式の証明書で、信頼のおける第三者機関が発行します。身近な例では、マイナンバーカードに電子証明書が使用されています。
電子署名を実行する際に電子証明書を使うことで、署名をしたのが本人であることを証明できます。証明者となるのが第三者機関となる認証局であり、電子署名の正当性を担保しやすくなる点が電子証明書の強みです。
タイムスタンプ
タイムスタンプは、電子データの作成者や作成日時を証明できるものです。タイムスタンプが記録されたタイミングに電子文書が存在していたことや、内容が改ざんされていないことなどを明らかにできます。
電子契約の場合、時刻認証局(TSA)という第三者機関がタイムスタンプを付与します。単独で利用するのではなく、電子署名と組み合わせることで、より信頼性の高い電子契約を実現できます。
書面契約との違い
電子契約と書面契約はどちらも法的に有効な契約ですが、媒体や署名方法などさまざまな部分に違いがあります。
もっともわかりやすい違いが媒体の形式です。電子契約は電子データ、書面契約は紙で契約書を作成します。電子契約はインターネットを介して行い、書面契約は郵送や持参などで行うのが一般的です。法的効力を持たせるのも、電子契約のほうは電子署名やタイムスタンプ、書面契約は捺印やサインなどです。
書面契約のみ収入印紙が必要であるという点も異なります。印紙税法によると、電子文書は課税文書とならないため、収入印紙は不要です。印紙税の高さに悩んでいる企業は、電子契約を導入することでコスト削減を叶えられるでしょう。
関連記事:電子契約における契約書の文言とは?変更箇所や注意点を紹介
電子契約の現状
便利な電子契約ですが、日本の場合はどの程度普及が進んでいるのでしょうか。ここでは、電子契約への移行が進んでいる背景や、現状の普及率などを解説します。
企業が電子契約を導入する理由
多くの企業が書面契約から電子契約への移行を目指す背景には、まず、関連する法律の整備されていることが挙げられます。電子帳簿保存法などの関連法律の改正や整備が進み、企業が電子契約を導入しやすい下地が整ってきたといえるでしょう。
また、メリットが多いことも理由のひとつです。紙の契約書を減らして電子契約をメインにすれば、印刷代や印紙税、コピー用紙代金、郵送費など、さまざまなコストを節約可能です。紙の保管に必要な場所も削減できますし、業務効率を向上させられる上、リモートワークでも手軽に契約を交わすことが可能になります。
加えて、新型コロナウイルスの流行以降、企業のDXやペーパーレス化が推奨されています。オンライン上での契約が可能で、出社が不要でリモートワークに対応できることも、電子契約が注目を集める理由のひとつです。従来の印鑑による紙面契約から電子契約への切り替えが進むきっかけとなったといわれています。
電子契約の普及率
近年のビジネスシーンでは、書面契約から電子契約へ切り替える流れが進んでいる状況です。
総務省が公表する資料「組織における文書の電子化又は DXに係る課題~統計委員会デジタル部会(2024年6月14日開催)資料」によれば、電子契約を「利用している」と回答した企業の割合は77.9%でした(2024年1月)。
出典:「組織における文書の電子化又は DXに係る課題~統計委員会デジタル部会(2024年6月14日開催)資料」(総務省)p6
なお、電子契約を導入した企業であっても、書面契約の機会が多いケースも見受けられることから、利用率の向上も一つの課題とされています。
関連記事:電子契約の後文の書き方|変更が必要な箇所と文例サンプル
電子契約の普及が進まない主な理由・リスク
業務効率化が可能になるなどのメリットの多い電子契約ですが、いくつかの課題が普及を妨げる一因になっていると考えられています。以下では、電子契約の課題で特に注意が必要な項目について解説します。
①取引先の理解を得ることが難しい
契約の際は、自社だけでなく取引先も電子契約に対応している必要があります。そのなかで、取引先の理解と同意を得ることが、電子契約の導入で大きなハードルとなっています。理解と同意のハードルが高い理由は、紙ベースの契約締結から電子契約の移行に伴い、契約フロー変更に少なからず負担や手間がかかってしまうためです。また、取引先もシステム利用料が発生する場合があったり、電子証明書を利用するために料金を支払う必要があったりします。
もちろん電子契約の利用は、取引先にとっても業務効率化やコスト削減などのメリットがあります。しかし、社内規定の変更が難しく、電子契約の導入が思うように進まないことも想定しておかなければなりません。
②一部の契約は書面での締結が義務付けられている
契約書の一部には、電子化が認められていないものがあります。例えば、以下のような書面が挙げられます(2024年11月現在)。
- 事業用定期借地契約
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
- 任意後見契約書 など
契約とは原則、当事者間の合意があった場合に成立するため、必ずしも契約書等の締結義務はありません。しかし、契約のなかには私文書ではなく、公的に認められた証書(公正証書)での締結を求めているものや、必ず書面の交付を義務付けているものもあります。
相手方からの事前承諾が必要な書類や、高額だったり条件が複雑だったりする取引の契約書の場合は、取引先との調整を嫌って紙による契約をするケースが多いようです。そのほか、結婚届や遺言などの公的書類は、物理的な文書や証人の存在を求められることが多く、完全な電子化は困難とされています。
こうした書面を多く扱う企業でも、電子契約を導入するメリットはあります。基本契約や秘密保持契約、申込書、請求書、雇用契約など、ほとんどの契約書は電子契約によって管理することが認められています。電子化できない契約書も存在するため、電子化できる契約書とできない契約書の比率を事前に確認したうえで、導入を検討するようにしましょう。
③業務フローの変更に伴う社内説明・調整が必要になる
電子契約を導入する際は、社内の業務フローを変更する必要があります。従来の契約業務を変更することに抵抗がある従業員も少なからず存在するでしょう。電子契約を最大限活用するためには、社内説明も行ったうえで、従業員の理解を得ることも大切です。電子契約を実際に利用するのは従業員です。電子契約を導入することの説明を疎かにせず、従業員からの理解を得てから導入しましょう。
しっかりと説明をしなければ、限られた部門のみの利用にとどまってしまい、社内の業務フローが逆に複雑になってしまうおそれがあります。契約管理漏れなどのリスクが生じるため、逆効果にならないよう注意しましょう。
④電子帳簿保存法への対応が必要になる
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類に関して電子データによる保存を認める法律のことです。
電子帳簿保存法では、大きく分けて2つの要件が設けられています。
1つは、保存データの改ざんを防ぎ、文面の訂正・削除などの事実内容を確認できる状態にしておく「真実性の確保」です。そしてもう1つは、保存データの明瞭な閲覧・出力に対応でき、必要なときにすぐに参照できる状態にしておく「可視性の確保」です。さらに、「検索性の確保」や「保存期間」の定めなどもあります。
電子帳簿保存法に準拠した電子取引では、電子契約の契約管理機能を搭載したシステムを導入することで、スムーズに要件に対応できます。
⑤契約締結日のバックデートに対応できない
電子契約では、合意に至った日付の正確性を担保するためにタイムスタンプが用いられます。タイムスタンプを付与した電子契約の場合、実際に契約締結に至った日付よりも前の日付で契約締結日を記載するバックデートに対応できません。
そのため、帳簿書類の正確性を監査法人や第三者に説明する場合にデメリットになることがあります。書面と同様に、多少のタイムラグについては問題とならないケースがほとんどですが、利用するにあたって留意しておきましょう。
⑥電子契約サービスの乗り換えが難しい
現行の電子契約サービスから新しいサービスに乗り換える際、多くの準備期間と作業の手間を要します。例えば、電子契約を全く使えない期間ができないよう、2つのサービスの利用期間を最低でも1ヶ月程度は重なるようにスケジュールを調整しなければなりません。
また、サービスの契約終了に伴い、データの取得ができなくなる可能性も考えて、移行する電子データのバックアップが必要です。サービス選定の際に、移行のしやすさや連携可能なシステムを考慮するなど、選び方を工夫することがポイントです。
関連記事:電子契約とは?メリット、書面契約との比較とともに解説
⑦サイバー攻撃を受けるおそれがある
書面の契約でも紛失のリスクはありますが、電子契約において、サイバー攻撃を受けるリスクは避けられません。重要な顧客情報が漏洩した場合、企業の信頼度にとって致命傷になりかねませんので、パスワードの取り扱いやユーザーの権限管理など、細心の注意が必要です。
⑧書面契約との混在が負担になる場合がある
契約内容や相手方の都合などに応じて書面契約と電子契約が混在することがあります。取引先の承諾が得られない場合は書面での契約が一般的です。また、電子化ができない契約書もあるため、電子契約サービスを導入してからも紙での契約が発生するケースは十分考えられます。
契約担当者は、どちらの方式で契約を締結するかを把握し、それぞれのマニュアルなどに従って適切に契約管理を行う必要があります。
⑨なりすましのリスクがある
メールアドレスなどで簡易的な本人確認を行う場合や、電子署名を使用せずに電子印鑑や電子サインを使う場合、なりすましが可能となってしまうことがあります。
電子契約のなりすましを防ぐには、電子署名法に基づく厳格な電子署名が利用可能なサービスを選ぶ必要があるでしょう。より信頼性の高い電子署名を実施したい場合は、当事者型のサービスを導入することがおすすめです。
関連記事:電子契約とは?メリットとデメリットを紹介
⑩電子署名の有効期限が切れるリスクがある
電子証明書には有効期限があり、更新手続きを行う必要があります。長期的な契約を行う場合はもちろん、契約の終了または継続を決定する際にも、契約期限は把握しておかなければならない点に注意しましょう。
⑪電子ファイルに対する心理的懸念がある
なかには、電子ファイルを用いることに懸念があるという方もいるのが現状です。契約書の実物がないことやメールのやり取りで完結することで、便利な反面、信頼性に欠けると感じてしまう方もいるでしょう。
また、電子契約サービス自体が終了してしまうリスクがあり、そのような懸念点があることもデメリットといえます。
電子契約の主な導入メリット
普及が進まない課題はあるものの、電子契約には多くのメリットがあります。ここでは電子契約の主なメリットを紹介していきます。
コスト削減につながる
電子契約を導入することで以下のコストを削減できます。
- 印紙税
- 書面契約の作成・郵送・管理コスト
- 人的コスト
書面契約の際は必要だった収入印紙が電子契約では不要になります。また、印刷や郵送を行わないためその分だけ業務効率化が可能です。保管のために用意していたファイルや棚も不要になるため、オフィスのスペースを有効活用できるようになります。業務を効率化できるので、不要な残業が減り、人件費の節減にもつながります。
業務を効率化できる
電子契約は、書面契約のような書面作成や押印、郵送などの作業が不要です。システム上で契約書を一元管理できるようになり、過去の文書もすぐに検索して発見できるようになります。書面の場合は1枚の文書を探すのに手間も時間もかかるため、電子化によって作業時間を短縮できるでしょう。また、電子契約サービスのなかには、WebAPI機能搭載のサービスが多く、文書管理ツールやERP、CRMなどとデータ連携することで、契約データを一元管理することが可能です。
書面契約で必要だったスキャンやシステムへの入力といった業務が、電子契約に切り替えることで自動化できるようになる点も魅力といえるでしょう。紙の契約書と電子契約を一括管理できるサービスもあるため、異なる媒体の契約書を併用していく場合も便利です。そういったサービスであれば、過去に発行した書面契約書をまとめて管理することもできます。
契約締結までの期間を短縮できる
書面契約の場合、契約締結するまでに2~3週間かかる場合も多く見られます。一方で、電子契約サービスを活用すると、契約書類さえできあがっていれば、最短1日で契約業務を完了することが可能です。従来よりもスピーディーに取引を開始できるようになるでしょう。
コンプライアンスやガバナンスを強化できる
電子データの場合、内容が改ざんされてしまうリスクがありますが、電子契約は電子証明書やタイムスタンプを採用しており、本人性の担保と改ざんの防止効果があります。信頼性の高い電子契約サービスであれば、コンプライアンスを強化できる点もメリットです。
契約手続きの状況を可視化できる
電子契約システムでは契約状況を可視化できる点もメリットといえます。「依頼中」「締結済」「却下」など、契約ステータスを細かく管理できるサービスが多く、総務担当者が顧客のステータスに応じて適切なアクションを選択することもできます。
テレワークに対応しやすい
電子契約サービスを利用する場合、メールを用いて契約締結が完了するので出社の必要性はありません。そのため、総務部門は「押印のために出社が必要」といわれていましたが、電子契約を導入すればその必要性はなくなり、テレワークなどの働き方にも対応しやすいといえるでしょう。
今こそ導入のタイミング!電子契約への移行をスムーズに実現する方法
電子契約の導入および移行をスムーズに実現するには、自社だけでなく、取引先へのメリットの説明や締結方法の使い分け、書類と電子文書の一元管理などが必要です。ここでは、具体的に何をするべきかわかりやすく紹介します。
①取引先へ電子契約を導入するメリットを伝える
取引先にとって、電子契約の導入メリットでわかりやすいのがコストの削減効果です。デジタル化することで、今まで契約書ごとに必要としていた印紙は無くなり、郵送代やインク代なども削減できます。頻繁に取引を行っている場合、印紙代が不要になれば大きなコスト削減につながります。特に、サービスオーナー企業からの発注金額が大きい取引先の場合、印紙代が無くなるだけでもかなり大幅なコスト削減が可能です。
さらに、電子契約を導入することで業務効率化できるのもメリットです。書面での契約書作成・印刷・郵送・返送といった作業には、多くの手間と時間がかかります。また、途中で契約内容が変更されれば書面を作り変える必要があり、やり取りを繰り返していくことになり、1つの契約を締結するまでかなりの期間がかかります。
電子契約なら印刷は不要であり、郵送・返送といった手間もありません。そのため、途中で契約内容に変更があっても迅速に対処することが可能です。場合によっては1ヶ月程度かかっていた契約締結を1日程度に短縮することができます。これらのメリットは、電子契約に対する理解を得るうえで大きなアドバンテージとなるでしょう。
②取引先によって締結方法を使い分ける
印紙税の削減や業務効率化といったメリットはあるものの、電子契約サービスを導入することにより発生するコストもあります。コスト発生という課題に対して、メリットを訴求するだけでは不十分でしょう。
電子契約には、電子証明書を用いた締結と、メール認証を用いた締結の2種類の締結方法があります。実は、取引先が料金を支払う必要があるのは、多くのサービスの場合、電子証明書を用いた契約締結のみです。
電子証明書を用いるとより厳格な署名となります。ハンコの種類でいうと実印に相当するため、業務委託契約書や金銭消費貸借契約書などに用いられます。それに対して、メール認証での署名は、認印に相当し、請求書・誓約書・見積書などに用いると便利です。どの書類にどちらを用いるかは、各企業にゆだねられています。
課金がどうしても難しい取引先に対しては、まずはメール認証での締結ができる書類から導入し、電子契約のメリットを十分に感じてもらうことも理解を得るためには重要です。2種類の締結方法については、各電子契約サービスによって、片方のみの場合と、両方に対応している場合があるので、事前に確認するとよいでしょう。
③取引先に対する導入説明会を開催する
取引先向け説明会も積極的に開催することが望ましいでしょう。
説明会では、電子契約導入による取引先のメリット・デメリットや導入時の作業イメージ、導入事例、電子証明書・タイムスタンプの説明など、電子契約参加への詳細を伝えることで、取引先からの理解を得やすくなります。
注意しなければならないのが、電子取引への参加を強制してはならない点です。取引先企業が下請けであったとしても、電子取引参加を強制するような行為は下請法などに抵触するおそれがあるため、必ず理解を得た上での参加を目指しましょう。
④書面と電子文書の一元管理に対応する
電子文書で対応できない契約や、取引先に電子契約に同意してもらえなかった場合に関しては、これまでのように書面の契約書で対応が必要です。電子契約サービスによっては、1つのデータベースで書面と電子文書の一元管理ができる機能を搭載しています。異なる文書のタイプであっても効率よく管理できるため、担当者の負担が軽減されます。
⑤セキュリティ対策を導入する
電子契約のセキュリティリスクを低減させ、安心して使えるように対策することも重要です。情報漏洩や不正アクセスなどを防止できるような仕組みを整えましょう。例えば、文書ごとにアクセス権限を設定し、特定の従業員のみが閲覧できるようにする方法があります。従業員全員に研修を行ってセキュリティに対する意識を高めることも大切です。ウイルスソフトの見直しや新規導入なども検討しましょう。
また、セキュリティ対策を重視している電子契約サービスを選ぶのも大事なポイントです。高度なセキュリティ対策を行っているサービスなら、リスクを可能な限り抑えながら電子契約を運用できます。
導入しやすい電子契約サービス「WAN-Sign」の特徴
電子契約を導入するにあたって、これまで述べてきたリスクが不安であり、書面からの切り替えに踏み切れないという担当者の方も多いのではないでしょうか。こうした場合、導入しやすい電子契約サービスを活用することで、スムーズな電子化を実現させられます。
電子契約への移行をお考えなら、幅広い企業で導入しやすい特徴を備えた『WAN-Sign(ワンサイン)』をご検討ください。『WAN-Sign』は、4,000社以上の情報資産を管理するNXワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービスです。無料プランから電子契約締結機能や文書管理機能、内部統制機能、業界最高水準のセキュリティなどをパッケージ化して提供しています。
以下では、『WAN-Sign』のメリットを具体的にご紹介します。
①あらゆる署名タイプに対応可能
WAN-Signは、厳格な実印版締結である当事者型署名、メール認証での簡易的な認印版締結である立会人型(事業者型)署名の両方に対応しています。
取引先の重要度に応じて締結レベルを使い分けられるため、締結プロセスの改善や文書管理の効率化を実現できます。
②高機能のパッケージをリーズナブルな価格で利用可能
WAN-Signなら、電子契約締結に必要な機能を全て含めたパッケージを無料で提供しています。電子契約締結だけではなく、通常の電子契約サービスなら追加費用が必要になる内部統制機能や閲覧権限の設定、IPアドレス制限、高度なセキュリティ機能などを0円で利用可能です。
③社内での電子契約の定着を手厚くサポート
WAN-Signの導入にあたって、電子契約サービスに精通した専属担当者による導入サポートを無料で提供しています。さらに、導入マニュアルの提供や有人のテクニカルサポートデスクによる丁寧なフォローや、1on1でのサポートも付帯します。
また、企業の規模や業種・業態を問わず、導入実績も豊富なため、信頼性の高い電子契約サービスをお求めの方でも安心です。
電子契約をスムーズに全社展開したい企業の担当者様は、ぜひこの機会に『WAN-Sign』の魅力的な導入効果がわかる資料を無料でダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
電子契約には一定のリスクはあるものの、対策可能でメリットが多い
この記事では、電子契約の基礎知識や普及に関する現状、普及が進まない主な理由やリスクなどを解説しました。
電子契約は、移行に伴う取引先からの理解や合意が必要なこと、一部の契約書は電子化できないことなどがデメリットになります。電子化に伴うリスクも加味した上で、導入を検討することが重要です。
一方、電子契約はメリットが豊富であり、従来の紙ベースの方法と比べて業務効率がよく、契約手続きが可視化されるため管理効率もアップします。デメリットを上回る効果が期待できると判断したら、ぜひ導入を進めていきましょう。
電子契約をトラブルなく導入したいときは、あらゆる署名タイプに対応し、高い操作性・機能性・コストパフォーマンスを備えた『WAN-Sign』がぴったりです。当事者型・立会人型のいずれの電子署名も対応可能なほか、外部サービスとのAPI連携によって各種業務を自動化できます。高水準のセキュリティ機能を標準で実装しているのも魅力です。
また、これまでに培った情報管理のノウハウを活かし、紙と電子文書を効率的に一元管理できる機能も備えています。サービス導入前後のサポートも充実しており、不安な点が多い場合も安心です。サービスの詳細が気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。