工事完了報告書とは?作成の目的と記載事項、注意点を解説
目次[非表示]
- 1.工事完了報告書の基礎知識
- 1.1.工事完了報告書とは?
- 1.2.工事完了報告書と作業完了報告書の違い
- 1.3.工事完了報告書を作成する目的
- 1.4.工事完了報告書の作成・提出は義務なのか?
- 1.5.工事完了報告書を提出するまでの流れ
- 2.工事完了報告書の書き方
- 2.1.工事完了報告書の主な記載事項
- 2.2.工事完了報告書を作成する方法
- 3.工事完了報告書の作成時の注意点
- 3.1.できる限り管理番号(工事番号)を割り振る
- 3.2.金額部分で齟齬がないよう事前に確認する
- 3.3.工事終了後、速やかに提出する
- 3.4.工事完了報告書は5年を目安に保存しておく
- 3.5.工事に関する領収書を保管しておく
- 3.6.記載漏れが無いようダブルチェックする
- 3.7.わかりやすい工事写真を撮影する
- 4.まとめ
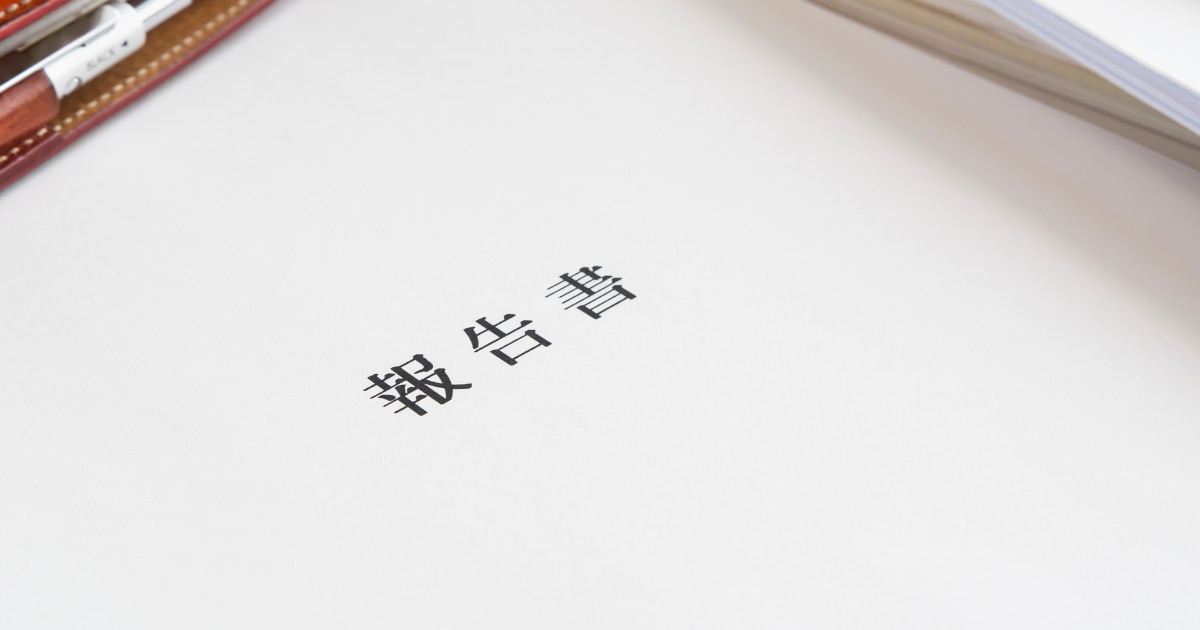
一般的に建設工事が完了した際は、建設業者が元請業者へ工事の完了を証明する「工事完了報告書」を提出します。工事完了報告書は、発注側・請負側の双方が工事の完了を確認し、トラブルを防止する上で重要な役割を担う書類です。
この記事では、工事完了報告書に関する基礎知識や、主な記載事項、書類作成時の注意点などを解説します。建設業界で工事に関連する契約業務や手続きを担当している方は、ぜひ参考にしてみてください。
工事完了報告書の基礎知識
初めに、「工事完了報告書」に関する基礎知識をご紹介します。書類を作成する目的や、作成手順を確認してみましょう。
工事完了報告書とは?
「工事完了報告書」とは、建設業者が工事の完了を報告するための書類です。一般的に施工会社である下請業者が、発注者である元請業者に対して提出します。工事請負契約の通りに工事が完了したことを証明する役割があります。
工事完了報告書と作業完了報告書の違い
「作業完了報告書」とは、特定の作業の完了を報告するための書類です。作業者が顧客や社内担当者に対して提出します。「作業完了報告書」が特定の作業ごとに作成されるのに対して、「工事完了報告書」は工事ごとに作成されます。
工事完了報告書を作成する目的
建設業者が工事完了報告書を作成する主な目的は、元請業者とのトラブル防止です。一方、元請業者は完成確認や証拠保全、経理処理などの目的で工事完了報告書を必要とします。このほかに、物件のオーナーがリフォームローンを利用する際に、金融機関へ工事完了報告書を提出するケースもあります。
工事完了報告書の作成・提出は義務なのか?
工事完了報告書は法律上で作成義務がある書類ではありません。ただし、実務においてはトラブル防止の観点から基本的に作成・提出が推奨されています。また、官公庁や自治体から公共工事を受注するケースでは、一般的に工事完了報告書の提出が義務付けられています。
工事完了報告書を提出するまでの流れ
工事の請負
発注側と請負側が工事請負契約を締結します。契約締結後、建設業者は施工に必要な情報を取りまとめます。
工事の完了
工事が完了したら、工事完了報告書に記載する工事写真やデータなどを整理します。当初と変更が生じた部分があれば明確にしておきます。
工事完了報告書の作成
取りまとめた情報や資料をもとに工事完了報告書を作成します。発注側から提示された提出期限までに完成させましょう。
元請業者へ工事完了報告書を提出
元請業者へ工事完了報告書を提出します。書類を受領した元請業者は、一定期間にわたり書類を保存します。
工事完了報告書の書き方
工事完了報告書を作成する際は、以下の記載項目を盛り込むことが一般的です。ここでは、書類の書き方や作成方法をお伝えします。
工事完了報告書の主な記載事項
基本項目
工事完了報告書には、一般的には以下の項目を記載します。
|
書面には発注側・請負側の正式な会社名や担当者名をそれぞれ記載して、責任の所在を明確にしましょう。また、トラブルが発生した際に迅速に対処するために、住所や電話番号などの連絡先を明記する必要があります。工事請負契約で合意した工事費用(請負金額)や工事内容を正確に記載して、認識の齟齬を避けることもポイントです。
任意項目
工事完了報告書には、任意で以下の項目を記載・添付します。
|
工事写真は、施工前・施工中・施工後の写真をそれぞれ記録に残すことが一般的です。写真の添付によって工事の前後を比較し、完成を証明する意味合いがあります。
工事完了報告書を作成する方法
工事完了報告書を作成する方法には、以下のような選択肢があります。
市販の書式 | 市販されている一般的な工事完了報告書の書式を使用して作成する方法 |
専用アプリ・ツールの書式 | 工事管理アプリやオンライン施工管理ツールなどのシステムの機能を活用して作成する方法 |
元請業者の書式 | 元請業者から提供された専用の書式を使用して作成する方法 |
官公庁指定の書式 | 公共工事の際に官公庁や自治体から指定された専用の書式を使用して作成する方法 |
自社作成のフォーマット | ExcelやWordなどのソフトを使って自社独自のフォーマット(テンプレート)を作成する方法 |
一般的な工事完了報告書は、市販の書式や専用アプリ・ツールの書式で作成可能です。元請業者や官公庁・自治体など発注側から指定がある場合は、指定の書式で作成しましょう。このほかに、自社独自に一からフォーマットを作成する方法もあります。
工事完了報告書の作成時の注意点
工事完了報告書を作成する際は、どんなポイントに注意すれば良いのでしょうか。最後に、書類作成時の注意点を解説します。
できる限り管理番号(工事番号)を割り振る
書類に管理番号(工事番号)を割り振って社内管理することで、どの工事に対する報告書なのかをスムーズに把握しやすくなります。管理業務や問い合わせ対応を効率化するためにも、工事完了報告書には番号を設定することが推奨されます。
金額部分で齟齬がないよう事前に確認する
工事完了報告書に記載する工事費用(請負金額)に誤りがないよう、正確に記入しましょう。その際は、具体的にどの費用を工事費用に含めるのか、契約の段階で発注側・請負側の認識を統一しておくことが大切です。
工事終了後、速やかに提出する
工事完了報告書の提出期限には法的な決まりがないものの、基本的には工事の完了から1週間程度を目安に速やかに提出します。事前に発注側へ期日を確認した上で、スケジュールに余裕を持って作成を進めると良いでしょう。
工事完了報告書は5年を目安に保存しておく
工事完了報告書には法的な保存義務がありませんが、工事実績を証明する書類として、帳簿や関連書類と同様に5年程度保存することが実務上で推奨されています。なお、「建設業法」の第40条第3項、「建設業法施行規則」の第28条において、帳簿や書類の保存期間は以下のように定められています。
(帳簿の備付け等)
第四十条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
【引用】「建設業法(昭和二十四年法律第百号)」(e-Gov法令検索)
(帳簿及び図書の保存期間)
第二十八条 法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
【引用】「建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)」(e-Gov法令検索)
工事に関する領収書を保管しておく
発注側から領収書の提出を求められるケースなど、場合によっては工事完了報告書に領収書を添付することがあります。工事に関する支出の証明となる領収書は適切に保管しておきましょう。
記載漏れが無いようダブルチェックする
作成した工事完了報告書は、記載漏れや誤りが無いよう複数名の担当者によるダブルチェックを実施するのが望ましいといえます。報告業務の正確性を高めるために必要に応じて、社内体制を見直しましょう。
わかりやすい工事写真を撮影する
工事完了報告書に添付する工事写真は、工事場所の状況が明確にわかるように撮影しましょう。撮影の際は十分な明るさを確保し、対象を鮮明に写すことが大切です。
まとめ
ここまで、工事完了報告書に関する基礎知識、主な記載事項、書類作成時の注意点などをお伝えしました。工事完了報告書は法律で作成が義務付けられている書類ではないものの、契約の履行を証明する重要な役割があるため、作成が推奨されています。ご紹介したポイントを参考に、必要な項目に抜け漏れがないよう書類を作成しましょう。建設工事の契約業務では締結から各種書類の発行までやるべき作業が数多くあります。
効率的な契約業務を実現するなら、NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」をおすすめします。専用システムで契約締結を電子化し、契約書を効率的に管理できるのがメリットです。契約業務や手続きを担当している方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。









