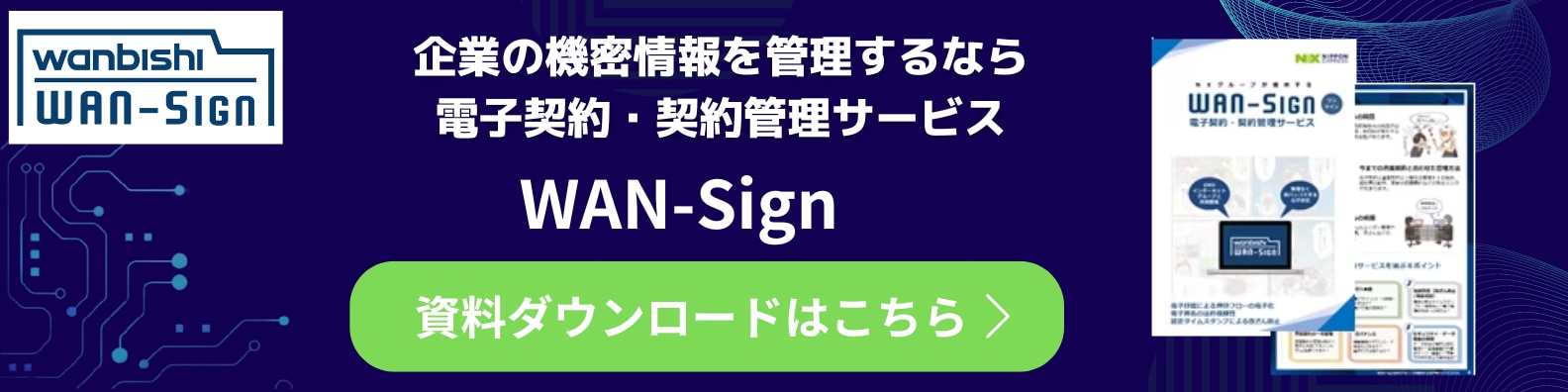覚書の法的効力とは?念書や契約書との違い、作成する際の注意点
目次[非表示]
- 1.覚書の法的効力とは?契約書や念書との違い
- 1.1.覚書とは?
- 1.2.覚書の活用シーン
- 1.3.覚書の法的効力
- 1.4.覚書と念書や契約書の違い
- 2.覚書の記載事項
- 3.覚書を作成するメリットと注意点
- 3.1.覚書を作成する主なメリット
- 3.2.覚書を作成する際の主な注意点
- 4.覚書の効力に関するよくある質問
- 5.法的効力を持つ覚書の作成は電子契約サービスで効率化しましょう

ビジネス上の取引において、当事者間の合意が成立している旨を証明するために「覚書」が作成されることがあります。ただ、契約書や念書といった文書との違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、覚書の基礎知識や念書・契約書との違い、主な記載事項などをご紹介します。また、作成時のメリットや注意点などもお伝えしますので、ぜひ参考にご覧ください。
覚書の法的効力とは?契約書や念書との違い
覚書はどのような文書であり、どういった場面で用いられるのでしょうか。以下では、覚書の概要や契約書・念書との違いなどを解説します。
覚書とは?
ビジネスシーンにおける覚書とは、当事者同士で合意した内容を記録しておくものです。「メモ」や「備忘録」といった意味で使われることもありますが、ビジネス上では契約書の一種として利用されます。
覚書の活用シーン
基本的に、覚書は契約書を補助する目的で作成されます。例えば、以下のような場面で覚書を取り交わすことがあります。
- 契約書の内容を一部だけ変更する
- 大まかな契約内容のみ合意し、後から交渉して詳細を決める など
覚書の法的効力
一般的に、覚書は法的効力を持つ文書とみなされます。覚書を締結した場合、当事者は記載されている内容を守らなくてはいけません。ただし、法的な拘束力を持たせるためには、当事者間で合意を取る、適切な事項を記載するなどの条件を満たすことが求められます。
覚書と念書や契約書の違い
覚書と念書の違い
念書とは、片方の当事者が相手方に対して履行する内容を記載した書面です。覚書の内容は双方が履行する必要がありますが、念書の内容は片方の当事者のみが履行するという点が異なります。また、適切な手順や内容で作成されたものであれば、法的効力は覚書と変わらないといわれています。
覚書と契約書の違い
取引を行う場合は契約書を作成し、書面に残すのが基本です。当事者間の合意事項が記載されている点は覚書と変わりません。ただし、契約書のほうがより細かい内容が記されていることが一般的です。また、覚書も契約書と同じような法的効力を持つことができます。
覚書の記載事項
覚書に法的効力を持たせるためには、最低限必要な事項を記載しておくことが重要です。記載しておきたい項目や、書き方のポイントを解説します。
表題
覚書のタイトルを記載します。「覚書」と書くだけでもかまいませんが、「○○に関する覚書」といったように、文書の内容がわかりやすい表題をつけることがおすすめです。
前文
合意を行う当事者の名称を記載します。「○○株式会社(以下、『甲』)と××株式会社(以下、『乙』)」というように、名称を「甲」「乙」に置き換えることが一般的です。
本文
双方の合意内容を具体的に記載します。複数の内容がある場合は箇条書きで記します。
後文
覚書を何通作成したかを記載します。加えて、作成した覚書を誰が保管するかについても記載しておきます。
日付・署名・捺印
日付は合意が行われた日や、効力が発生する日などを記載します。締結日と効力発生日が異なる場合は、具体的な日付を別途明示しておきましょう。また、合意があることを証明するために、当事者双方が署名・捺印します。
覚書を作成するメリットと注意点
覚書の作成はメリットが多いものの、気をつけておきたいポイントもあります。具体的なメリット・デメリットを確認しておきましょう。
覚書を作成する主なメリット
元の契約書を維持したまま、変更内容を一目で把握できる
契約書の内容を修正・変更することになった場合、一から文書を作成し直すのは手間がかかります。変更内容がわかりにくくなる点も問題です。
覚書を作成することで変更履歴が明確に把握できるようになります。契約書の作成・レビューにかかる負担を軽減できるでしょう。
書面化の手間が少なく、スピーディーに合意内容をまとめられる
覚書は契約書よりも簡潔な内容で作成されることが基本です。文書作成の負担が少ないため、合意内容を速やかにまとめることも可能です。
担当者の変更などによるトラブルを回避しやすい
覚書は、双方の合意があったことの証拠となります。特に中小企業の場合は口頭のみでの合意が行われるケースも少なくありません。口約束のみでは担当者が変わった場合などに十分な引き継ぎがなされておらず、トラブルの原因になることもあるでしょう。万が一に備え、覚書を作成して合意内容を残しておくことがおすすめです。
覚書を作成する際の主な注意点
覚書が増えると契約内容を把握しにくくなる
覚書を増やしすぎると管理が煩雑になり、かえって契約内容がわかりにくくなってしまうことがあります。契約条件の確認などに時間がかかってしまうため注意が必要です。
当事者の甲乙を間違えないよう注意する
覚書に記載する当事者の甲乙は、契約書と同様に記載することがおすすめです。契約書と異なる場合、混乱を招いてしまうケースもあるため気をつけましょう。
影響するすべての書面で整合性の確認が必要になる
覚書を作成する場合は、関連する契約書など、すべての書面で整合性が取れているのかをチェックする必要があります。書類の一元管理ができていない場合、確認の手間が増えてしまうでしょう。
覚書の効力に関するよくある質問
最後に、覚書についてよくある質問をご紹介します。気になる疑問点を解消し、適切な方法で覚書を作成しましょう。
覚書には署名押印が必要?
一般的に、覚書を作成する場合は署名押印を行います。当事者の署名や捺印があることで、覚書の内容に合意した旨を示せます。
覚書を修正したいときはどうする?
覚書を修正したい場合、さらに「覚書を修正するための覚書」を作成します。本文には具体的な変更内容を記載しましょう。
覚書に収入印紙が必要かどうかの判断基準は?
覚書の内容によっては印紙税法上の課税文書とみなされ、収入印紙の貼付が求められることがあります。しかし、収入印紙が必要なのは紙の書類だけです。電子契約の場合は課税文書とみなされず、印紙税が発生しません。収入印紙の貼付も不要です。
法的効力を持つ覚書の作成は電子契約サービスで効率化しましょう
覚書は当事者間で合意が成立したことを証明できる文書です。作成しておくことでトラブルを回避し、契約をスムーズに進めやすくなるというメリットがあります。一方で、書面が増えることによる作業の手間が増える点には留意しましょう。
覚書作成の負担を軽減するには、電子契約サービスを活用することがおすすめです。電子契約であれば印紙税もかからず、文書管理も行いやすくなります。
電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」なら、覚書の作成・管理の効率化を実現できます。電子契約はWeb上で完結できるため、締結までにかかっていた時間を大幅に短縮することも可能です。原契約と覚書を関連文書として紐づけすることで簡単に変更内容も確認できます。紙の文書とデジタル文書の両方を一元管理できるのも大きな魅力です。詳しいプランについて気になる場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。