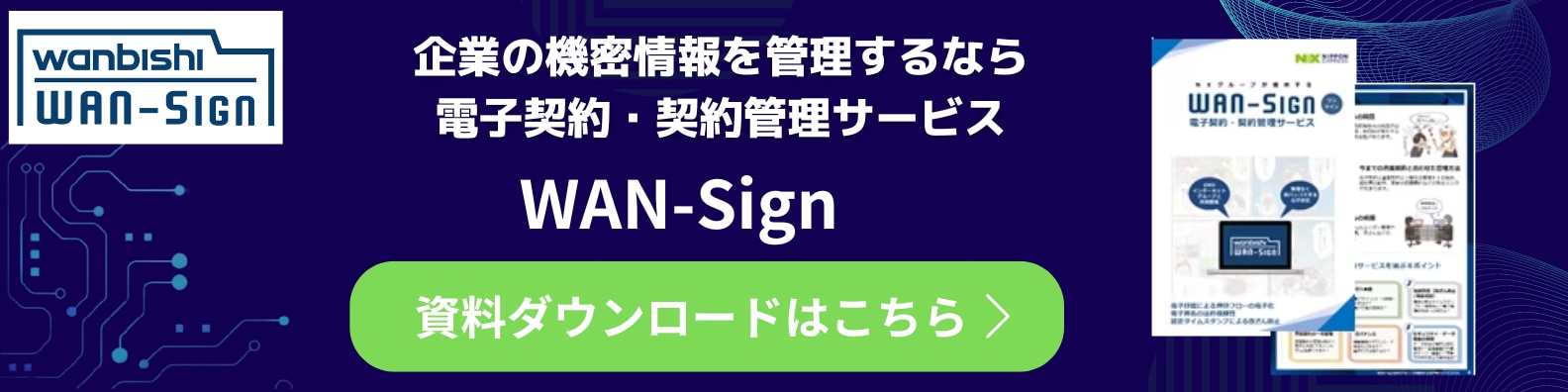契約書の法的効力とは?契約書を作成する理由と無効になるケース
目次[非表示]
- 1.契約書の法的効力とは?
- 1.1.契約書自体に法的効力があるわけではない
- 1.2.契約が持つ効力
- 2.契約書を作成すべき理由
- 2.1.合意内容を確定化・固定化させるため
- 2.2.トラブルや訴訟時の証拠とするため
- 2.3.法律関係を明確化させるため
- 3.契約の効力が無効・取り消し・解除になるケース
- 3.1.無効になるケース
- 3.2.取り消しになるケース
- 3.3.解除になるケース
- 4.契約書を作成する際に注意すべきポイント
- 4.1.必要事項が漏れていないか確認する
- 4.2.取引に関するリスクとリスクをカバーする内容を確認する
- 4.3.第三者が見ても伝わるような内容にする
- 4.4.責任の範囲を明確にしておく
- 4.5.関連する法律、判例を調べておく
- 4.6.契約書に記載してはいけない内容になっていないか確認する
- 5.まとめ
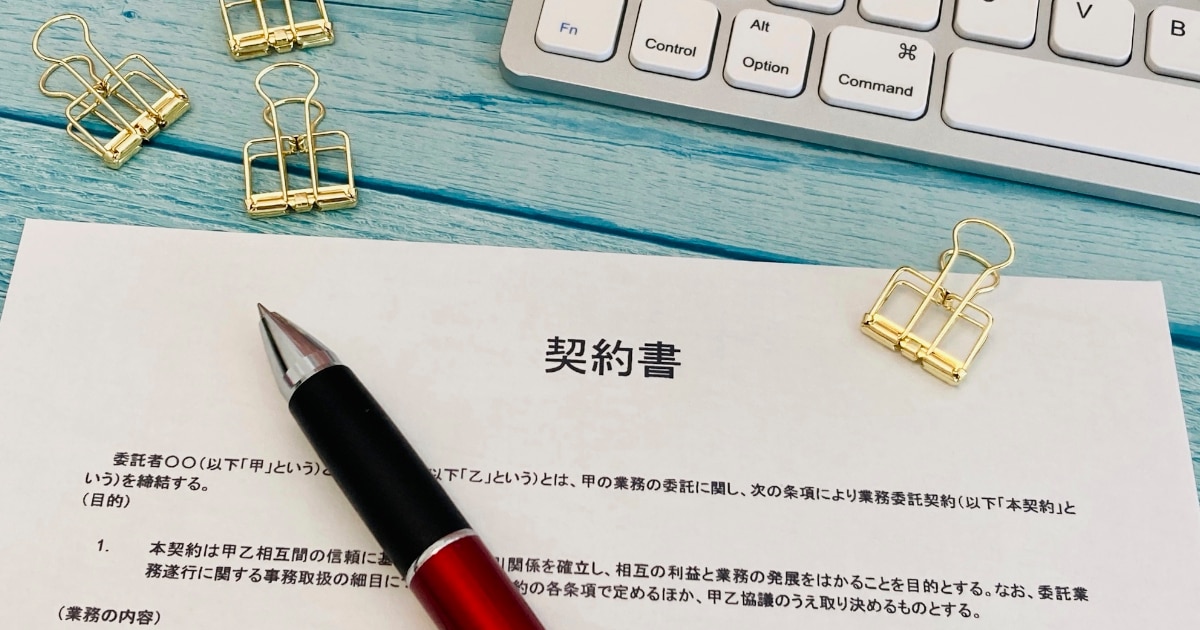
企業間の取引では、契約を締結する際は契約書を交わすケースが多く見られます。「契約書の作成は義務であり、法的効力を持つ」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、実際には一部の例外を除き、契約書の作成は義務ではなく、書面にすることで自動的に法的効力が生じるわけではありません。今回は、契約書の法的効力に関する基礎知識や、契約書を作るべき理由、契約の効力が失われるパターンなどをご紹介します。
契約書の法的効力とは?
まずは、契約書の法的効力や、契約の持つ効力について解説します。基本的な知識を確かめておきましょう。
契約書自体に法的効力があるわけではない
実は、契約書そのものに法的な効力が存在するわけではありません。契約は口頭のみでも成立可能であり、当事者間の合意があれば効力が発生します。
ただし、定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条第1項)のように、契約書の作成が法的に義務付けられている契約もあります。加えて、強制執行認諾文言付き公正証書のように法的効力を持つ契約書もあります。一部の例外がある点を押さえておきましょう。
契約が持つ効力
法的効力
契約成立後、当事者間に債権・債務が発生します。債権者は債務者に対し契約内容の履行を請求でき、履行されない場合は損害賠償や強制執行が可能です。
法的拘束力
契約を締結すると当事者は契約内容に縛られ、勝手に解除できません。債務者は履行義務を負い、双方が取引完了の責任を持ちます。
契約書を作成すべき理由
契約書を作成しなくても契約の効力は生じますが、それでも契約書を作成することには重要な意味があります。具体的な理由を確認しましょう。
合意内容を確定化・固定化させるため
契約が成立するのは、申し込みに対して承諾があり、双方の合意が取れたときです。ただし、口約束のみでは合意内容が不明確になります。契約書の作成により、合意内容を確定・固定することが可能です。
トラブルや訴訟時の証拠とするため
契約書を交わしていなければ、後から「言った」「言わない」で争うことになるケースも見られます。合意内容を明示しておくと、トラブルが起こらないように予防できるでしょう。
また、契約書の有無によって、万が一の事態が起こった際の対応が変わってきます。片方の当事者が契約を守らなかった場合、相手方に裁判を起こし、強制執行や損害賠償などを求めることが可能です。契約内容を明らかにして書面に残しておくことで、トラブルが起こった際にも証拠として提示できます。
法律関係を明確化させるため
契約では取引条件や支払い方法、万一の対処法などを取り決めますが、口頭のやり取りでは記憶が曖昧になり、紛争の原因となる可能性があります。そこで、契約内容を書面に明記することで食い違いを防ぎ、法律関係を明確にできます。
ただし、この効果は契約書に記載された文言が明確で、疑義の余地がない場合に限られます。契約書作成時には、文言の細かい部分まで注意することが求められます。
契約の効力が無効・取り消し・解除になるケース
契約を一度結んでも、理由次第で無効・取り消し・解除となる場合があります。主なケースを見ていきましょう。
無効になるケース
何らかの理由で契約自体が成立していなかったとみなされると「契約無効」となります。例えば、契約内容が反社会的行為に該当するような「公序良俗違反」となる契約は無効です。契約が無効と判断された場合、その契約は最初から成立していなかったものとして扱われます。
取り消しになるケース
一度は契約が成立し法的な効力が生じたものの、当事者の意思表示によって遡って無効とするのが「契約の取り消し」です。契約無効のパターンと異なるのは、当事者の意思表示があるまでは契約が有効になっていることです。
契約当事者が制限行為能力者の場合
未成年者や成年被後見人などの「制限行為能力者」は、単独で有効な法律行為はできないとされています。例えば、未成年者が親の同意なく契約を交わした場合、契約取り消しとなることがあります。
当事者の錯誤による契約の場合
契約において、当事者に錯誤があった場合も契約取り消しになることがあります。例えば、物件の売却代金を誤って記載した契約書を交わした際は、錯誤があったとして契約取り消しとなるケースが見られます。
解除になるケース
法律で定められた要件を満たせば、相手方の同意がなくとも一方から契約を解除できることがあります。主なケースは以下の通りです。
債務不履行の場合
契約解除の代表例の一つが債務不履行です。例えば、売買契約を結んだものの売主が商品を用意できなくなった場合、買主は解除権を行使して代金の支払い義務から逃れられます。
クーリングオフ制度が適用される場合
クーリングオフ制度も、契約解除の一種とされます。期間の制限はあるものの、消費者からの一方的な解除が可能です。
契約書を作成する際に注意すべきポイント
契約書作成時には、以下のようなポイントに留意し、ミスや漏れなく作ることを心がけましょう。ここでは、契約書作成時の注意点を解説します。
必要事項が漏れていないか確認する
一般的に、契約書にはタイトルや前文、契約条項、後文を記載します。加えて、日付欄や署名・記名押印欄なども必要です。ある程度決まった形式の契約を行うことが多い場合、テンプレートを活用する企業も多く見られます。
ただし、契約する状況に応じて盛り込むべき事項は変わってきます。自社でよく扱っているひな形を使う際も、契約締結前に必須事項の漏れがないかしっかりと確認しましょう。
取引に関するリスクとリスクをカバーする内容を確認する
契約に伴い、どのようなリスクがあるのかを明らかにすることが重要です。例えば、商品売買の契約では、納期が遅延するリスクや代金を回収できないリスクなどが考えられます。その上で、トラブルを未然に防ぐための条項を契約書に盛り込みましょう。
第三者が見ても伝わるような内容にする
契約書の文言は、誰が見ても理解できるように書くこともポイントです。当事者のみに伝わるような専門用語や業界用語などを並べるのは、できるだけ避けましょう。
仮に、契約にまつわる事柄で裁判になった場合、裁判官や弁護士などの第三者にも契約書の内容を見せることになります。その際に誤解が生じないよう、一般的な単語や言い回しを用いましょう。
責任の範囲を明確にしておく
契約書には責任の範囲を記載しておくことも重要です。契約締結前に、どちら側にどのような責任が生じるのかを明確にしておきましょう。責任範囲を適切に協議しないまま契約を結ぶと、トラブル時に解決が困難になるケースもあるため注意が必要です。
関連する法律、判例を調べておく
契約を締結する際は、関連する法律や判例を十分に確認しておきましょう。契約書の内容が法令違反となると、契約が無効になる可能性があります。そのため、細心の注意を払う必要があります。
契約書に記載してはいけない内容になっていないか確認する
契約書の形式は決められておらず、基本的に記載する事項は当事者の合意のもと自由に決定できます。ただし、「公序良俗に反する内容」や「強行法規に違反する内容」などは記載すべきではありません。内容に問題がないかを確認しましょう。
まとめ
一部の例外を除き、契約書そのものに効力は発生しないものの、契約を交わす際は書面に残すことが重要です。当事者間の合意内容を明らかにできるほか、問題が発生した際にも証拠として提示することができます。ただし、内容が不適切な場合は無効や取り消しにつながる可能性もあります。契約書作成のコツを押さえておきましょう。
また、契約内容の確認や適切な契約書の作成など、契約関連の業務には煩雑なことが多く、管理の手間が大きくなりやすい傾向にあります。契約書作成・管理のさらなる効率化を目指したいときは、電子契約を導入することがおすすめです。電子契約・契約管理サービスの「WAN-Sign」には、電子契約締結機能や契約管理機能など、充実した機能が備わっています。サービス詳細についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。