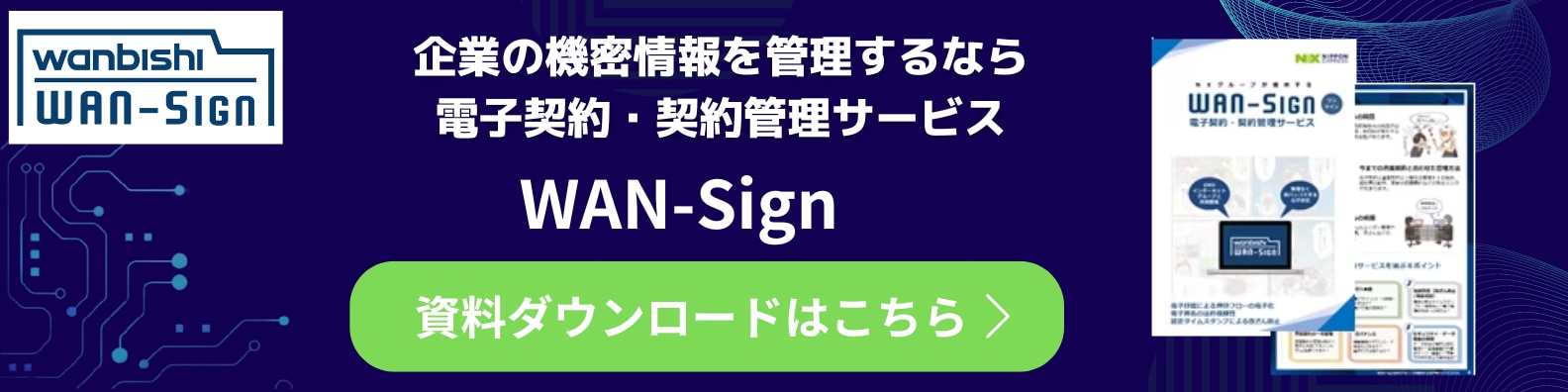契約書を製本する方法|製本の手順と注意点、契印の押し方は?
目次[非表示]
- 1.契約書を製本する理由
- 1.1.改ざん・偽造を防ぐため
- 1.2.印鑑を押す回数を減らすため
- 2.契約書の製本手順
- 2.1.Step1.製本に必要な道具を準備する
- 2.2.Step2.契約書をホチキスで留める
- 2.3.Step3.紙(帯)や製本テープでカバーする
- 2.4.Step4.契印を押す
- 3.契印の押し方
- 3.1.契印を押す場所に決まりはない
- 3.2.袋とじ部分に重なるように押す
- 3.3.署名した全員分の契印を押す
- 4.契約書を製本する際の注意点
- 4.1.製本テープの取り扱いに気をつける
- 4.2.契約書の枚数が多い場合は厚みも測っておく
- 4.3.袋とじを製本する際は十分な時間を確保しておく
- 4.4.契約書を印刷する際は左右の余白を多めにとっておく
- 5.まとめ
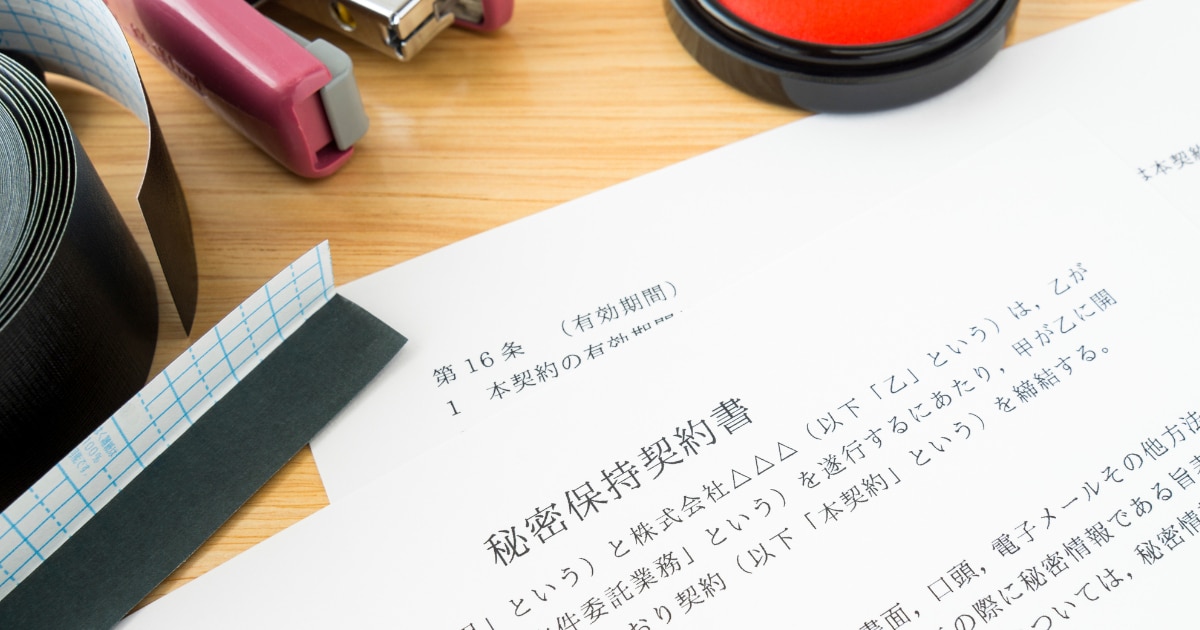
契約書を作成するとき、用紙の枚数が多い場合は製本をすることがあります。見た目が良くなるのはもちろん、その他にも改ざん・偽造を防ぎやすい、印鑑を押す回数を減らせるといったメリットがあります。
契約書をきれいに製本するためには、道具の取り扱いに注意することが大切です。加えて、契印の押し方にも注意しましょう。本記事では、契約書を製本する主な理由や、契約書の製本手順、注意点などをご紹介します。また、契約書管理の課題解決に役立つサービスもご紹介するため、ぜひ参考にご覧ください。
契約書を製本する理由
契約書の製本は、法律によって義務とされているわけではありません。ただし、バラバラのままではさまざまな不具合が起こる可能性があるため、通常は袋とじで製本します。ここでは、契約書に製本が必要な理由を解説します。
改ざん・偽造を防ぐため
契約書を製本する理由の一つが、偽造・改ざん防止です。製本されていない場合、1ページだけ抜き取って文書の内容を変えるといった不正も起こりやすくなってしまいます。しっかりと製本することで、改ざんや偽造を防ぎ、安全に保管できます。
印鑑を押す回数を減らすため
契約書が複数枚にわたる場合、捺印の回数が増えてしまいます。特に、枚数が多い場合は契印を押す手間が大きくなるのがデメリットです。
契約書を作成する際は、文書の差し替えや追加などを防ぐ目的で「契印」を押すのが一般的です。契印とは、複数ページにわたる契約書に連続性があることを示すため、紙のつなぎ目に押す印のことです。
契印と混同されやすいのが「割印」です。割印は書類を2部以上作成する際、それらが同一の文書であることを証明するために押します。例えば、契約書や領収書などの原本と控えを作る場合に用います。割印に使用する印章の規定はありませんが、契印は契約書に署名・捺印したときと同じ印章を使うのが通例です。
契約書を製本していない場合、すべての見開き部分に契印を押す必要があります。製本されているものであれば、表紙・裏表紙のみの押印で問題ありません。印鑑を押す手間を減らせるでしょう。
契約書の製本手順
契約書の製本方法に決まりはありませんが、以下のような手順で行うのが一般的です。ここでは、基本的な製本の流れを解説します。
Step1.製本に必要な道具を準備する
契約書を製本する際は、ホチキスや製本テープもしくは帯、ハサミ、定規などを用意します。事前に道具を揃えておきましょう。
Step2.契約書をホチキスで留める
契約書をホチキスで留めます。留める場所が用紙の端から近すぎると破れやすくなるため、5mm程度は空けましょう。また、枚数が多い場合は3か所、少ない場合は2か所留めます。
Step3.紙(帯)や製本テープでカバーする
ホチキスの針を隠し、見た目を整えるために、紙製の帯や製本テープでカバーします。カバーをつけておくと、ページの抜き取りや差し替えの際に剥がす必要があるため、不正を発見しやすくなるメリットもあります。
Step4.契印を押す
最後に表紙と裏表紙の両方、もしくは片方に契印を押します。契印の押し方については次の見出しでご紹介します。
契印の押し方
契約書の信頼性を高めるためには、契印を適切な方法で押すことが大切です。契印の押し方に関するルールを確かめておきましょう。
契印を押す場所に決まりはない
契印を押す箇所について、厳格な規定は存在しません。ただし、ビジネスマナーとして一般的なルールはあります。例えば、製本されていない場合、契印はページのつなぎ目の上下2カ所に押します。斜め上の1カ所だけホチキス留めしている場合、前のページを半分に谷折りして、次のページと重なる箇所に契印を押すのが基本です。
袋とじ部分に重なるように押す
製本された契約書の場合は、帯や製本テープと表紙・裏表紙が重なる部分に契印を押します。そのため、帯や製本テープは印影の見えやすい明るい色を選びましょう。契約書用の製本テープも販売されているため、専用のものを使うと安心です。
署名した全員分の契印を押す
ご紹介した通り、契印は契約書の署名・捺印で用いられた印鑑と同様のものを使います。署名者全員が、それぞれの契印を押しましょう。
契約書を製本する際の注意点
契約書の製本時には、どのようなポイントに気をつけたら良いのでしょうか。主な注意点を把握しておき、間違いのないように製本しましょう。
製本テープの取り扱いに気をつける
市販の製本テープには、ロール状のものが多くあります。長さを測ってカットした直後は巻き癖がついており、そのまま貼ると、シワができる可能性があります。ズレてしまうケースもあるため、慎重に扱いましょう。製本テープのなかにはA4サイズなどにカットされた状態で販売されているものもあります。巻き癖が気になる場合はこちらを活用するのがおすすめです。
また、製本テープによって粘着力に違いがある点にも留意しましょう。粘着力が強すぎると、思わぬ場所に貼り付いて用紙が破れてしまうことがあります。反対に、弱すぎると剥がれてしまい、糊付けする必要が生じます。
契約書の枚数が多い場合は厚みも測っておく
契約書のページ数が多いときは、厚みを計測してから製本テープをカットしましょう。上下の端を折り返す長さを決めてカットすると、過不足なく綺麗に貼り付けることができます。
袋とじを製本する際は十分な時間を確保しておく
製本作業の時間は十分に確保しておきましょう。時間に余裕がない中で焦って製本すると、シワや破れなどが生じて見た目が悪くなってしまうことがあります。ページが抜けてしまうおそれもあるため注意が必要です。
契約書を印刷する際は左右の余白を多めにとっておく
契約書を用紙に印刷するときは、製本テープを考慮して余白を設けておくことが重要です。文字が製本テープで隠れないよう、十分な余白を確保しましょう。印刷設定に「袋とじ」がある場合は選択すると良いでしょう。
まとめ
契約書の製本を行ったほうが良い理由や具体的な手順、契印の押し方、製本時の注意点などをお伝えしました。契約書の枚数が多いときは、安全性や押印の手間を考慮して製本することが推奨されます。しかし、綺麗に製本するためにはコツが必要です。契約書を作成する機会が多ければ、負担も大きくなるでしょう。
契約書の製本作業をできるだけ減らしたいときは、電子契約を導入することもおすすめの方法です。電子契約なら製本作業に時間を取られなくなり、契約締結までのリードタイム短縮にもつなげられます。紙や製本テープなどの購入費や、印刷代を削減することもできます。契約書の保管・管理の効率化にも有効です。
便利で使い勝手の良い電子契約・契約管理サービスをお探しなら、ぜひ「WAN-Sign」をご検討ください。初期費用無料で、電子契約締結機能や文書管理機能など、幅広い機能をご利用いただけます。サービスの導入前から運用開始後まで、専任の営業担当者が一貫してサポートするため安心です。詳細が気になるときはお気軽にお問い合わせください。