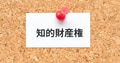顧問契約書の基礎知識|記載項目や作成のポイント、よくある質問を解説
目次[非表示]
- 1.顧問契約書の基礎知識
- 1.1.顧問契約書とは?
- 1.2.そもそも顧問契約とは?
- 1.3.顧問契約と他の契約の違い
- 1.4.顧問契約のメリット・デメリット
- 2.顧問契約書の主な記載項目
- 2.1.契約書名
- 2.2.契約当事者の名称
- 2.3.委託業務の内容
- 2.4.費用
- 2.5.契約期間
- 2.6.契約の解除
- 2.7.秘密保持義務
- 2.8.競業避止義務
- 2.9.損害賠償
- 2.10.知的財産権の扱い
- 2.11.反社会的勢力の排除
- 2.12.管轄裁判所
- 3.顧問契約書を作成する際のポイント
- 3.1.顧問の専門性や経験を確認しておく
- 3.2.契約条件の詳細を明確化しておく
- 3.3.利益相反の可能性を回避しておく
- 3.4.適切な流れで顧問契約を締結する
- 3.5.顧問契約の報酬形態を確認しておく
- 4.顧問契約書に関するよくある質問
- 4.1.顧問契約書に収入印紙は必要?
- 4.2.顧問契約書に収入印紙が必要な場合、費用はどちらが負担する?
- 4.3.顧問契約書に収入印紙が必要な場合、貼らないとどうなる?
- 4.4.顧問契約の一般的な期間の目安は?
- 4.5.顧問契約の報酬の相場は?
- 4.6.法人とも顧問契約を締結できる?
- 5.まとめ
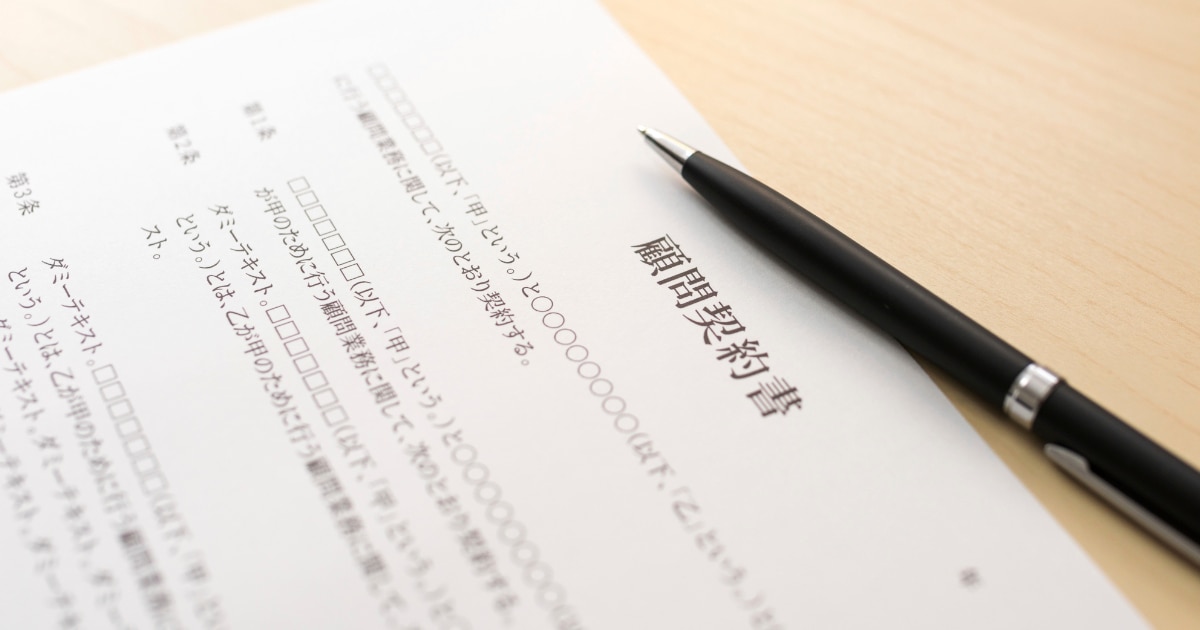
法律や租税に関する専門業務を継続的に外部の専門家へ依頼する場合は、顧問契約を締結します。その際は、顧問先との認識の齟齬を避けてトラブルを未然に防ぐために、契約締結にあたり「顧問契約書」を作成することが一般的です。
この記事では、顧問契約書に関する基礎知識のほか、書類の記載項目、作成のポイント、よくある質問などを解説します。契約業務のご担当者様は、ぜひ参考にしてみてください。
顧問契約書の基礎知識
初めに、「顧問契約書」に関する基礎知識をお伝えします。顧問契約の特徴や、他の契約方法との違いなどの基本を改めて確認してみましょう。
顧問契約書とは?
「顧問契約書」は契約書の一種で、専門家と顧問契約を締結するための書類です。契約書には、当事者が契約内容に合意し、契約が成立したことを証明する役割があります。
そもそも顧問契約とは?
顧問契約とは、専門家へ相談・助言・事務処理などの顧問業務を依頼し、その対価として顧問料を支払う契約のことです。顧問契約を締結する専門家の例として、「弁護士」「税理士」「社会保険労務士(社労士)」「司法書士」「公認会計士」などが挙げられます。
顧問契約と他の契約の違い
業務委託契約との違い
「業務委託契約」とは、外部の受託者に仕事を依頼する契約全般のことを指します。「顧問契約」は業務委託契約の一種で、なかでも専門知識やスキルを有する専門家へ仕事を依頼する契約が該当します。
アドバイザリー契約との違い
「アドバイザリー契約」とは、企業の経営を支援するアドバイザリー業務を外部の専門家に依頼する契約のことです。アドバイザリー契約を締結する専門家の例として「コンサルタント(コンサルティング会社)」や「M&A仲介会社」などが挙げられます。「顧問契約」とは依頼する業務内容に違いがあります。
雇用契約との違い
「雇用契約」とは、使用者が労働に対して賃金を支払う約束をする契約のことです。労働者は使用者の指揮命令に従って幅広い業務を遂行します。一方、「顧問契約」では専門家が契約で定めた特定の業務のみを遂行します。
顧問契約のメリット・デメリット
顧問契約のメリット
企業が顧問契約を締結すると、ビジネスでの対応や判断に高度な専門性を必要とする場面で、速やかに専門家によるサポートを受けられます。長期的に連携する専門家に依頼できるため、自社の立場や状況に即した支援を期待できます。
顧問契約のデメリット
顧問契約は一般的に長期的な契約が前提となるため、短期間での解約が難しい点に注意しましょう。契約を締結する際は、自社が求めるスキルを持ち、相性の良い専門家を見極める必要があります。
顧問契約書の主な記載項目
顧問契約書には、主に以下の項目を記載します。自社の文書のひな形を作成する際は、具体的に明記すべき項目や内容をチェックしておきましょう。
契約書名
契約書のタイトルを記載します。業務内容に応じて「顧問契約書」「法律顧問契約書」「税理士顧問契約書」といった形で設定することが一般的です。
契約当事者の名称
契約当事者である法人・個人の名称や氏名を記載します。また、住所や連絡先なども併せて記載しましょう。
委託業務の内容
顧問契約で委託する業務内容や範囲などを具体的に記載します。例えば「法律相談や契約締結の助言」など、具体的に明記しましょう。
費用
顧問料の金額、支払期日、支払方法などを具体的に記載します。消費税込み・抜きも含めて金額を明確にしておきましょう。
契約期間
契約期間の開始日と終了日を具体的に記載します。また、必要に応じて満了時の更新の有無や条件も盛り込みます。
契約の解除
解約の条件や手続きなどを詳しく記載します。中途解約で発生する違約金や、未払いの顧問料の清算方法なども明記しましょう。
秘密保持義務
顧問契約中や契約終了後の秘密保持義務について記載します。機密情報漏えい防止の観点から重要な項目です。
競業避止義務
顧問契約中から契約終了後の競業避止義務について記載します。事業や顧客の情報を競合他社へ流出させないよう配慮が必要です。
損害賠償
契約違反によって与えた損害を賠償する責任について記載します。損害賠償の範囲や上限金額も盛り込みましょう。
知的財産権の扱い
顧問業務の過程で発生した成果物の知的財産権の帰属について記載します。具体的には、専門家が作成した資料や報告書などが該当します。
反社会的勢力の排除
顧問契約を締結する当事者が反社会的勢力でないことを保証する条項を盛り込みます。また、違反した場合の契約解除について記載することが一般的です。
管轄裁判所
顧問契約に関するトラブル発生時の管轄裁判所を記載します。一般的には、当事者の本店所在地などを管轄する裁判所を記載します。
顧問契約書を作成する際のポイント
顧問契約を締結する際は、相手方とのトラブルを防止するために以下の注意点を押さえておくと良いでしょう。ここでは顧問契約書を作成する際のポイントをご紹介します。
顧問の専門性や経験を確認しておく
顧問業務を依頼する場合は、顧問先の専門性や経験が自社の求める水準に達しているか確認しておきましょう。具体的には、顧問の学位・資格・職歴・実績などの情報を詳細にチェックします。
契約条件の詳細を明確化しておく
顧問契約を締結する際は、あらかじめ詳細な契約条件や業務内容を明確化した上で、契約書に明記することが大切です。顧問先との認識を一致させることで、トラブル防止につながります。
利益相反の可能性を回避しておく
顧問契約により顧客同士の利益相反(=複数の当事者の利益が衝突してしまうこと)が発生しないよう注意しましょう。顧問先が競合他社との利益相反が発生するリスクがないか、事前に調査しておくことが重要です。
適切な流れで顧問契約を締結する
顧問契約を締結する際は、まず電話やメールで専門家へ問い合わせを行い、初回面談を実施した上で、契約内容や契約金額を検討して契約を結ぶ流れが一般的です。自社の業務に適した信頼できる専門家へ相談すると良いでしょう。
顧問契約の報酬形態を確認しておく
顧問契約の報酬形態には、「定額型」「タイムチャージ型」「成果報酬型」の種類があります。それぞれ報酬が発生する条件に違いがあるため、確認しておきましょう。
契約形態 | 報酬が発生する条件 |
定額型 | 月額固定の報酬が発生する。 |
タイムチャージ型 | 顧問が稼働した時間単位で報酬が発生する。 |
成果報酬型 | 業務の成果に対して報酬が発生する。 |
顧問契約書に関するよくある質問
最後に、顧問契約書に関するよくある質問と回答をご紹介します。業務で発生するさまざまなケースに備えて、疑問を解消しておきましょう。
顧問契約書に収入印紙は必要?
顧問契約書は、契約内容によって収入印紙が必要なケースと不要なケースがあります。なかでも収入印紙が必要な具体例は、「請負契約を締結するケース」や「法人同士で3カ月以上にわたり継続的に取り引きするケース」などです。
顧問契約書に収入印紙が必要な場合、費用はどちらが負担する?
「印紙税法」の第3条においては、課税文書の作成者や、共同作成者に納税の義務があるとされています。実務においては、契約当事者がそれぞれ1通ずつ契約書を作成して保管する場合、各自が自身の保管分に収入印紙を添付し、負担するケースが多くなっています。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
【出典】「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」(e-Gov法令検索)
顧問契約書に収入印紙が必要な場合、貼らないとどうなる?
課税文書に収入印紙を貼付しない場合、印紙税の本税と別に過怠税を課されたり、罰則の対象となったりする可能性があります。収入印紙は適切に書面へ貼付して、正しい印紙税額を納めましょう。
顧問契約の一般的な期間の目安は?
顧問契約の契約期間は、一般的に1~3年間となります。場合によっては契約期間中に解約すると違約金が発生するケースもあります。
顧問契約の報酬の相場は?
顧問契約の報酬の相場は、職種や組織の規模によって異なります。中小企業の場合、職種ごとの相場の目安は以下の通りです。
職種 | 中小企業の場合の相場 |
弁護士 | 5万~10万円/月 |
税理士 | 3万~6万円/月 |
社労士 | 2万~5万円/月 |
法人とも顧問契約を締結できる?
顧問契約は法人・個人のいずれとも締結できます。そのため、弁護士法人と顧問契約を締結したり、個人の弁護士と顧問契約を締結したりすることが可能です。
まとめ
顧問契約書は、弁護士・税理士・社労士などの専門家へ顧問業務を依頼する際に用いられる書類です。近年は顧問契約をはじめとした各種契約業務を専門サービスで電子化し、業務効率化を図る企業が多くなっています。NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、顧問契約の締結に対応可能です。低コストで業界最高水準のセキュリティを搭載した電子契約を実現できるため、契約業務のご担当者様はぜひご検討ください。